〚ニュース〛介護業界

□福祉人事.comのSNSでも注目ニュースを配信中!
Instagram / X(旧Twitter) / Facebook
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
このページでは、福祉業界の「介護」に関わるニュースを紹介していきます
■本ページのアジェンダ
・介護業界の週ごとの注目ニュース一覧
2026年2月16日~2月22日の注目ニュース
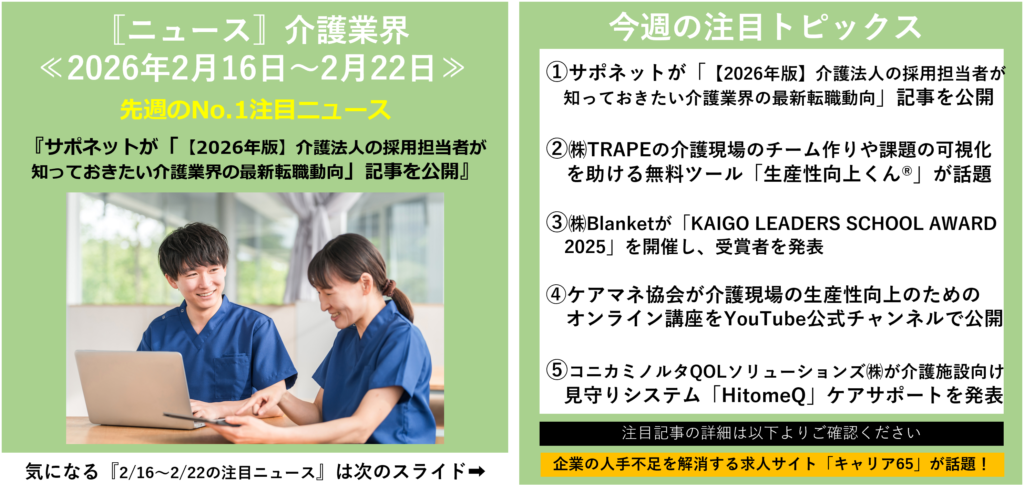
2026年に入り、介護業界の人事・採用を取り巻く環境はさらに大きく動いています。
人材不足は依然として深刻。一方で、生産性向上支援ツールの拡大、ICT活用の推進、人材育成コミュニティの活発化など、現場を支える新たな取り組みも次々と登場しています。
本記事では、「介護業界 人事 採用 ニュース」 を探している人事担当者の方に向けて、今週特に注目度が高かったニュースを5つ厳選し、
・記事の要点
・人事担当者としての学び
・自事業所で今すぐ検討できること
の視点でわかりやすく解説します。
“情報収集”で終わらせず、“行動”につなげるためのヒントとしてご活用ください。
① 2026年版 介護職の転職市場動向
■ 記事の要約
2026年版の介護職転職市場動向をまとめた分析記事。介護業界は依然として売り手市場が続き、求人数は高止まり。一方で求職者は「職場環境」「人間関係」「働きやすさ」をより重視する傾向が強まっている。待遇だけでなく、職場の雰囲気や成長機会の提示が重要になっている点が強調されている。
■ 人事担当者にとっての学び
単に求人を出すだけでは差別化できない時代に入っている。採用広報や面接時の情報開示の質が応募率・内定承諾率に直結する。特に「働きやすさ」を具体的に言語化できるかが鍵。
■ 自分の事業所で検討できること
・求人票に“職場の雰囲気”を具体的に明記
・職員インタビューを活用した採用広報
・面接時にキャリアパスを説明する仕組みづくり
② 生産性向上は準備が8割!無料ツール「生産性向上くん®」
■ 記事の要約
株式会社TRAPEが開発した無料Webツール「生産性向上くん®」の導入が約900事業所に拡大。チーム作り・課題の可視化・タイムスタディなど“準備段階”を支援する機能が充実。国の生産性向上ガイドラインにも沿った設計で、利用料は無料。
■ 人事担当者にとっての学び
生産性向上はICT導入が本質ではない。「現状把握とチーム形成」が成功の前提条件。職員の本音を可視化する仕組みが離職防止にもつながる。
■ 自分の事業所で検討できること
・職員アンケートによる課題の見える化
・生産性向上推進委員会の設置
・加算取得に向けたデータ管理体制の整備
③ KAIGO LEADERS SCHOOL AWARD 2025の受賞者を発表
■ 記事の要約
介護人材育成コミュニティ「KAIGO LEADERS」によるアワード開催。現場発信・教育・リーダー育成に取り組む人材を表彰。介護職の価値向上と発信力強化を目的としている。
■ 人事担当者にとっての学び
“採用前”だけでなく“採用後”の育成設計が重要。外部コミュニティ参加や学習機会の提供はエンゲージメント向上につながる。
■ 自分の事業所で検討できること
・若手職員の外部研修参加支援
・社内発信制度の整備
・リーダー候補の育成プログラム導入
④ 介護支援専門員協会が無料のICT活用オンライン講座を公開
■ 記事の要約
日本介護支援専門員協会が生産性向上に向けたICT活用講座を公開。制度理解から補助金活用、組織戦略までを体系的に解説。誰でも無料視聴可能。
■ 人事担当者にとっての学び
ICT導入は補助金・制度理解とセットで考える必要がある。採用競争力向上の観点からも「ICT活用している職場」は強い。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入状況の棚卸し
・補助金活用の検討
・“DX推進施設”としての採用広報活用
⑤ コニカミノルタが介護支援プラットフォームをリリース
■ 記事の要約
コニカミノルタの見守りシステム「HitomeQ ケアサポート」がAI・画像センシングを活用し、業務効率化とケアの質向上を実現。人手不足解消のソリューションとして注目。
■ 人事担当者にとっての学び
テクノロジー活用は採用力強化に直結する。特に若手やデジタル世代には魅力的な環境づくりになる。
■ 自分の事業所で検討できること
・見守り機器導入検討
・ICT活用を求人票に明記
・業務効率化による離職防止施策
今週の介護業界ニュースから見えてくるのは、単なる採用テクニックの問題ではなく、
・生産性向上の土台づくり
・職員の声の可視化
・ICT活用による働きやすさの強化
・人材育成と発信力の向上
といった“組織力そのもの”が問われているという事実です。
売り手市場が続く中で、求人を出すだけでは応募は増えません。
しかし、
✔ 働きやすい職場づくりを進める
✔ その取り組みを言語化して伝える
✔ 職員の成長機会を設計する
これらを積み重ねた事業所は、確実に「選ばれる側」に回ることができます。
人手不足が深刻化する時代だからこそ、焦って解決策に飛びつくのではなく、“準備8割”の姿勢で一歩ずつ取り組むことが重要です。
採用は単なる人員補充ではなく、組織の未来づくり。
今回のニュースを、自事業所の成長戦略にどう活かすか——それが人事担当者の腕の見せどころです。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年2月9日~2月15日の注目ニュース
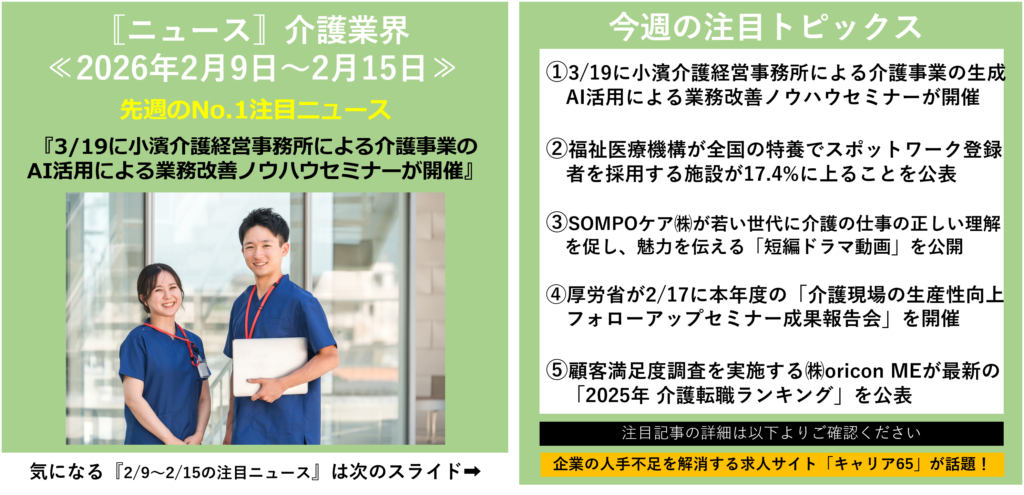
人手不足が続く介護業界では、採用手法の見直しや職場環境の改善、テクノロジー活用など、人事担当者に求められる役割がますます大きくなっています。特に近年は、従来の採用活動だけでは人材確保が難しくなり、「働きやすさの向上」「新しい人材活用」「情報発信力の強化」といった多面的な取り組みが重要になってきました。
そこで本記事では、今週注目された介護業界の人事・採用に関するニュースをピックアップし、人事担当者の視点で解説します。他事業所の取り組みや業界の動きを知ることで、自施設の採用戦略や職場改善のヒントとして活用していただければ幸いです。
① 【3/19開催オンラインセミナー】介護事業における生成AIの活用による業務改善ノウハウ全公開
■ 記事の要約
介護事業所向けに、生成AIを活用した業務改善のノウハウを紹介するオンラインセミナーの開催が発表された。介護現場では記録業務や報告書作成、各種書類対応などの事務作業が多く、職員の負担増加や残業の要因となっている。こうした課題を背景に、AIを活用して文章作成や情報整理を効率化する取り組みが注目されており、今回のセミナーでは実際の活用方法や導入のポイントなどが共有される予定だ。人手不足が続く介護業界において、テクノロジーによる業務効率化は今後ますます重要なテーマとなっていく。
■ 人事担当者にとっての学び
採用が難しい時代において、「人を増やす」だけでなく「業務を減らす」という視点が重要になってきている。生成AIは記録補助や文書作成の効率化など、現場の負担軽減に直結する可能性がある。業務が効率化されれば残業削減や働きやすさの向上につながり、結果として離職防止や採用力の強化にもなる。今後はAI活用の有無が職場環境の差となり、人材確保に影響する時代に入っていく可能性が高い。
■ 自分の事業所で検討できること
まずは記録業務や事務作業のどこに時間がかかっているのかを洗い出し、AIで補助できる部分がないかを検討することが現実的な第一歩となる。いきなり大きなシステムを導入するのではなく、議事録作成や文章整理など小さな業務から試験導入する方法も有効だ。職員の負担軽減が実感できれば、定着率向上や採用PRの材料にもなるだろう。
② 人手不足の特養、約2割がスポットワークを導入 都市部を中心に活用広がる=WAM調査
■ 記事の要約
WAMの調査により、人手不足が続く特別養護老人ホームの約17.4%が、単発バイトなどの「スポットワーク」を導入していることが明らかになった。都市部を中心に活用が広がっており、繁忙時間帯や急な欠員対応として短時間・単発の人材を確保する手段として注目されている。従来の常勤・非常勤だけでは人手不足を補いきれない中、新しい労働力の活用方法として浸透し始めている。
■ 人事担当者にとっての学び
採用が難しい状況では、「フルタイム人材を確保する」ことだけにこだわると現場の負担が増え続ける。スポットワークの活用は、必要な時間帯だけ人材を補える柔軟な手段として有効だ。特に入浴介助や食事介助など時間帯が集中する業務では、短時間の人材活用が現場の疲弊防止につながる。採用の考え方を広げることが、慢性的な人手不足を乗り切る鍵になる。
■ 自分の事業所で検討できること
繁忙時間帯を分析し、「短時間だけ人が欲しい業務」を洗い出すことが重要だ。その上で、スポットワークや超短時間雇用などの仕組みを部分的に取り入れることで、既存職員の負担を軽減できる。いきなり全面導入するのではなく、まずは限定的な業務から試験的に活用することで、現場への影響や運用方法を確認していくとよい。
③ 次世代に介護の“リアル”と“未来”を届ける動画第二弾を公開~仕事選びに悩む若い世代に寄り添い、介護の魅力を伝える短編ドラマ~
■ 記事の要約
SOMPOケアは、若い世代に介護の魅力を伝えることを目的とした短編ドラマ動画の第2弾を公開した。介護職のリアルな姿ややりがい、将来性を描くことで、従来のネガティブなイメージを払拭し、職業理解を促す狙いがある。採用難が続く中で、仕事内容を分かりやすく伝えるコンテンツを通じて、若年層への関心喚起を図る取り組みとなっている。
■ 人事担当者にとっての学び
求人広告だけでは介護の魅力は十分に伝わらない時代になっている。動画やストーリーを使って「働く姿」を具体的に見せることは、応募意欲の向上につながる有効な手法だ。特に若い世代はSNSや動画を通じて職業選択をする傾向が強く、採用活動は「情報発信力」が大きな差を生むポイントになっている。
■ 自分の事業所で検討できること
自施設でも、働く職員の様子ややりがいを伝える写真・動画の活用を検討できる。スマートフォンで撮影した簡単な紹介動画でも、現場の雰囲気が伝わるだけで応募のハードルは下がる。採用ページやSNSでの発信を強化することで、「どんな職場か分からない」という求職者の不安を減らすことができる。
④ 厚労省、生産性向上の成果報告会を17日に開催へ 現場のリアルな実践事例を共有
■ 記事の要約
厚生労働省は、「介護現場における生産性向上フォローアップセミナー」の成果報告会を開催すると発表した。各地の事業所で実践された業務改善やテクノロジー活用の事例が共有される予定で、国としても生産性向上を重要な政策テーマとして位置づけている。人手不足の解消を、人員増加だけでなく業務の見直しによって進めていく流れが強まっている。
■ 人事担当者にとっての学び
今後の人材戦略は「採用」と「業務改善」をセットで考える必要がある。国が主導して生産性向上を推進している背景には、人手不足が長期化するという前提がある。つまり、採用だけで解決する時代ではなく、働き方の見直しや業務の効率化を進める事業所ほど、人材が定着しやすくなるという流れが強まっている。
■ 自分の事業所で検討できること
他施設の改善事例を積極的に収集し、自施設でも取り入れられるものがないか検討することが重要だ。小さな改善でも、職員の負担軽減につながれば離職防止に効果がある。記録方法の見直しや業務分担の再設計など、すぐに始められる改革から着手することで、働きやすい職場づくりにつながる。
⑤ 転職経験のある介護・福祉従事者おすすめの介護転職、2026年最新1位は?
■ 記事の要約
オリコンが発表した最新の「介護転職ランキング」において、カイゴジョブエージェントとマイナビ介護職が同点1位を獲得した。実際に転職を経験した介護職員の満足度に基づいたランキングであり、求職者が転職サービスを選ぶ際の重要な判断材料となる。介護業界において転職市場の存在感が高まっていることを示す結果ともいえる。
■ 人事担当者にとっての学び
どの転職サービスが求職者から支持されているかを把握することは、採用戦略を考えるうえで非常に重要だ。人材紹介会社の活用はコストがかかる一方で、採用成功率を高める有力な手段でもある。求職者の動向を知ることで、自社の求人の出し方や媒体選びを見直すきっかけになる。
■ 自分の事業所で検討できること
現在利用している採用媒体や紹介会社が、自施設の採用ニーズに合っているかを定期的に見直すことが大切だ。ランキング上位のサービスを研究し、どのような層が登録しているのかを把握することで、より効果的な媒体選定ができる。複数のチャネルを組み合わせて母集団形成を強化する視点も重要になる。
今回のニュースから見えてくるのは、「採用のやり方そのものが変わり始めている」という点です。スポットワークの活用、AIによる業務効率化、動画を使った採用ブランディング、国主導の生産性向上施策、転職市場の拡大など、現場を取り巻く環境は大きく変化しています。
人材確保が難しい時代だからこそ、採用だけに頼るのではなく、働きやすい職場づくりや柔軟な人材活用、情報発信の強化を組み合わせることが重要です。今回紹介した動きの中には、すぐに取り入れられるヒントも多くあります。自事業所に合った形で少しずつ取り入れていくことが、安定した人材確保と定着につながっていくでしょう。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年2月2日~2月8日の注目ニュース
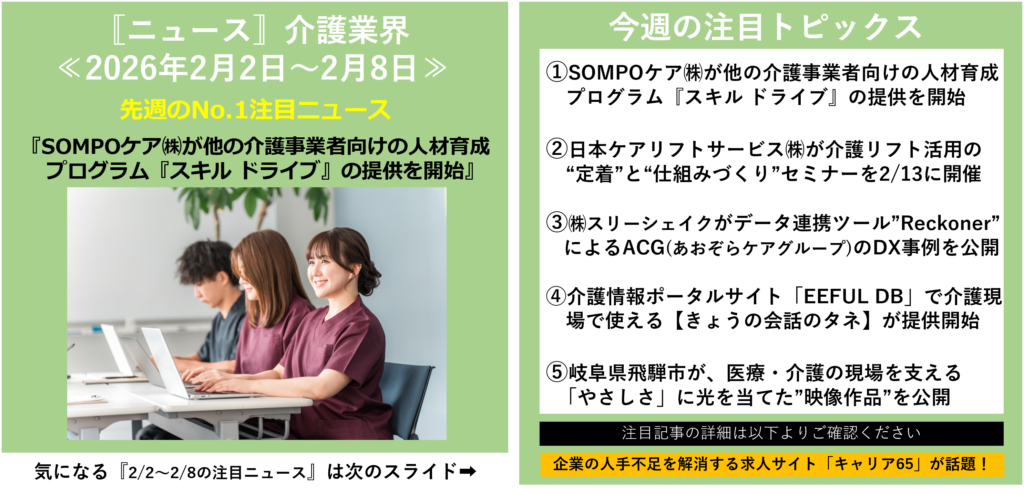
介護業界では、慢性的な人材不足が続くなか、「採用」「育成」「定着」「働きやすさづくり」など、人事担当者に求められる役割はますます重要になっています。特に近年は、単に人を採るだけでなく、教育体制の整備やDXの活用、職場環境の改善、さらには仕事の魅力発信まで、人事領域が大きく広がっているのが特徴です。
そこで本記事では、「介護業界 人事 採用 ニュース」で情報収集をしている方に向けて、今週注目された人事・採用関連のニュースを5本ピックアップし、現場で活かせる視点に落とし込んで解説します。
他施設の取り組みを知ることは、自事業所の採用力や定着率を高めるヒントになります。明日からの人事施策を考える材料として、ぜひ参考にしてください。
① SOMPOケア:人材育成プログラム『スキル ドライブ』提供開始
■ 記事の要約
SOMPOケアは、介護事業者向けの人材育成支援サービス「スキル ドライブ」の提供を開始しました。背景には、深刻化する人材不足と、採用しても育たない・定着しないという業界共通の課題があります。
このサービスは、職員のスキルを可視化するアセスメント機能、動画学習、オンライン研修、実技指導などを組み合わせた総合的な教育プログラムです。職員一人ひとりの成長状況をデータで把握できるため、管理者は教育の成果を確認しながら、適切な指導や配置が可能になります。
単なる研修ではなく、「成長の見える化」によって人材育成を仕組み化する点が特徴で、採用後の育成・定着に重点を置いた取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の対策というと「採用数を増やす」ことに目が向きがちですが、今後は「育てる仕組み」を持つ施設が選ばれる時代になっていきます。
特に重要なのは、
・スキルを言語化する
・成長を可視化する
・教育を属人化させない
という考え方です。
教育体制が整っている職場は、求職者にとって安心材料になります。「未経験でも大丈夫」と言える根拠になるため、採用力そのものを高める武器にもなります。
■ 自分の事業所で検討できること
・新人教育の手順をマニュアル化する
・スキルチェックシートを作る
・動画研修を取り入れる
・育成担当を決める
大きなシステム導入でなくても、「育てる仕組み」を整えるだけで、定着率は大きく変わります。採用と同じくらい、育成に投資する視点が重要です。
② 介護リフト活用の定着をテーマに事例共有イベント開催
■ 記事の要約
日本ケアリフトサービスは、介護リフトの活用をテーマにした「SOEL COMMUNITY ミーティング」を開催。全国の施設による先進事例の共有が行われます。
介護リフトは、職員の身体的負担を軽減し、腰痛対策や離職防止につながる重要な設備です。しかし、「導入したが使われない」というケースも多く、定着には運用ルールや教育が不可欠です。
今回のイベントでは、現場への浸透方法や、使い続けるための仕組みづくりに焦点が当てられています。
■ 人事担当者にとっての学び
離職理由の上位に入るのが「身体的負担」です。つまり、設備投資は人事施策でもあります。
重要なのは、
・設備を入れること
ではなく
・現場に根付かせること
安全に働ける環境づくりは、採用力の向上にも直結します。「腰に優しい職場」というメッセージは、求職者にとって非常に強い魅力になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・腰痛対策の設備導入
・安全な介助方法の研修
・機器使用のルールづくり
・現場の声を反映した改善
「働きやすさ」は最大の採用ブランディングです。小さな改善でも、長期的には大きな人材確保につながります。
③ データ連携ツール導入による介護事業者のDX事例
■ 記事の要約
データ連携ツール「Reckoner」を活用した介護事業者のDX事例が公開されました。各種システムのデータを統合することで、業務効率化や情報管理の最適化を実現した事例です。
介護業界では、勤怠、人事、請求、利用者管理などが別々のシステムで管理されていることが多く、事務作業の負担が大きくなりがちです。データ連携により、入力作業の削減やミス防止が可能になります。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の時代は、「人を増やす」だけでなく「業務を減らす」ことも重要です。
事務作業が多い職場ほど、
・残業が増える
・現場の負担が増える
・離職につながる
という悪循環が起きやすくなります。DXは、採用対策そのものと言えます。
■ 自分の事業所で検討できること
・紙業務の削減
・勤怠管理のデジタル化
・システムの連携見直し
・事務作業の棚卸し
まずは「どの業務に時間がかかっているか」を洗い出すだけでも、大きな改善のヒントになります。
④ 介護現場のコミュニケーション支援コンテンツ開始
■ 記事の要約
介護情報ポータル「EEFUL DB」が、利用者との会話のきっかけを提供する新コンテンツ「きょうの会話のタネ」を開始しました。
日々の会話ネタを提供することで、コミュニケーションを円滑にし、現場の心理的負担を軽減することを目的としています。利用者との関係づくりをサポートするツールとして注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
介護の仕事は「人と向き合う仕事」です。
つまり、働きやすさは
・人間関係
・コミュニケーション
に大きく左右されます。
職員の精神的な負担を減らす取り組みは、結果として定着率を高めます。
■ 自分の事業所で検討できること
・会話のヒント集を作る
・利用者情報の共有を強化
・コミュニケーション研修
・成功事例の共有
小さな工夫でも、現場の雰囲気は大きく変わります。
⑤ 岐阜県飛騨市:介護の魅力を伝えるプロジェクト
■ 記事の要約
岐阜県飛騨市は、医療・介護現場の温かさを音と映像で伝えるプロジェクトを公開しました。現場の「ありがとう」や日常の音を収録し、介護の価値を社会に発信する取り組みです。
人口減少が進む地域では、人材確保が喫緊の課題です。仕事の魅力を伝えることで、地域全体で人材確保につなげる狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
これからの採用は、「求人票だけ」では不十分です。
重要なのは、
・仕事の意味
・現場の雰囲気
・やりがい
を伝えることです。
感情に訴える発信は、応募動機を大きく左右します。
■ 自分の事業所で検討できること
・職員の声を発信する
・日常の様子をSNSで紹介
・施設紹介動画の作成
・理念や想いの言語化
採用は「広報力」で差がつく時代です。大掛かりな制作でなくても、スマートフォンでの発信から始められます。
今週のニュースを通して見えてきたのは、介護業界の人事戦略が「採用中心」から「総合力」へと変化しているという点です。
・教育を仕組み化する人材育成
・身体的負担を減らす職場環境づくり
・DXによる業務効率化
・コミュニケーション支援による働きやすさ向上
・魅力発信による採用ブランディング
これらはすべて、人材不足という共通課題に対する異なるアプローチです。そして共通しているのは、「人が集まり、長く働き続けられる職場をつくる」という視点です。
特別な予算や大きな改革がなくても、
・教育の見える化
・働きやすさの改善
・現場の魅力の発信
といった小さな積み重ねが、採用力を確実に高めていきます。
人材確保が難しい時代だからこそ、他施設の事例から学び、自事業所に合った形で取り入れていくことが重要です。今回のニュースが、採用成功や職場づくりのヒントになれば幸いです。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月26日~2月1日の注目ニュース
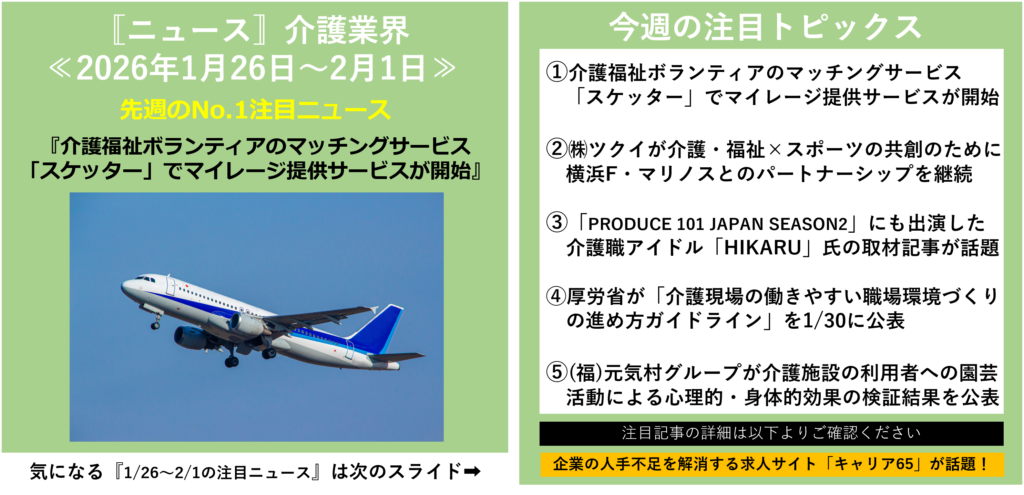
介護業界では慢性的な人手不足が続く中、「どうやって人を採るか」だけでなく、「どうやって人とつながり続けるか」という視点が、これまで以上に重要になっています。給与や求人条件の改善だけでは限界が見え始め、ボランティア導線、業界ブランディング、働き方の多様化、事業所間連携など、人事・採用の考え方そのものが大きく変わりつつあります。
本記事では、2026年1月に発表された介護業界の人事・採用に関する注目ニュース5本を取り上げ、それぞれの内容を「人事担当者の視点」でわかりやすく解説します。単なる業界ニュースの要約にとどまらず、「自社の採用や職場づくりにどう活かせるか」という実務目線で整理していますので、介護事業所の経営者・人事責任者の方は、ぜひ自社施策のヒントとしてご活用ください。
① JAL × プラスロボ|介護福祉ボランティア「スケッター」でマイレージ提供開始
■ 記事の要約
日本航空(JAL)とプラスロボは、介護福祉に特化した謝礼付きボランティアのマッチングサービス「Sketter(スケッター)」において、ボランティア参加者にJALマイレージを付与する新サービスを開始すると発表しました。スケッターは、無資格・未経験者でも介護事業所でボランティア活動ができる地域互助型プラットフォームで、これまでもボランティア経験をきっかけに介護事業所へ入職するケースが多い点が特徴です。今回の連携により、活動者はマイルを特典航空券に交換でき、自身の旅行や遠方エリアでのボランティア活動にも活用可能となります。特に55歳以上のアクティブシニアには追加マイルが付与され、フレイル予防や社会参加の促進という健康面の効果も意識された設計になっています。
■ 人事担当者にとっての学び
この取り組みの本質は、「ボランティア=無償・善意」という従来の枠組みから、「参加インセンティブを設計した人材導線」へと進化させている点にあります。給与や時給だけで人材を集めるのではなく、マイレージという“非金銭報酬”を活用することで、介護業界に関心を持つ潜在層の参加ハードルを下げています。特に、採用広告ではリーチしづらいシニア層・社会貢献志向層・副業層などを自然に巻き込める点は、従来の採用施策にはない発想です。人材不足の時代においては、「いきなり採用」ではなく、「まず関係人口として接点をつくる」という考え方が、今後ますます重要になります。
■ 自分の事業所で検討できること
自社でも、いきなり求人応募を求めるのではなく、「職場体験」「お手伝い参加」「ボランティア受け入れ」などの軽い関与ステップを設けることは十分可能です。たとえば、レクリエーション補助、イベント運営サポート、見守りなど、資格不要の業務を切り出し、地域住民が参加できる仕組みをつくることで、将来の採用候補者プールを形成できます。重要なのは、参加者にとって“参加する意味”を可視化すること。金銭報酬でなくても、感謝状、地域ポイント、福利厚生連携など、インセンティブ設計次第で関係人口は着実に増やせます。
② ツクイ × 横浜F・マリノス|スポーツ連携による介護業界ブランディング
■ 記事の要約
ツクイは、プロサッカークラブ横浜F・マリノスとのパートナーシップを継続し、スポーツイベントを通じて介護・福祉の社会的価値を発信する取り組みを継続すると発表しました。スタジアムでの啓発活動や共同イベントなどを通じて、一般層に介護業界を身近に感じてもらうことを目的としています。これは単なるスポンサー活動ではなく、介護業界のイメージ向上や、将来の人材確保を見据えた中長期的なブランディング施策と位置付けられています。
■ 人事担当者にとっての学び
この事例のポイントは、「採用広告を出さずに、採用につながる母集団を育てている」点です。多くの事業所では、求人票や人材紹介会社に依存した“刈り取り型採用”になりがちですが、ツクイは「介護を知らない層」に対して、まずポジティブな接点を作ることに投資しています。採用市場が厳しくなるほど、知名度・イメージ・共感性といった“非スペック要素”が、応募数を左右します。つまり、これからの人事は「採用担当者」であると同時に、「広報・マーケティング担当者」でもある、という視点が不可欠です。
■ 自分の事業所で検討できること
大企業のようなスポンサー契約が難しくても、地域レベルでの連携は十分可能です。たとえば、地元スポーツチーム、学校行事、地域イベントへの協賛・参加を通じて、施設名や仕事内容を知ってもらう機会を増やすだけでも効果があります。「求人を出す前に、まず知ってもらう」という意識を持ち、広報活動を採用戦略の一部として位置付けることが重要です。
③ “アイドルで介護職員” HIKARU|パラレルキャリアという新しい人材像
■ 記事の要約
介護職として働きながら、アイドル活動も行うHIKARUさんのインタビュー記事では、「介護×芸能」という異色のキャリアが紹介されています。介護現場でのリアルな経験と、芸能活動で培った表現力や発信力を両立させることで、自身の生き方そのものを価値として発信しています。介護の仕事を「一生の専業職」と捉えるのではなく、「複数の顔を持つキャリアの一部」として位置付けている点が特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
この事例が示すのは、「介護人材=フルタイム正社員」という固定観念の限界です。副業解禁や働き方の多様化が進む中で、介護職も“人生のすべてを捧げる仕事”ではなく、“キャリアの一部として選ばれる仕事”へと再定義されつつあります。パラレルキャリアを許容することで、これまで介護業界に来なかった層(クリエイター、フリーランス、学生、副業層)を取り込める可能性が広がります。
■ 自分の事業所で検討できること
副業OK、短時間勤務、週3日勤務など、柔軟な雇用設計を検討するだけでも、人材プールは大きく広がります。「介護だけで食べていける人」ではなく、「介護もやりたい人」を受け入れる設計に変えることで、結果的に応募数・定着率の向上につながります。
④ 厚労省|介護事業の「協働化・大規模化ガイドライン」を公表
■ 記事の要約
厚生労働省は、介護事業の持続性を高めるため、「協働化・大規模化」に関するガイドラインを公表しました。これは、複数の事業所が連携し、人材育成、採用、業務効率化を共同で行うことで、経営基盤を強化する方針を示したものです。特に、人材確保や教育コストの共有、管理部門の統合などが具体例として挙げられています。
■ 人事担当者にとっての学び
このガイドラインが示すのは、「単独事業所モデルの限界」です。今後、1事業所だけで採用・育成・定着を完結させるのは、現実的にますます困難になります。人材は“自社で囲い込むもの”から、“地域でシェアするもの”へと発想を転換する必要があります。人事戦略も、競争から協調へとパラダイムシフトが起きています。
■ 自分の事業所で検討できること
近隣事業所との合同研修、共同採用説明会、人材バンクの共有など、小さな協働から始めることが可能です。「うちは小さいから無理」ではなく、「小さいからこそ連携する」発想が、これからの生存戦略になります。
⑤ 元気村グループ|園芸活動による心理的・身体的効果の検証
■ 記事の要約
社会福祉法人元気村グループは、介護老人保健施設において園芸活動を導入し、高齢者の心理的・身体的効果を検証しました。利用者の「畑仕事がしたい」という希望をもとにプログラムを設計した結果、生活リズムの改善、不安感の軽減、意欲向上といった効果が確認されました。
■ 人事担当者にとっての学び
この事例は、利用者満足だけでなく、職員の働きがいや職場の雰囲気にも好影響を与える点が重要です。レクリエーションが活性化することで、職員側も「ありがとう」「楽しかった」というポジティブなフィードバックを得やすくなり、感情労働の負荷が軽減されます。結果として、離職防止やエンゲージメント向上にもつながる“間接的人事施策”といえます。
■ 自分の事業所で検討できること
アクティビティを単なるサービス提供ではなく、「職場改善施策」として再定義することがポイントです。園芸、音楽、体操、地域交流など、利用者と職員の双方が楽しめる取り組みを増やすことで、「働きやすい職場」は自然と出来上がっていきます。
今回取り上げた5本のニュースに共通しているのは、介護業界の人事戦略が「募集・採用中心」から「関係づくり・環境づくり中心」へとシフトしている点です。
ボランティアを入口にした関係人口づくり、業界イメージを高めるブランディング施策、副業やパラレルキャリアの容認、事業所同士の協働、そして職員が前向きに働ける職場設計――いずれも、人を“集める”よりも、人と“つながり続ける”発想に基づいています。
これからの介護人事に求められるのは、求人票を改善することだけではありません。
「介護の仕事を知ってもらう」「関わるきっかけをつくる」「続けたいと思える環境を整える」という3点を、採用戦略と一体で設計していくことが、結果的に最も強い人材確保策になります。
人事・採用は、もはや現場の業務ではなく、経営戦略そのものです。
今回のニュースをヒントに、自社の採用のあり方を一度見直してみることが、これからの介護経営における大きな一歩になるはずです。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月19日~1月25日の注目ニュース
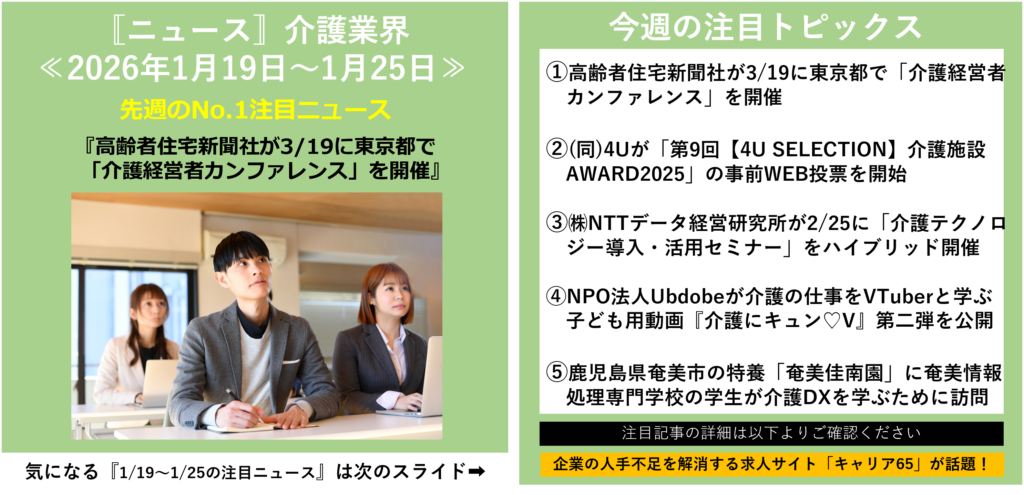
介護業界では今、人材不足が常態化する中で「どう採用するか」だけでなく、「どう定着させ、どう育てるか」まで含めた人事戦略が強く求められています。単に求人広告を出すだけでは応募が集まりにくくなり、採用コストも上昇傾向にあります
一方で、現場ではDXの活用、処遇改善、キャリア設計、業界ブランディングなど、これまでとは異なるアプローチによる人材確保の動きが加速しています。
本記事では、今週の介護業界で注目度が高い人事・採用関連ニュースを5本厳選し、それぞれについて「人事担当者にとっての学び」と「自社で検討できる具体策」の視点から解説します。制度改正やテクノロジー活用、若年層への業界認知づくりなど、短期施策から中長期戦略まで幅広く取り上げていますので、人材確保に課題を感じている介護事業者の方は、ぜひ自社の施策づくりのヒントとしてご活用ください。
① 3月19日開催 第2回 介護経営者カンファレンス
■ 記事の要約
介護業界専門紙「高齢者住宅新聞」が、介護経営者向けに開催するイベント。2026年3月19日(木)10:00〜17:00、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO(東京・京橋)で実施されます。入場・セミナー聴講は無料(抽選・招待制、当日先着の注意あり)。特徴は「全12講座」の講演・座談会と、介護事業者向けの最新ソリューションを相談できる出展ブース、そして経営者交流会まで含む“1日で潮流をつかむ設計”。テーマも、2027年度の介護保険制度改正・処遇改善、人材のキャリアと賃金設計、介護DX/生成AI、生産性向上など、人事・採用に直結する内容が並びます。
■ 人事担当者にとっての学び
採用が厳しい時代ほど、「求人を増やす」だけでは限界が来ます。このカンファレンスの示唆は、制度改正×賃金設計×生産性×DXを“採用と定着”に結びつけて考えること。たとえば、処遇改善を“配るだけ”で終わらせず、キャリアや評価と連動させると、応募動機(納得感)と定着(将来像)を同時に強化できます。さらに、生産性向上・DXは現場負担の軽減だけでなく、「働きやすい職場」という採用広報の武器にもなります。講座テーマがまさにその論点を横断している点が、人事にとって大きな学びです。
■ 自分の事業所で検討できること
・賃金とキャリアの再設計:処遇改善の配分ルールを、役割/評価/成長とセットで見直す(“説明できる賃金”に)。
・生産性KPIの設定:記録、連携、会議、移動など“時間が溶ける業務”を棚卸しし、月次で改善。
・採用広報の更新:DXや研修、キャリア設計を求人票/説明会の定番トークに組み込む(応募の質が上がる)。
・経営×人事の連携会議:制度改正/報酬改定の情報を、人件費計画と採用計画に落として“先手”を打つ。
② 正解のない介護現場で、施設はどんな挑戦をしてきたのか(介護施設AWARD2025)
■ 記事の要約
合同会社4Uが主催する 「4U SELECTION 介護施設AWARD2025」に関する発表で、現場の挑戦を“評価ではなく共有”として可視化する趣旨が語られています。今回テーマは 「越境(Boundary Crossing)」。地域・多世代・異分野とつながりながら価値をつくる全国7施設をノミネートし、事前WEB投票(1/22〜2/27)と当日投票の合算で「共感」を集めた施設ベスト3を選出、最も共感を得た施設を年間大賞にする参加型の仕組みです。イベント当日は、成功談だけでなく葛藤や失敗も含めた“リアルなプロセス”を語るトークセッションや交流の場も用意されています。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の解決策は、待遇や募集チャネルだけでなく、「現場の誇り」や「共感される物語」をどう作るかに広がっています。AWARDの設計は、現場の実践を外部に共有し、他施設の学びへ変換する“知の循環”そのもの。人事の観点では、①採用広報に使える具体的エピソードが増える、②職員が自分たちの仕事を言語化でき、エンゲージメントが上がる、③他施設の工夫から定着施策のヒントを得られる、という効果が期待できます。「静かな違和感(良い取り組みが伝わらない)」を解消する仕掛けは、採用競争が激しいほど価値が増します。
■ 自分の事業所で検討できること
・“越境”の棚卸し:地域連携、多世代交流、異業種連携など、自施設の取り組みを3つ言語化し採用広報へ。
・現場発のストーリー収集:月1回、職員から「最近の挑戦/学び」を短文で集め、面接/説明会の素材にする。
・共感指標の導入:利用者満足や稼働率だけでなく、職員が誇れる取り組みを“見える化”して称賛する。
・外部発信の習慣化:成功だけでなく、試行錯誤も含めて発信し“共感で集まる採用”の土台を作る。
③ 〖2/25(水)ハイブリッド開催〗介護現場と開発企業がつながる!介護テクノロジー導入・活用セミナー
■ 記事の要約
NTTデータ経営研究所によるセミナー告知で、2026年2月25日にハイブリッド形式で開催。対象は介護事業者、介護テクノロジー開発企業、政策動向に関心のある層など幅広く、参加費無料。定員は現地100名・オンライン300名(予定)、申込締切は2月16日。プログラムには、介護テクノロジー関連の政策動向(経産省・厚労省)、介護事業者向けの導入・定着の視点、メーカーによる導入事例紹介、ネットワーキング、さらに現地のみ個別相談会も含まれています。単なる製品説明ではなく、導入定着の“現場実装”に踏み込む構成が特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の局面では、採用強化と同時に「辞めにくい現場」を作ることが重要です。テクノロジー導入は、記録・移動・情報連携の負担を下げ、現場の疲弊を減らすことで定着に効きます。さらに人事目線では、①“働きやすさ”を求人で具体化できる、②新人教育の再現性が上がり戦力化が早まる、③管理者のマネジメント負荷が下がり離職連鎖を防ぐ、という効果が狙えます。本セミナーは政策動向も扱うため、補助制度や推進施策の流れを早期に掴み、投資判断と採用戦略をつなげる学びが得られます。
■ 自分の事業所で検討できること
・“導入前提”の業務棚卸し:記録/申し送り/インカム/見守り等、効果が出やすい領域から優先順位をつける。
・小さく試すPoC:いきなり全体導入ではなく、1ユニット/1フロアで試し、定着条件(運用ルール/教育)を固める。
・求人票の改善:「ICT活用」「業務効率化」などを、具体例付きで記載し応募ハードルを下げる。
・個別相談会の活用:現地参加なら、導入/運用の悩みをその場で相談し、失敗コストを下げる。
④ 介護の仕事をVTuberと学ぶ子ども向け動画コンテンツ『介護にキュン♡V』の第二弾を公開
■ 記事の要約
NPO法人Ubdobeが、子ども・若年層向けに介護の仕事を学べるVTuber動画シリーズ 『介護にキュン♡V』第二弾を公開。大阪府の介護人材不足の状況(有効求人倍率が高水準、2026年に不足見込み等)を背景に、“介護=大変”という先入観を変え、「人の人生を支える仕事」の本質的魅力を届けたいという狙いが説明されています。第二弾のテーマは「介護の仕事ってどこでしているの?」で、在宅・施設・まちの中など、活躍の場が一つではないことを分かりやすく伝えています。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースの肝は、採用を“短期の充足”だけでなく、中長期の母集団形成(業界認知)として捉えている点です。高校生・大学生の進路選択は、日頃触れる情報で大きく変わります。介護の仕事を「近くにある」「多様である」「社会的意義がある」と伝える発信は、将来の志望者だけでなく、保護者・教員・地域の理解も広げます。人事としては、採用広報のチャネルを求人媒体だけに閉じず、SNSや動画など“理解を作る”施策へ拡張する必要がある、という示唆になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用広報の再設計:若年層向けに「介護の仕事の種類」「働く場所の多様性」を短尺で発信する。
・職場見学の“入口”を軽く:応募前見学や体験を増やし、先入観の壁を下げる。
・学校/地域との接点づくり:学校説明会、地域イベント協賛など“未来の応募者”との接点を持つ。
・動画素材の内製:自施設の「1日の流れ」「職種紹介」を30〜60秒で作り、求人に添付して理解促進。
⑤ DX活用の可能性探る 学生14人が介護施設を見学(奄美情報処理専門学校)
■ 記事の要約
記事タイトルが示す通り、情報処理系の学生が介護施設を見学し、DX活用の可能性を現場で学ぶ内容です。ポイントは「介護×IT」を“机上の理想”ではなく、施設のリアルな業務(記録、情報共有、見守り、連携など)に結びつけて捉えている点。介護現場側にとっては、DXを推進する担い手候補(IT人材・学生)と接点を持つ機会になり、学生側にとっては、社会課題の現場に触れて将来のキャリア選択の視野が広がります。地域単位での人材循環(学び→就職→定着)を作る動きとして注目できます。
■ 人事担当者にとっての学び
採用難の時代は、即戦力だけを追うと母集団が先細りします。そこで有効なのが、「教育機関との連携」と「職業理解の早期化」。介護職だけでなく、IT・事務・企画など多職種連携の入口を増やすことで、介護施設の採用ポートフォリオが厚くなります。さらにDXは、“システム導入”がゴールではなく“業務が回る”ことがゴール。学生見学や共同プロジェクトは、現場の課題を言語化し、改善テーマを切り出すきっかけにもなります。人事はこの流れを「採用(入口)」と「業務改善(定着)」の両面から設計するのがポイントです。
■ 自分の事業所で検討できること
・学校連携メニューの整備:見学、職場体験、課題研究(介護DXの提案)などをパッケージ化する。
・DXテーマの“教材化”:記録効率、申し送り、シフト、業務導線など、学生が理解できる課題として提示する。
・多職種採用の拡張:介護職以外に「DX推進補助」「事務×現場支援」など、入口職種を作る。
・受け入れ体制の型化:見学当日の案内資料/説明者/フィードバックをテンプレ化し、継続実施しやすくする。
今回紹介した5つのニュースから共通して見えてくるのは、介護業界の人事・採用はすでに「求人を出して待つ時代」から、「職場の価値をつくり、伝え、育てる時代」へと移行しているという点です。
経営者カンファレンスに象徴されるように、賃金・キャリア・DX・生産性はすべて採用と直結しています。また、介護施設AWARDやVTuber活用のような取り組みは、採用そのものを“広報・ブランディング”として捉える発想を示しています。さらに、介護テクノロジーセミナーや学生見学事例からは、DXや教育機関との連携が、将来の人材確保と業務改善を同時に実現する可能性が見えてきます。
人材不足を嘆くだけではなく、
・現場の負担を減らす仕組みをつくる
・仕事の魅力を言語化して発信する
・若い世代との接点を増やす
こうした取り組みを積み重ねることが、結果的に「採用しやすく、辞めにくい職場」を生み出します。今後の介護経営において、人事は単なる裏方ではなく、事業成長の中核を担う戦略領域です。今回のニュースをきっかけに、ぜひ自社の人事・採用施策を一度見直してみてはいかがでしょうか。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月12日~1月18日の注目ニュース
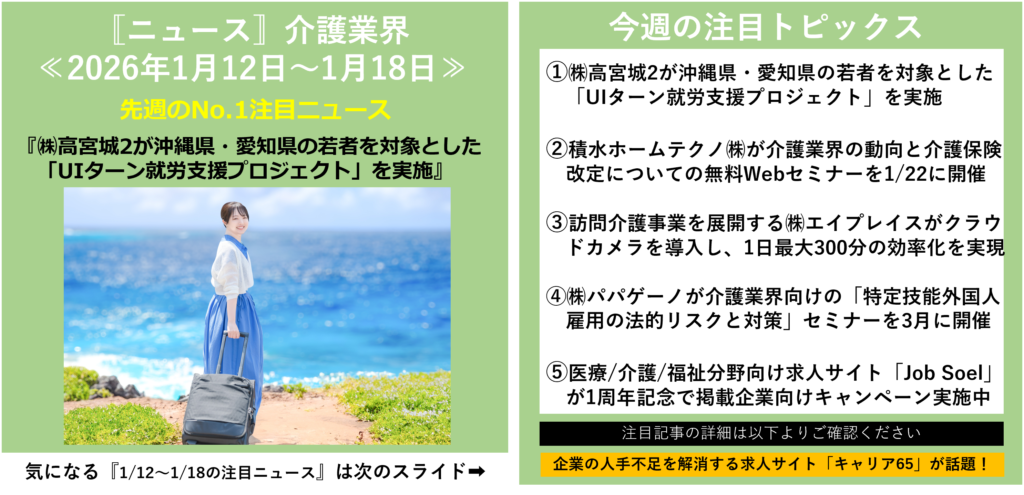
介護業界の人事・採用担当者にとって、「人が集まらない」「定着しない」「育たない」は、もはや日常的な経営課題です。
人材不足が深刻化する中、採用のやり方そのものを変えなければならない時代 に入りました。
求人を出すだけでは応募は来ず、給与を上げるだけでも解決しません。
「誰を、どう育て、どう活躍してもらうか」まで設計することが、これからの介護人事には求められています。
本記事では、
今週注目された 介護業界の人事・採用に直結する5つのニュース をもとに、
人事担当者が「明日から実践できるヒント」をわかりやすく解説します。
若年層採用、制度改正、ICT活用、外国人採用、採用媒体活用――
最新トレンドを押さえ、採用成功につなげるための実践ポイントを整理しました。
① 沖縄・愛知の若者就労支援プロジェクト「Sun-Land-Sunプロジェクト」参加者募集
■ 記事の要約
沖縄・愛知の若者を対象に、介護業界での就労と資格取得を一体化した「Sun-Land-Sunプロジェクト」2026年度参加者募集が開始されました。本プロジェクトは、愛知県の介護事業所で働きながら介護資格を取得し、就職までを伴走支援する仕組みです。「福祉はかっこいい仕事」というメッセージを軸に、若者の県外流出対策と介護人材不足の解消を同時に実現するモデルとして注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
若年層採用は「求人を出すだけ」では集まりません。価値観づくり・育成・就職までを一体化した仕組みづくりが、これからの介護採用の主流になります。採用ブランディングと育成設計をセットで考える重要性が明確になっています。
■ 自分の事業所で検討できること
・学校、自治体、支援団体と連携したUIターン型採用の構築
・「なぜ介護で働くのか」を伝える採用ストーリー設計
・新人育成プログラムの体系化
② 介護業界2026年の大転換期へ!! 介護報酬臨時改定や処遇改善加算の無料WEBセミナー開催
■ 記事の要約
積水ホームテクノが、介護報酬臨時改定や処遇改善加算の最新動向を解説する無料WEBセミナーを開催します。2026年に向けた制度改正は、人件費・採用・定着施策に大きな影響を与える重要テーマです。経営判断と人事戦略をつなぐ情報提供として注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
制度改正は「経営の話」ではなく「採用力そのもの」に直結します。処遇改善・賃上げ原資の理解は、求人票の訴求力と採用成功率を左右します。
■ 自分の事業所で検討できること
・制度改正を踏まえた給与、処遇設計の見直し
・採用メッセージへの反映(安定性、将来性の訴求)
・経営と人事の情報共有体制づくり
③ 訪問介護の業務効率化とサービス向上にICT活用、セーフィーのウェアラブルカメラ導入
■ 記事の要約
エイプレイスが訪問介護の教育効率化のため、セーフィーのウェアラブルクラウドカメラを導入しました。遠隔指導や振り返り学習により、教育時間削減とサービス品質向上を同時に実現。新人不安の軽減と定着率向上にもつながっています。
■ 人事担当者にとっての学び
ICTは業務効率化だけでなく「採用ブランディング」と「定着施策」になります。安心して成長できる環境が、応募の決め手になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・教育体制の可視化(ICT活用)
・新人フォロー体制の強化
・採用ページでの育成環境アピール
④ 特定技能外国人雇用の法的リスクと対策セミナー開催
■ 記事の要約
特定技能外国人の採用に関する法的リスクと実務対応を学ぶ無料セミナーが開催されます。訪問介護解禁により外国人採用は「検討」から「実践」フェーズへ。正しい知識と体制整備が不可欠です。
■ 人事担当者にとっての学び
外国人採用は「人手不足対策」ではなく「中長期採用戦略」です。法令遵守と定着設計がセットで求められます。
■ 自分の事業所で検討できること
・外国人採用ロードマップ作成
・受け入れ体制(教育、生活支援)の整備
・採用リスクチェックリスト作成
⑤ 医療・介護・福祉求人サイト「ジョブソエル」1周年キャンペーン
■ 記事の要約
医療・介護・福祉専門求人サイト「ジョブソエル」が1周年を迎え、求職者向け・企業向けの採用応援キャンペーンを実施。掲載割引やPR強化施策により、採用活動を後押しします。
■ 人事担当者にとっての学び
採用市場は「露出×タイミング×メッセージ設計」が勝負。キャンペーン活用は、母集団形成の重要な武器になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用媒体の活用戦略見直し
・採用メッセージ、写真、ストーリーの刷新
・KPI(応募数、面接数、採用率)の可視化
今回紹介した5つのニュースは、すべて
「介護採用は“戦略設計”の時代に入った」ことを示しています。
・若者を育てて採用する仕組みづくり
・制度改正を踏まえた処遇設計と採用メッセージ
・ICTで教育と定着を支える仕組み
・外国人採用を中長期戦略として設計する視点
・採用媒体を“戦略的に使いこなす”考え方
どれか一つだけでは、採用は成功しません。
「採用・育成・定着」を一気通貫で設計すること」 が、これからの介護人事の勝ちパターンです。
人事は、単なる採用担当ではなく「事業成長を支える戦略パートナー」 です。
今日のニュースをきっかけに、ぜひ自社の採用戦略を一段アップデートしてみてください。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月5日~1月11日の注目ニュース
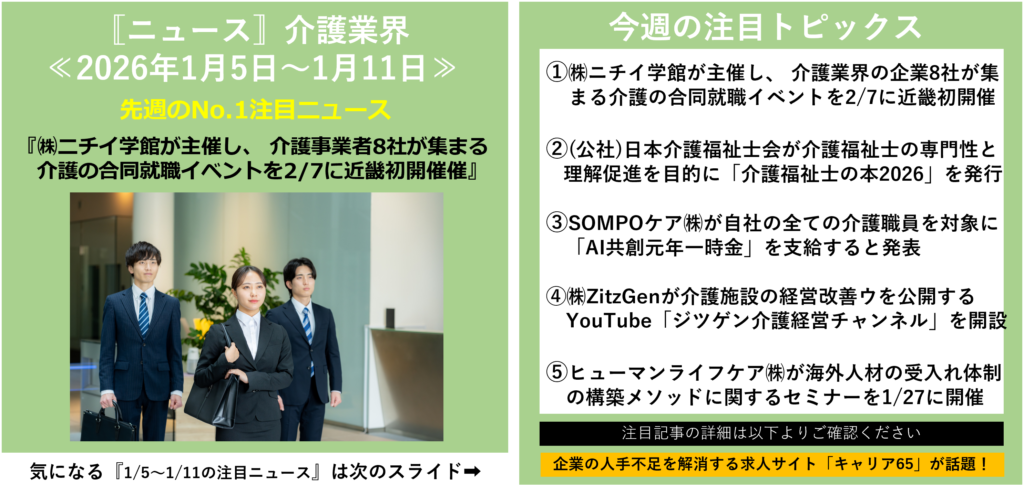
介護業界の人材不足は、もはや「慢性的」ではなく「構造的な経営課題」になっています。
求人広告を出しても応募が集まらない、採用してもすぐ辞めてしまう、外国人材やシニア人材の活用もうまく進まない——こうした悩みを抱える人事担当者は少なくありません。
そんな中、今週の介護業界では「採用のやり方」や「人材をどう活かすか」に直結する重要な動きが複数ありました。
合同就職イベントの開催、介護職の魅力を伝える冊子の発行、AI導入を人事施策と結びつけた一時金の支給、離職率を下げる経営ノウハウの公開、そして海外人材の受入れ体制構築——。
これらのニュースは単なる話題ではなく、「これからの介護人事はどう変わるべきか」への具体的なヒントを含んでいます。
本記事では、今週特に注目度の高かった5つの人事・採用関連ニュースを、人事担当者の視点でわかりやすく解説します。
① 介護職合同就職イベント「介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス」
■ 記事の要約
ニチイ学館は2026年2月7日、大阪・あべのハルカスで介護業界の合同就職イベントを開催します。複数の介護事業者が参加し、来場者は一日で複数法人の採用担当者と直接話すことができます。求人票では分からない「働き方」「職場の雰囲気」「教育体制」などをその場で確認でき、資格相談や復職支援ブースも設けられています。ネット応募では接点を持ちにくいシニア層やブランク人材に直接アプローチする狙いがあり、「会って納得してもらう採用」への転換を示す取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
今の介護採用で最も不足しているのは「情報量」です。給与やシフトだけでは人は動かず、「誰と、どんな環境で働くのか」が決定要因になっています。イベント型採用は、ミスマッチを減らし、定着率を上げる構造を作ります。シニア層やブランク人材に特に有効な手法です。
■自分の事業所で検討できること
施設見学会やミニ説明会など、「直接話せる場」を定期的に設けるだけでも応募の質は変わります。ハローワークや自治体と連携した小規模な説明会や、シニア向け就職イベントへの参加も有効です。求人広告だけに頼らない採用チャネルを一つ持つことが重要です。
② 介護福祉士の専門性と魅力を伝える「介護福祉士の本2026」発行
■ 記事の要約
日本介護福祉士会は「介護福祉士の本2026」を発行しました。今回のテーマは「笑いの力」で、介護現場でのコミュニケーションや人間関係、仕事のやりがいを分かりやすく紹介しています。この冊子は全国の施設や養成校に配布され、介護職の専門性と社会的価値を伝える役割を担います。人材確保が難しい中で、業界として職業イメージを高め、介護の仕事に関心を持つ人を増やす狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
採用難の本質は「仕事の魅力が伝わっていない」ことにあります。業界団体が公式に魅力を言語化してくれることで、人事は“売りやすい商材”を手に入れた状態になります。説明会や面接で積極的に使うべきです。
■ 自分の事業所で検討できること
面接や施設見学の際に配布したり、新人研修で使うことで、介護の仕事の意味や専門性を伝える補助ツールとして活用できます。志向性の合う人材を集めやすくなります。
③ SOMPOケア、全職員に「AI共創元年一時金」を支給
■ 記事の要約
SOMPOケアは、AIやデジタル技術の活用を進めるため、全職員に「AI共創元年一時金」を支給すると発表しました。正社員や社会保険加入パートには1万円、その他のパートには5千円が支給されます。テクノロジー導入を「現場の負担」ではなく「従業員への投資」として位置づけることで、現場の協力を得ながらDXを進める狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
DXはシステム導入ではなく人の行動変容です。評価・報酬と結びつけないDXは形骸化します。SOMPOの事例は、人事が変革のドライバーになれることを示しています。
■ 自分の事業所で検討できること
ICT導入時に、使いこなした職員を評価したり、改善提案を見える化することで、デジタル活用を前向きに進める土壌を作ることができます。
④ 離職率7%・入居率向上を実現する介護経営ノウハウを無料公開
■ 記事の要約
介護施設の離職率低下や入居率向上、加算取得につながる経営ノウハウがYouTubeで無料で公開されました。人材定着と経営改善を同時に実現した事例や実践的な運営手法が紹介されています。採用難の時代において、「人が辞めない職場づくり」が最大の採用施策であることを示す内容となっています。
■ 人事担当者にとっての学び
採用がうまくいかない施設の多くは、実は「辞める原因」を放置しています。人事は採用だけでなく、定着率を経営指標として経営陣に示す役割を担う時代です。
■ 自分の事業所で検討できること
採用を増やす前に、離職率やシフトの安定度などを確認し、「なぜ辞めているのか」を把握することが重要です。定着対策が採用力につながります。
⑤ 介護現場が迷わない、海外人材の受入れ体制づくりセミナー
■ 記事の要約
ヒューマンホールディングスは、介護現場での海外人材受入れ体制をテーマにしたオンラインセミナーを開催します。属人化や丸投げを防ぎ、法人として外国人材を戦力化する仕組みづくりがテーマです。制度の説明にとどまらず、実際の運用や教育体制の整え方を学べる内容となっています。
■ 人事担当者にとっての学び
外国人採用は人事の“プロジェクト管理力”が問われます。制度・教育・現場の連携を設計できるかどうかで、成功か失敗かが決まります。
■ 自分の事業所で検討できること
受入れ担当やOJT担当を決め、組織として育てる体制を整えることで、外国人材を安定した戦力にしやすくなります。
今週の5つのニュースを横断して見ると、介護業界の人事は明確に次のフェーズへ進んでいることが分かります。
それは「人を集める」から「人を選び、活かし、定着させる」への転換です。
合同就職イベントは「会って納得してもらう採用」へのシフトを示し、「介護福祉士の本」は仕事の価値を言語化し、SOMPOケアの一時金はDXを人事制度と結びつけ、経営ノウハウの公開は「辞めない職場」が最大の採用施策であることを示し、海外人材セミナーは「制度任せ」から「組織運用」への転換を促しています。
つまり、これからの介護人事に必要なのは「求人を出す力」ではなく、「人が働き続けたくなる設計力」です。
人材不足の時代だからこそ、
・どうやって出会うか
・どうやって魅力を伝えるか
・どうやって戦力化するか
・どうやって辞めさせないか
この4点を戦略的に考えられる事業所だけが、生き残っていきます。
今回のニュースは、そのためのヒントが詰まった「今週の教科書」と言えるでしょう。
なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月29日~1月4日の注目ニュース
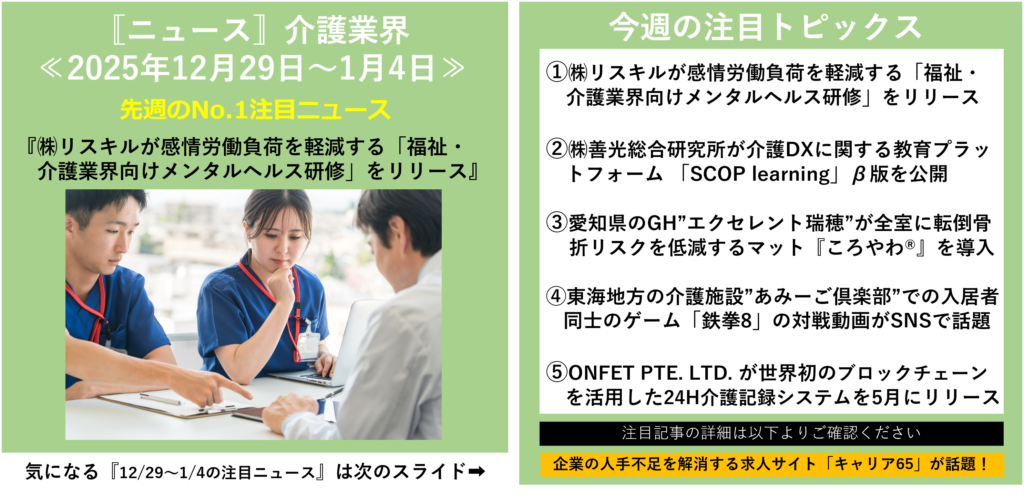
介護業界では人材不足が慢性化する中、採用だけでなく「定着」「育成」「働きやすさ」まで含めた人事施策が強く求められています。
最近は、賃上げや募集条件の見直しだけでは人材確保が難しく、研修・DX・職場環境づくり・職員のやりがい設計といった多面的な取り組みが注目されています。
本記事では、今週話題となった介護業界の人事・採用に関わる最新ニュースを5本ピックアップし、人事担当者の視点で「何を学べるか」「自社でどう活かせるか」を整理しました。
現場の負担軽減や離職防止、採用力強化につながるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
① 介護・福祉職向けメンタルヘルス研修の提供開始
■ 記事の要約
介護・福祉現場で課題となりやすい「感情労働」やストレスに着目し、専門的なメンタルヘルス研修プログラムが提供開始されました。利用者や家族との関係構築、クレーム対応、看取りなど、心理的負担が大きい業務に従事する職員が、自身の感情を整理し、セルフケアや回復力(レジリエンス)を高めることを目的としています。新人職員から管理職まで幅広く対応できる内容で、離職防止や職場の心理的安全性向上が期待されています。
■ 人事担当者にとっての学び
近年の介護離職の要因は「身体的負担」だけでなく、「精神的な消耗」が大きな割合を占めています。賃金改善やシフト調整だけでは解決できない課題に対し、教育・研修という人事施策でアプローチする重要性を示す事例です。特に「辞めさせない採用」を考える上で、採用後のケア設計が不可欠であることが改めて浮き彫りになっています。
■ 自分の事業所で検討できること
・管理職向けに「部下のストレスサインに気づく研修」を導入
・外部研修を活用し、全職員向けに年1回のメンタルケア機会を設ける
・採用時に「メンタルケアに取り組んでいる職場」であることを訴求
研修投資は定着率向上につながり、結果的に採用コスト削減にも寄与します。
② 介護DX人材育成プラットフォーム「SCOP learning」β版公開
■ 記事の要約
介護現場のDX推進を目的としたeラーニング型教育プラットフォーム「SCOP learning」のβ版が公開されました。ICTが苦手な職員でも理解しやすい構成で、記録業務の効率化やデータ活用の基礎を学べる点が特徴です。属人化しがちなDXを、組織全体の共通スキルとして底上げする狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
DXは「システム導入」で終わりがちですが、本質は「人材育成」です。本ニュースは、教育を前提としたDX推進が、人材定着・業務効率・採用力向上に直結することを示しています。特に若手やIT耐性のある人材にとって、「学べる環境がある職場」は応募動機になりやすく、人事施策としても有効です。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT担当を一人に任せず、学習機会を全職員に提供
・DX研修を「評価制度」や「キャリアパス」と連動
・採用広報で「DXに取り組む介護事業所」を明確に打ち出す
教育型DXは、人事と現場をつなぐ重要な投資といえます。
③ 転倒骨折リスク低減フロアを全居室に導入
■ 記事の要約
グループホームにおいて、転倒時の衝撃を和らげる床材・マットを全居室に導入した事例が紹介されました。入居者の安全性向上だけでなく、事故対応に伴う職員の精神的・時間的負担を軽減する狙いがあります。ハード面から事故リスクを下げる先進的な取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
介護事故は、職員の離職理由にもなりやすい要因です。設備投資は「利用者向け施策」と捉えられがちですが、実は職員の安心感や働きやすさにも直結します。安全配慮が行き届いた職場は、採用時の差別化ポイントにもなります。
■ 自分の事業所で検討できること
・事故が起きやすい場所の環境改善から段階的に着手
・安全対策を採用ページや求人票で積極的に発信
・「ヒヤリハット削減」を人事KPIとして設定
ハード投資は、人材定着の“見えにくい基盤”となります。
④ 介護施設で高齢者eスポーツ大会が話題に
■ 記事の要約
介護施設で高齢者が参加するeスポーツ大会が開催され、大きな反響を呼びました。単なる娯楽ではなく、交流促進や自己肯定感向上、生活意欲の活性化につながる新しいレクリエーションとして注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
職員の仕事満足度は「利用者の笑顔」や「現場の雰囲気」に大きく左右されます。こうした先進的な取り組みは、現場にポジティブな空気を生み、職員のやりがいや誇りにもつながります。結果として定着率や採用ブランディングにも好影響を与えます。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICTを活用した新しいレクリエーションの検討
・イベントを広報/採用コンテンツとして活用
・「挑戦を応援する職場文化」を人事方針に明記
現場の楽しさは、人材獲得競争における重要資産です。
⑤ AI×ブロックチェーン介護記録システムを2026年提供予定
■ 記事の要約
AI翻訳とブロックチェーン技術を組み合わせた次世代介護記録システムが発表されました。多言語対応により外国人介護人材の記録負担を軽減し、同時に記録の改ざん防止や透明性を確保する仕組みです。人材多様化が進む介護業界において注目度の高いニュースです。
■ 人事担当者にとっての学び
外国人材の採用が進まない理由の一つが「記録業務の壁」です。テクノロジー活用によって制度・言語の壁を下げることで、採用の選択肢を広げられる可能性があります。人事とICTが密接に関わる時代に入っていることを示しています。
■ 自分の事業所で検討できること
・外国人材採用を見据えた業務プロセスの見直し
・記録業務の簡素化/標準化の検討
・「多様な人材が活躍できる職場」を採用方針に明記
将来を見据えた準備が、人材確保力の差になります。
今週のニュースを振り返ると、介護業界の人事課題は「人を集める」フェーズから、「人が長く安心して働ける環境をどうつくるか」へと確実にシフトしていることが分かります。
メンタルヘルス研修、DX人材育成、安全対策、レクリエーションの工夫、外国人材を支えるICT――いずれも、採用・定着・職員満足度を同時に高める視点が共通しています。
重要なのは、これらを単発施策で終わらせず、
・採用メッセージ
・教育/評価制度
・職場環境づくり
と連動させて設計することです。
小さな取り組みでも、「人を大切にする姿勢」が伝わる事業所は、結果として選ばれる職場になります。
人材確保に悩む今だからこそ、最新事例からヒントを得て、自社らしい人事・採用の形を一歩ずつ形にしていきましょう。
ら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月22日~12月28日の注目ニュース
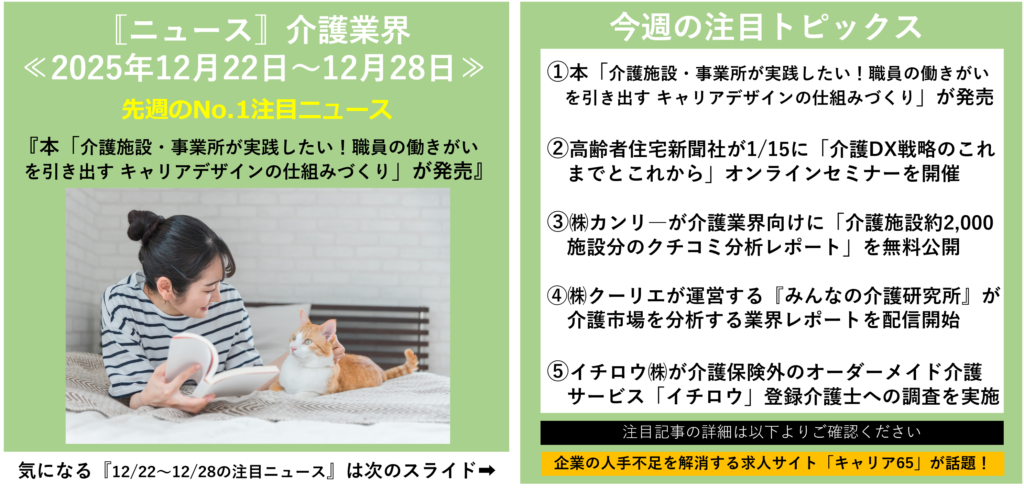
慢性的な人材不足が続く介護業界において、「どう採用するか」だけでなく「どう働き続けてもらうか」「どう選ばれる職場になるか」 が、これまで以上に重要になっています。
今週は、
・職員の働きがいとキャリアデザイン
・クチコミ評価と現場負担の関係
・統計データから見える介護市場の転換点
・介護離職や在宅介護の限界と新たな支援の形
など、人事 / 採用の本質に直結するニュース が多く発信されました。
本記事では、介護事業所の人事・採用担当者が「明日から何を見直すべきか」「どんな視点を持つべきか」を考えるヒントとして、今週注目すべき5つのニュースを分かりやすく解説します。
① 『介護施設・事業所が実践したい!職員の働きがいを引き出す キャリアデザインの仕組みづくり』発刊
■ 記事の要約
第一法規株式会社は2025年12月24日、介護施設・事業所向けに、職員の働きがいとキャリア形成をテーマにした専門書を発刊しました。
本書では「辞めない職場づくり」ではなく、職員が主体的に『ここで働きたい』と思える職場をどう設計するかに焦点を当てています。スキルアップ、ワークライフバランス、多様な働き方を“制度・仕組み”として整理している点が特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
採用難の時代において、待遇改善だけでは人は定着しません。
キャリアの見通しを描けるかどうかが、特に中堅・シニア層の離職を左右します。人事が「成長の道筋」を示せているかが、採用力そのものになります。
■ 自分の事業所で検討できること
・キャリア面談が評価中心になっていないか
・年齢 / 役割別のキャリアモデルを可視化できているか
・フルタイム以外の働き方を制度化できているか
② 介護・高齢者住宅分野の最新動向を学ぶ事業者向けセミナー開催
■ 記事の要約
高齢者住宅・介護事業に関わる事業者向けに、業界動向や人材課題をテーマとしたセミナーが開催されます。
人材不足を前提とした経営・運営視点や、現場任せにしない人材戦略の重要性が解説される内容です。
■ 人事担当者にとっての学び
現場対応だけでは人材課題は解決しません。
業界全体の構造変化を理解した上で人事戦略を立てる視点が求められています。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用計画を単年度で考えていないか
・人事が経営課題と切り離されていないか
③ 【介護業界向け無料レポート】家族との連携不足が低評価の引き金に?
■ 記事の要約
株式会社カンリーは、約2,000施設のクチコミを分析した無料レポートを公開しました。
評価が低くなる要因として「家族とのコミュニケーション不足」が大きく影響していることが明らかになっています。
■ 人事担当者にとっての学び
クチコミ評価は利用者だけでなく求職者にも見られています。
現場職員に家族対応の負担が集中すると、ストレス増大→対応品質低下→評価悪化という悪循環が生まれます。
■ 自分の事業所で検討できること
・家族対応が属人化していないか
・職員が安心して説明できる仕組みがあるか
④ 【統計データで見る】2026年を見据えた介護市場を読み解く
■ 記事の要約
株式会社クーリエが運営する「みんなの介護研究所」は、介護事業者の倒産増加などを背景に、介護市場の構造変化をデータで分析しています。
■ 人事担当者にとっての学び
人材戦略の失敗=経営リスクという時代に入っています。
人件費削減だけの経営は限界であり、生産性・定着を含めた人事設計が不可欠です。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用できない場合の事業継続リスクを想定しているか
・中長期の人材計画を描けているか
⑤ 【総勢1,100人調査】介護を必要とする側と提供する側の実態
■ 記事の要約
イチロウ株式会社は、介護を「する側・される側」双方を対象にした1,100人調査を実施。
介護離職への不安や、介護保険だけでは対応しきれない現実が浮き彫りになりました。
■ 人事担当者にとっての学び
介護職員自身も介護離職リスクを抱える当事者です。
仕事と家庭介護の両立支援は、定着施策そのものです。
■ 自分の事業所で検討できること
・介護離職を防ぐ相談体制はあるか
・保険外サービスなど外部資源を案内できているか
今週の介護業界ニュースを振り返ると、共通して見えてくるのは採用や定着の課題は、もはや人事部門だけの問題ではない という現実です。
・働きがいを仕組みとして設計できているか
・職員の負担が評価 / クチコミにどう影響しているか
・人材戦略を持たない経営が、どれほどのリスクを抱えているか
・職員自身の介護 / 生活課題に向き合えているか
こうした視点を持つことが、
「人が集まらない職場」と「選ばれ続ける職場」の分かれ目になります。
人手不足の時代だからこそ、
採用を“短期の補充”ではなく、“中長期の人材設計”として捉えること が不可欠です。
今回のニュースを、自事業所の人事・採用の見直しにつなげるきっかけとして、ぜひ活用してみてください。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月15日~12月21日の注目ニュース
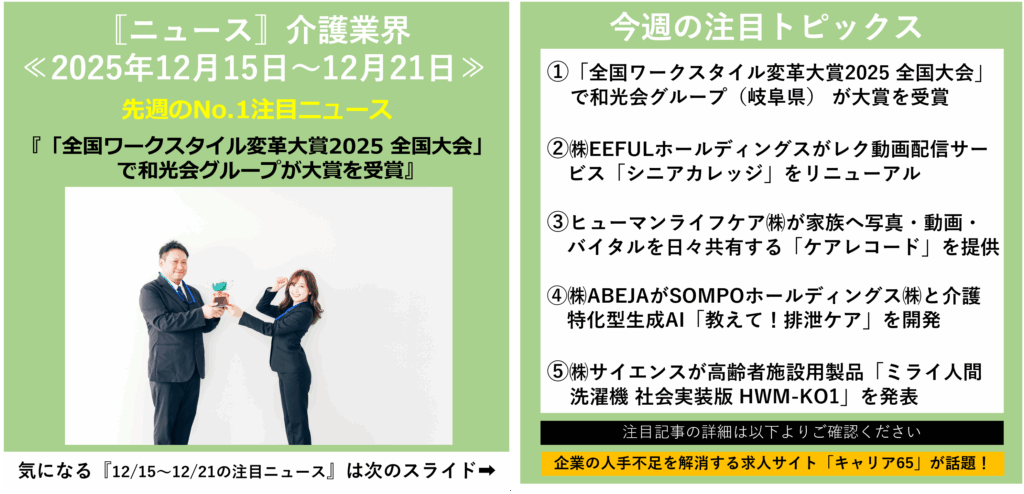
介護業界では、人手不足の深刻化を背景に、採用・定着・働き方改革をどう進めるか が人事担当者にとって重要なテーマとなっています。
DXの活用、AI導入、業務負担を軽減する機器の実装など、現場を支える新たな取り組みも次々と登場しています。
本記事では、今週特に注目度の高かった介護業界の人事・採用関連ニュースを5本厳選し、
それぞれについて
・何が起きているのか
・人事担当者としてどこに注目すべきか
・自社の事業所でどう活かせるか
という視点でわかりやすく解説します。
日々の人事施策や採用戦略を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。
① 介護現場の働き方改革が進む:「全国ワークスタイル変革大賞2025」受賞事例が示す人事戦略
■ 記事の要約
「全国ワークスタイル変革大賞2025」は、介護・福祉現場を含む全国の勤務環境改善事例を表彰する取り組みです。
今年は岐阜の和光会グループが大賞を受賞し、紙ベースの手続きやマニュアルをデジタル化することで、年間8.4万時間もの業務削減に成功した事例が紹介されました。
その他の受賞施設でもITツール活用や仕組み改善で現場負担を軽減し、業務効率化や職員の定着率改善につながっています。
■ 人事担当者にとっての学び
今回の受賞事例は、単なる業務効率化ではなく職員の働きやすさ向上と採用力強化を共に実現している点がポイントです。
介護業界は慢性的な人手不足と長時間労働が課題ですが、ITツールや業務プロセスの見直しは、職員満足度・定着率の向上に直結します。
特に人事部としては、現場の声を経営戦略に反映させることが重要になるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
・現場の負担が大きい手続きや業務プロセスのデジタル化
・職員からのフィードバックを集めて改善の優先順位を決定
・業務効率化の効果を採用ブランディングに活かす
② レクリエーション動画サービス「シニアカレッジ」リニューアルが示す介護現場改善
■ 記事の要約
介護施設向けのレクリエーション動画配信サービス「シニアカレッジ」がリニューアルされ、検索性や操作性が大幅に向上しました。
映像コンテンツのプレイリスト機能、連続再生対応などで、介護スタッフの準備時間を大幅に削減できます。高齢者とのコミュニケーション促進やレクリエーション準備の負担軽減が期待されているツールです。
■ 人事担当者にとっての学び
レクリエーションは介護現場で重要な業務ですが、準備や企画には時間と労力がかかります。
人事部としては、こうした業務時間の削減が職員の負担軽減と離職予防につながることを理解し、教育・研修やツール導入の投資効果を評価する視点が必要です。
■ 自分の事業所で検討できること
・レクリエーション準備時間の削減に向け動画・デジタル教材の活用
・スタッフ意見を反映したツール導入検討
・現場負担を減らす仕組みを採用評価制度に組み込む
③ 介護DXサービス「ケアレコード」で現場・家族・人事がつなが
■ 記事の要約
ヒューマンホールディングスが提供する介護DXサービス「ケアレコード」は、利用者の写真や健康データ、介護記録を家族と共有できるプラットフォームです。
これにより情報共有がスムーズになるとともに、ケアの透明性と信頼性が高まり、利用者・家族双方の安心感が向上します。
また、担当ケアマネージャーとの連携も強化されるため、ケア品質の向上に寄与します。
■ 人事担当者にとっての学び
情報共有の「見える化」は介護の質向上だけでなく、現場スタッフの働きがい向上にもつながります。
人事施策としてケア品質向上を人材戦略につなげる観点は、採用競争力アップの要素になるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
・利用者/家族との信頼構築を戦略化
・DXツール導入を人事評価や採用ブランディングに活かす
・現場スタッフの負担軽減と自己成長につながる研修制度設計
④ 生成AIによる介護支援の可能性:排泄ケアAIを導入する意義
■ 記事の要約
ABEJAとSOMPOグループが共同で、介護現場の負担が大きい排泄ケア支援のための生成AIツール開発を進めています。
このAIはベテラン職員のノウハウを学習し、ケア記録や業務支援を通して新人スタッフの支援や情報共有を可能にします。
試験版の導入に向けて事業者の募集も進んでいます。
■ 人事担当者にとっての学び
AIによる支援は、介護業務の負担を軽減するだけでなく、新人育成・教育の効率化という人事視点でも大きな意味を持ちます。
職員がより専門的なケアに集中できる環境は、離職防止や働きがい向上にも寄与します。
■ 自分の事業所で検討できること
・AI導入による教育/研修支援の強化
・AI活用による現場負担軽減を人事制度に反映
・導入効果を採用広報で訴求する
⑤ 介護現場への最新機器導入:「人間洗濯機」が示す負担軽減の必要性
■ 記事の要約
介護現場の身体的負担を軽減する介助機器として、「人間洗濯機」と呼ばれる全自動洗浄機が注目されています。
体を清潔に保つという介護ケアの中でも、身体的負担は大きなストレスになりがちですが、このような機器の導入は負担軽減と安全性向上に寄与します。
各現場で試験導入や検証が進んでいます。
■ 人事担当者にとっての学び
人間洗濯機のような介助機器の導入は、身体的な負担軽減による離職抑制や職員満足度の向上を実現します。
人事戦略としては、働きやすさ・安全性を高める施策を人材採用メッセージに組み込むことで応募者の共感を得られます。
■ 自分の事業所で検討できること
・最新機器導入による現場負担軽減の効果を試算
・身体的負担軽減を訴求した採用広報
・職員の声を反映した設備投資の優先度決定
今回紹介した5つのニュースに共通しているのは、
「現場の負担を減らし、働きやすさを高めることが、採用と定着につながる」 という明確なメッセージです。
・DXによる業務効率化
・レクリエーションやケア記録のデジタル活用
・AIや介護機器による身体的/精神的負担の軽減
これらは単なる業務改善にとどまらず、
「選ばれる職場づくり」や「長く働き続けられる環境づくり」 に直結します。
人事担当者としては、制度やツールを導入すること自体が目的ではなく、
それを 採用メッセージ・定着施策・人材育成 にどう結びつけるかが重要です。
ぜひ今回のニュースを、自社の人事戦略を見直すきっかけとして活用してみてください。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月8日~12月14日の注目ニュース
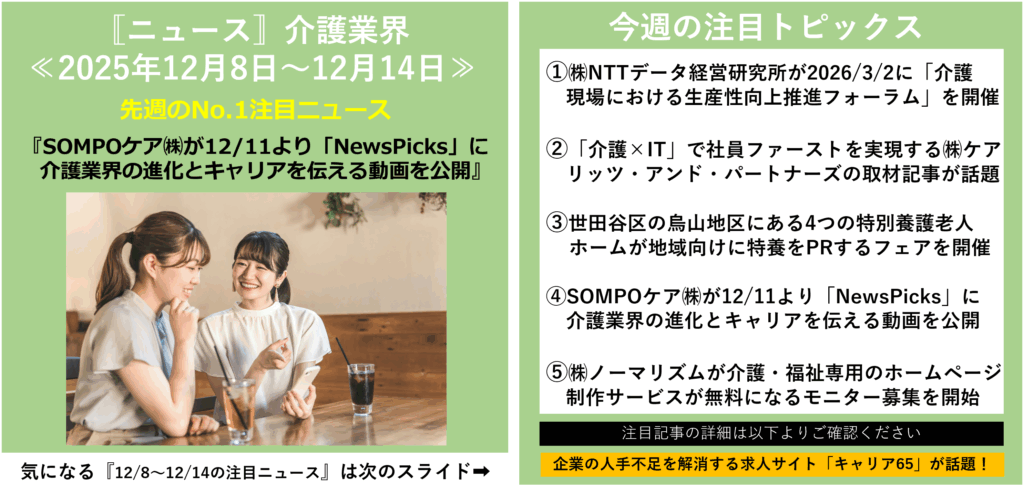
人手不足が慢性化する介護業界において、人事・採用担当者に求められる役割は年々高度化しています。
「求人を出しても応募が来ない」「採用しても定着しない」といった課題は、もはや一部の事業所だけの問題ではありません。
こうした中で重要なのが、他社はどのように人材課題と向き合い、どんな工夫をしているのかを知ることです。
制度・テクノロジー・情報発信・地域連携など、介護業界の人事施策は確実に進化しています。
本記事では、今週注目された介護業界の人事・採用関連ニュースを5本厳選し、
「人事担当者にとっての学び」と「自事業所で検討できるポイント」の視点から分かりやすく解説します。
日々の採用活動を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。
① 介護現場における生産性向上推進フォーラム2025
■ 記事の要約
本フォーラムは、厚生労働省の施策と連動しながら、介護現場の生産性向上をテーマに開催されるイベントです。業務負担の軽減、ICT・介護テクノロジーの活用、先進事業所の具体的な改善事例などが共有される予定で、現場の「人が足りない」「忙しすぎる」という課題に真正面から向き合う内容となっています。生産性向上は単なる効率化ではなく、「職員が長く働ける環境づくり」である点が強調されているのが特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
採用が難しい時代において、「人を増やす」前に「今いる人が辞めない環境をどうつくるか」が重要であることを再認識させられます。生産性向上は人事・採用施策と切り離された話ではなく、結果的に離職率低下や採用ブランディングにも直結します。人事担当者が業務改善の議論に関与する必要性を示す好例です。
■ 自分の事業所で検討できること
・業務の棚卸し(ムダ/属人化の洗い出し)
・ICTや記録業務の簡素化の検討
・「忙しいから採れない」ではなく「忙しくならない設計」への発想転換
② 「介護×IT」で若手が活躍する組織づくり(Diamond Online)
■ 記事の要約
介護事業者がITを積極的に活用し、業務効率化と働きやすさを両立させている事例を紹介した記事です。夜勤に依存しない体制づくりや、管理業務のデジタル化により、若手職員が長く働ける環境を実現しています。結果として、介護業界で課題とされがちな「若手が定着しない」という問題に対して、明確な解決策を示しています。
■ 人事担当者にとっての学び
「若い人が来ない」のではなく、「若い人が続かない構造」こそが課題であることが浮き彫りになります。採用強化よりも前に、働き方や評価制度、業務負荷の見直しを行うことが、結果的に採用力を高めることにつながります
■ 自分の事業所で検討できること
・IT化=コストではなく定着投資として捉える
・夜勤やシフト設計の再検討
・若手が「将来像」を描けるキャリア設計の明確化
③ 地域合同開催の特養フェアが示す採用の新しい入口
■ 記事の要約
東京都世田谷区で、複数の特別養護老人ホームが合同で開催した「特養フェア」の様子を伝える記事です。地域住民向けに施設紹介や相談対応を行い、介護の仕事や施設の役割を身近に感じてもらうことを目的としています。採用説明会というより「地域交流イベント」に近い形で実施されている点が特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
採用活動は求人媒体だけで完結しない、という示唆があります。地域に開かれた活動を通じて、潜在的な応募者や支援者と接点を持つことが、結果的に採用につながるケースも少なくありません。「知ってもらうこと」自体が人事施策になる好例です。
■ 自分の事業所で検討できること
・近隣事業所との合同イベントの検討
・地域住民向け見学会/相談会の実施
・採用目的だけに偏らない情報発信
④ 動画で伝える介護のリアルと未来(SOMPOケア)
■ 記事の要約
SOMPOケアが、介護の仕事のリアルな姿や未来像を伝える動画コンテンツを公開したというニュースです。ニュースメディアやドラマ形式を活用し、従来の求人情報では伝えきれなかった「働く意味」「やりがい」を発信しています。特に、介護未経験層へのアプローチを意識した内容となっています。
■ 人事担当者にとっての学び
求人票だけでは伝わらない情報こそ、応募の意思決定に大きく影響することが分かります。動画やストーリーは、職場の雰囲気や価値観を直感的に伝える強力な手段です。
■ 自分の事業所で検討できること
・短い動画や写真で職場の様子を発信
・「大変さ」も含めたリアルな情報開示
・理念や想いを言葉以外で伝える工夫
⑤ 採用力を左右する「介護事業所のホームページ」
■ 記事の要約
介護・福祉事業者向けに特化したホームページ制作サービスのモニター募集に関するニュースです。施設情報だけでなく、採用ページの設計や情報発信を重視した内容が特徴で、求職者目線でのサイト構築を支援します。
■ 人事担当者にとっての学び
応募者は必ずと言っていいほど事業所のホームページを確認します。ホームページは「24時間働く採用担当者」であり、情報が古い・少ないだけで応募機会を失う可能性があります。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用ページの内容見直し
・「どんな人が働いているか」を見せる工夫
・応募前の不安を解消するQ&A設置
今回取り上げた5つのニュースから見えてくるのは、介護業界の人事・採用は「募集を増やす段階」から「働き続けられる環境を設計する段階」へ移行しているという点です。
生産性向上やIT活用は、単なる業務効率化ではなく、職員の負担軽減と定着率向上につながります。
また、地域イベントや動画発信、ホームページの改善など、「知ってもらう」「伝える」工夫も、採用力を左右する重要な要素です。
人材確保が難しい今だからこそ、
・人事が現場改善に関与する
・採用を“広報/ブランディング”として捉える
・自事業所の魅力を言語化/可視化する
こうした視点が、これからの介護事業所には求められます。
まずは小さな取り組みからでも構いません。
今回のニュースをきっかけに、自事業所の人事・採用のあり方を見直す一歩につなげていきましょう。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月1日~12月7日の注目ニュース
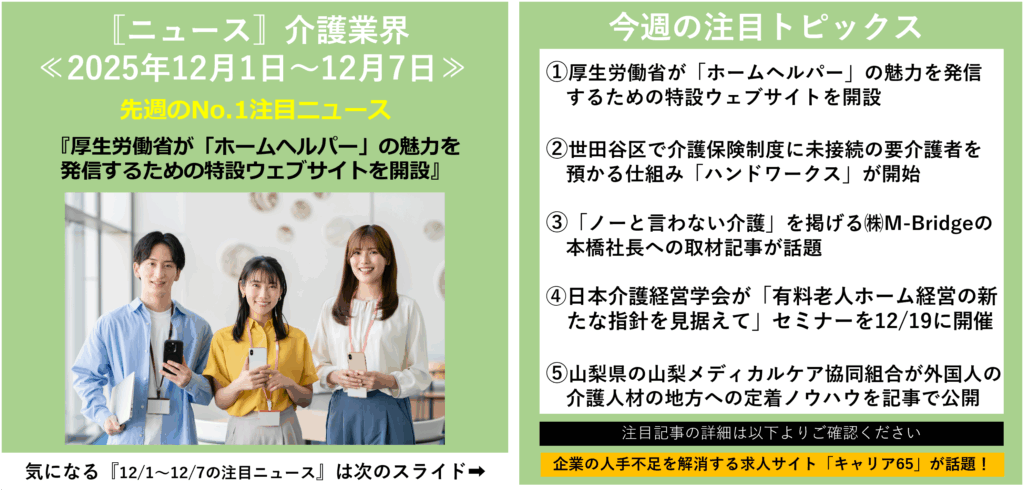
近年、介護業界では採用競争の激化と離職率の上昇が続き、「採用できない」「定着しない」という声が全国で聞かれます。
加えて、若手の採用難、地方から都市部への人材流出、外国人材の争奪、ケアラーなど隠れた潜在層の増加——構造的に人材確保が難しくなる中で、企業は「従来型採用の延長線」では戦えなくなってきています。
そんな中、今週の介護業界では、国・自治体・企業がそれぞれ異なる方向性で「採用」「定着」「働き方」を再定義する動きが目立ちました。
キーワードは、「多様性の許容」「理念の可視化」「未来を描ける職場づくり」。
本記事では、介護業界の採用・定着に関わる最新ニュースを5つ厳選し、
人事担当者にとっての学び
自事業所での検討ポイント
を整理したうえで解説します。
「人が集まり、辞めず、育つ職場づくり」は、一朝一夕では実現できません。政策、採用設計、広報戦略、現場の仕組みまで複数の視点が求められる時代です。
あなたの事業所の採用戦略をアップデートするヒントとして、ぜひ参考にしてください。
① ホームヘルパーの魅力を発信する特設サイトを厚労省が開設
■ 記事の要約
厚生労働省は「訪問介護(ホームヘルパー)」への応募減少と定着課題に対応すべく、幅広い層に向けて魅力を発信する特設サイトを開設。漫画・動画・現場の声などを使い、未経験者、学生、子育て中の主婦、ミドルスイッチ層まで横断的に訴求するためのコンテンツを整備。社会理解の遅れ・仕事イメージの偏りを是正する狙いがある。背景には、「訪問介護の担い手不足」が特に深刻化し、都市部でも地方でも採用困難が続いており、事業者個社では改善しきれなかった“業界課題”に国が政策的に動いた形。
■ 人事担当者にとっての学び
・採用成功は、求人票よりも前の“職業理解”が鍵になる
・“やりがい” と “具体的な業務イメージ” をセットで届ける時代
・採用広報と採用は別物 —「募集」だけでは人は動かない
特に、ホームページ、SNS、動画、現場スタッフの声など、「自社の仕事がどんな価値を生むのか」を可視化しなければ応募の母数は増えない。
■ 自分の事業所で検討できること
・公式サイトに“仕事紹介ページ”を作成(職種別/一日の流れ)
・「ヘルパーのやりがい」を言語化し、写真付きで紹介
・採用ページに“理念”や“ケアの考え方”を掲載
・SNSで「やさしさの瞬間」「利用者の笑顔」など日常を発信
採用は「マッチング」より「認知→共感→応募」の時代へ移行しつつある。
② 介護人材不足とケアラー支援を両立する業界初プロジェクト「バンドワークス」開始
■ 記事の要約
家族の介護・子育てなどで「フルタイムが難しい層」=“ケアラー”が、スキマ時間で働ける介護現場を構築するプロジェクト。従来の固定シフト型では排除されてきた層を、AIシミュレーションによる業務分割と複数人連動型勤務(バンドワーク)で補完。「育てたのに辞められる」ではなく、「働けるときに働いてもらう」という発想の転換となり、労働市場の回復と就労支援を同時に実現。
■ 人事担当者にとっての学び
・“フルタイム以外を排除しない採用”が競争優位になる
・1人のフルタイムより “3人の2時間” が戦力になる時代
・ケアラー、主婦、副業人材、シニア=“潜在労働力” の宝庫
採用は「求職者を選ぶ」構造から「求職者が選べる仕様にする」構造へ。
■ 自分の事業所で検討できること
・“週1/1時間/午前だけ” を許容する求人設計
・「分業できる業務」を分解 → 採用枠として再設計
・シニア/主婦/ダブルワーカー向けの短時間採用枠
・「固定シフト」ではなく「希望提出制+AI/表管理」
採用は“入れ替える”のではなく“取りこぼさない”方向へ進む。
③ 「ノーと言わない介護」— 入居者の自由を守る新しい介護施設のあり方(M-Bridge 本橋建哉社長)
■ 記事の要約
M-Bridgeが掲げる「ノーと言わない介護」は、従来の“ルール優先の介護”から脱し、入居者の自己決定を尊重するケア哲学。施設の運営は、空き家活用、動物福祉(犬猫の殺処分ゼロ)、就労支援など複層的に社会課題と接続。「制約をかけて安全を守る介護」から、「自由を尊重して支援する介護」へ転換するモデルを提示。
■ 人事担当者にとっての学び
・採用広報で“理念”=最強の差別化資源になる
・給与だけでは人材は惹きつけられない
・“共感採用”が応募の質と定着率を左右する
求職者は「何をするか」だけではなく、「なぜその仕事をするのか」に反応する。
■ 自分の事業所で検討できること
・介護方針/ケア哲学の明文化
・求人票に「この仕事の価値と社会的意義」を明記
・動物/地域/空き家活用など、社会接続のテーマを検討
・面接で「あなたのケア観」をテーマに語り合う
“採用競争”ではなく“理念共感”が採用成功の軸になる。
④ 有料老人ホーム経営の新指針を議論 — 日本介護経営学会「第9回セミナー開催」
■ 記事の要約
日本介護経営学会が、有料老人ホーム事業の品質向上と経営安定をテーマに討議。背景には、価格競争 → サービス差別化 → 継続率向上という「介護版 ストックビジネス化」が進み、“稼働率が経営の生命線” になっている現状。国の政策は「自立支援」「地域包括」「生活リハビリ」へシフト。事業者は経営・人材・品質の三位一体の体制整備が求められる。
■ 人事担当者にとっての学び
・採用は単発イベントではなく“事業の運営資源”
・人材×サービス品質=継続率=収益
・“即戦力採用”の限界 → “育成できる組織” が勝つ
経営は「採用の結果」で決まる時代へ。
■ 自分の事業所で検討できること
・“定着前提”の育成プログラム設計
・評価/昇格基準の提示と透明化
・キャリアステップ(相談員/主任/生活支援)
・利用者家族の満足度を採用広報で活用
採用と育成は分離せず、連携させることが経営の鍵。
⑤ どうすれば外国人が定着する?介護人材「奪い合い時代」の地方モデル(山梨)
■ 記事の要約
地方から都市部へ優秀な外国人が流出する現象の中、山梨メディカルケア協同組合では“事前の相互理解と合意形成”“生活サポート”“キャリア支援”により、定着率70%以上を維持。「寮の質」「地域を理解」「キャリア支援」「役割付与」「日本人より評価される体験」が定着を生む。給与競争ではなく “尊重と期待” が離職防止に寄与している。
■ 人事担当者にとっての学び
・「外国人だから」ではなく「未来の働き手として扱う」
・生活支援は福利厚生ではなく“採用投資”
・キャリア支援と役職付与が長期雇用を生む
採用は「採る」ではなく「迎える支援」に変わっている。
■ 自分の事業所で検討できること
・ミスマッチ防止の事前説明資料作成
・住宅、交通、生活支援を制度設計
・実務者/介護福祉士取得の学習支援
・面談で将来像を共有し、「配役」を与える
人材は奪われるものではなく、育つ環境に残る。
今週のニュースを振り返ると、介護業界の採用と人材戦略は、もはや「労働力の確保」の枠を超え、「誰が、どんな価値観で、どんな人生を描きながら働くのか」を前提とした組織づくりへ変化しています。
・理念に共感して入職する人は、定着する。
・未来像が描ける人は、成長する。
・待遇だけでなく「理解」「期待」「尊重」が採用を支える。
採用とは、単に人を増やす活動ではなく、組織の文化をつくる行為であり、地域に根ざす存在となるための取り組みです。
これからの介護事業者に求められるのは、「応募者を選ぶ立場」ではなく、「選ばれる事業所であり続けること」。
働きたい人が、その人生と向き合いながら、安心してキャリアを築ける環境を用意できる事業者が、この先の介護業界で強い競争力を持つことになります。
採用と定着は、コストではなく「投資」です。
未来の介護現場を支える人材と共に、持続可能な組織をつくっていくために、今回のニュースを一つのヒントとしてご活用ください。
ら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年11月24日~11月30日の注目ニュース
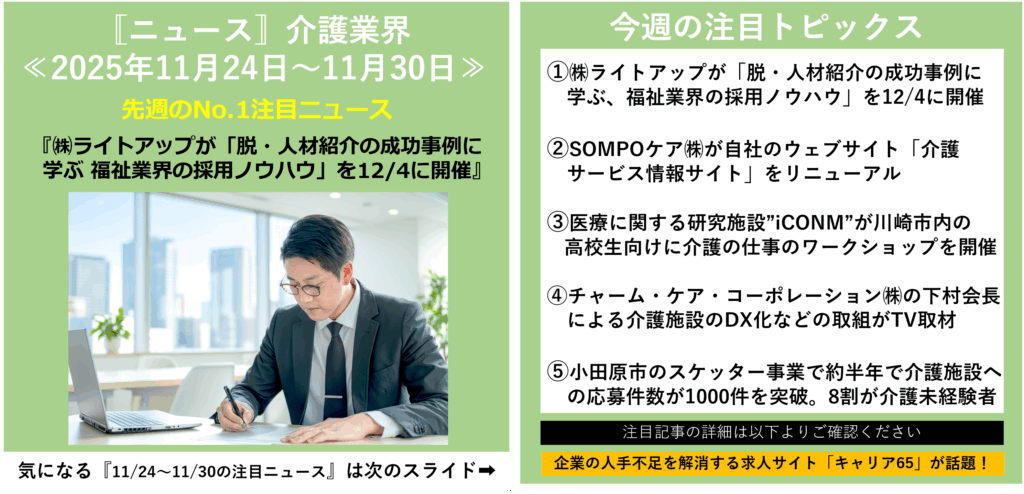
介護業界では、採用難・人材不足が年々深刻化する一方で、現場の働き方改革やDX推進、地域連携、若年層へのアプローチなど、採用・人事を取り巻く動きは加速度的に変化しています。特に2025年以降は、採用単価の上昇、未経験者の掘り起こし、採用広報の重要度増加など、事業者が押さえるべきトレンドがますます増えています。
本記事では、今週の介護業界の人事・採用に関わる注目ニュース5本 をピックアップし、人事担当者が明日からの採用戦略に活かせる「学び」と「実践ポイント」をわかりやすくまとめました。
・採用を内製化する最新ノウハウ
・サービス紹介と採用広報の一体化
・高校生との連携による人材育成の新潮流
・DXによる働き方改革のリアル
・地域から未経験者を呼び込む新モデル
採用に悩む事業者ほど、ヒントは“現場の外”にあります。
最新ニュースから、今すぐ取り入れられるポイントを一緒に見ていきましょう。
① ライトアップ、「脱・人材紹介」採用ノウハウセミナーを開催
■ 記事の要約
株式会社ライトアップが、福祉・医療業界向けに「脱・人材紹介」をテーマとしたオンラインセミナーを開催する。採用広告や紹介会社に頼っても成果が出にくい事例をもとに、よくある失敗パターンや、再現性のある採用体制づくりを解説。「レンタル人事」モデルを提供するキャンディータフト社の代表が登壇し、体制構築の方法や導入までの流れを約30分で伝える。参加者には個別相談特典もあり、自社課題に応じたアドバイスが受けられる。
■ 人事担当者にとっての学び
採用難が進む中、人材紹介に依存した“外注型採用”では安定的な母集団形成が難しくなっている。この記事は、「採用は仕組みで決まる」 という考え方を示している。求人票の質や応募後対応のスピードなど、基本的な運用改善だけでも成果が変わることを踏まえると、今後は“採用の内製化”が重要になる。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用の失敗パターンを整理し、求人票/面接フローを見直す
・人材紹介への依存割合を確認し、費用と成果のバランスを可視化
・SNS発信や採用広報を月1本からでも開始
・応募者対応(返信/面接日程)を標準化し、スピード改善
・こうしたセミナーで外部知見を取り入れ、採用体制を小さく改善
② SOMPOケア、介護サービス情報サイトを全面リニューアル
■ 記事の要約
SOMPOケアが、自社の介護サービス情報サイトを全面リニューアルした。目的は、初めて介護サービスを利用する家族・本人が迷わず必要な情報に辿り着けるようにすること。今回の改修では、介護保険の仕組みをわかりやすく図解化し、サービス比較・選び方、利用者の声、写真・動画など“リアルな情報”を強化。また専門用語を排除し、誰でも読めるようコンテンツ構造を見直した。スマホ閲覧を前提としたUI改善も行い、閲覧数の向上を目指している。
■ 人事担当者にとっての学び
介護業界では「わかりやすさ=信頼性」という構造があり、利用者だけでなく求職者もホームページの“情報のていねいさ”を重視する。特に、若年層や中高年の求職者は応募前に必ず事業所のホームページや口コミを確認するため、サービス紹介の内容は採用広報と表裏一体。今回のSOMPOケアのリニューアルは、サービス理解のしやすさを高めることが「採用力向上」につながることを象徴している。また、介護の仕事内容を専門用語なしで説明できる事業所のほうが応募者の離脱が少ない。
■ 自分の事業所で検討できること
・採用ページとサービス紹介ページの言葉/写真の刷新
・スタッフの「1日の流れ」紹介記事や動画を追加
・利用者/家族の声、写真、ショート動画の拡充
・難しい専門用語の排除
・スマホで読みやすいレイアウトの最適化
・介護保険の基礎知識ページを追加
③ iCONM、高校生向けワークショップで福祉人材育成を推進
■ 記事の要約
川崎市のナノ医療イノベーションセンター「iCONM」が、高校生向けに福祉人材育成ワークショップを開催。市立川崎高校(福祉科)と川崎総合科学高校(科学科)の66名が参加。福祉科の生徒は介護実習で見た課題を共有し、科学科の生徒はアプリ開発などテクノロジーを活用した解決策を提案。双方の専門性を掛け合わせ、現場課題を協働的に解決する学びの場となった。少子高齢化による介護人材不足を見据えた“若年層へのアプローチ”として注目される。
■ 人事担当者にとっての学び
介護業界の人材難は深刻化しており、若年層へのアプローチが大きな課題。今回のように「介護 × 工学 × テクノロジー」という視点は、従来の福祉系志望者以外に興味を持ってもらう有効な導線となる。高校生が実際に現場課題を聞き、テクノロジーで解決を考えることは、介護を“未来の産業”として捉えてもらう機会になりうる。採用は求人広告だけでなく、教育分野と連携した“長期母集団形成”が不可欠であることを示している。
■ 自分の事業所で検討できること
・地域の高校(福祉科/情報科/工業科など)への出前授業
・施設見学/ボランティアを定期受け入れ
・夏休み/冬休み向け「介護×DX」体験イベント開催
・地域包括/社会福祉協議会/教育委員会との連携強化
・ICT導入事例を高校向けに公開し、若者への魅力発信に活用
④ チャーム・ケア・コーポレーション下村会長の密着番組「関西リーダー列伝」放送へ
■ 記事の要約
介護大手「チャーム・ケア・コーポレーション」の下村隆彦会長が、テレビ大阪の番組「関西リーダー列伝」で特集される。テーマは「DX革命で介護業界の未来を変える」。下村会長の「生涯青春」を掲げて挑戦し続ける姿勢とともに、チャーム・ケアが進めるICT活用、業務効率化、入居者情報のデジタル管理、働き方改革などが紹介される。介護業界のイメージ刷新にも寄与する内容となっている。
■ 人事担当者にとっての学び
業界全体でDXが進むなか、求職者は「デジタル化された働きやすい職場」を求める傾向が顕著になっている。チャーム・ケアのような大手企業がDXに本気で取り組み、それがメディアで取り上げられることは業界全体の信頼性向上につながる。中小事業者も「一部の業務からDXを始める」ことで、職員の負担軽減や採用力向上が期待できる。“働きやすさの見える化”は採用広報の強い武器となる。
■ 自分の事業所で検討できること
・記録アプリ/インカム/タブレット活用の段階導入
・業務フローの見直しとデジタル化ポイントの抽出
・トップメッセージとして“DXへの本気度”を採用サイトに掲載
・職員負担が大きい業務の可視化(申し送り、夜勤記録など)
・DXの成功事例をSNS/採用ページで発信
⑤ 小田原市スケッター事業、半年で応募1000件突破—未経験者79%の新たな介護人材の入口に
■ 記事の要約
小田原市が株式会社プラスロボと連携して実施する「スケッター」事業がわずか半年で応募1000件超、マッチング700件超を達成。登録者の79%が介護未経験者で、10代学生から90代まで幅広い年代が参加している。身体介助を伴わない補助業務が中心のため、多くの地域住民が“気軽に福祉へ参加できる仕組み”となっている。また、スケッターから6名が介護職へ採用された実績も生まれ、地域密着型の新たな採用入り口として注目される。12月には好事例を共有するイベントも開催予定。
■ 人事担当者にとっての学び
採用市場が縮小する中、未経験者を地域から掘り起こすモデルは極めて有効。特に「単発」「短時間」「補助業務」のライトワークは、主婦、副業層、地域の高齢者など、多様な層を巻き込みやすい。スケッター経由で実際に採用につながった例が複数確認されていることから、介護の導入部分(入口)設計を工夫することが人材確保の重要戦略となる。地域住民の“福祉マインド”を刺激できれば、採用母集団の潜在層が大きく広がる。
■ 自分の事業所で検討できること
・補助業務(配膳、掃除、レクリエーション準備等)を切り出し“入口業務”として整備
・地域住民向けの介護体験会/見学会/ボランティア受入れ
・自治体/社協との連携強化
・副業人材/短時間人材の受け入れ体制整備
・スケッターや地域互助サービスの活用検討
今週の介護業界ニュースから見えてきたのは、採用難が続く中でも、「未来志向の取り組み」を行う事業者が確実に成果を上げ始めている という現実です。
DX化、地域連携、教育機関との協働、採用広報の強化、ライトワークの受け皿づくりなど、どれも特別な投資を必要とするものばかりではありません。
特に、
・“人材紹介に依存しない採用力の構築”
・“未経験者が関われる入口設計”
・“情報発信のわかりやすさ”
・“働きやすい職場の見える化”
は、今後どの規模の事業所でも避けて通れないテーマとなります。
変化が激しい時代だからこそ、早く動いた事業所ほど大きなアドバンテージを得ます。
本記事で紹介した「学び」と「できること」を、ぜひ自社の採用戦略に取り入れてみてください。
小さな改善でも、人材確保の未来は大きく変わります。
なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年11月17日~11月23日の注目ニュース
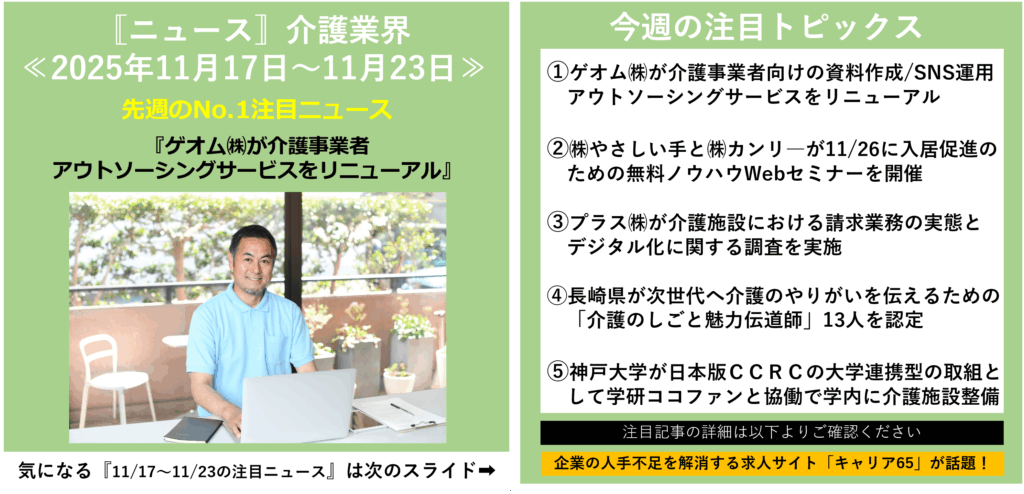
介護業界では、人材不足が常態化する中で「採用・定着」「魅力発信」「DX」「多世代連携」など、多方面で大きな変化が起きています。とくにここ数週間は、人事・採用に直結するニュースが相次ぎ、介護事業所に求められる役割や戦略が大きく揺れ動いています。
本記事では、介護人事に特に影響の大きい最新ニュース5本を厳選して解説し、
・今、業界で何が起きているのか
・各ニュースから人事が学ぶべきポイント
・自法人で今すぐ検討できること
を分かりやすく整理しました。
「採用が難しい」「応募が来ない」「定着率が課題」
こうした悩みを抱える人事マネージャーにとって、いま何を優先し、どう動くべきかを見極めるための“最新地図”としてご活用ください。
① ゲオム、介護事業者向けアウトソーシングサービスをリニューアル
■ 記事の要約
介護業界向け業務支援を行うゲオムが、事務・広報・資料作成などを請け負うアウトソーシングサービスを大幅にリニューアルした。今回の強化ポイントは、資料作成、加算算定のための各種帳票づくり、議事録作成に加え、採用広報に直結する「SNS投稿代行」や「調査リサーチ業務」まで幅広い領域をカバーした点にある。介護現場では慢性的な人手不足により、現場のケア以外の業務を担うスタッフの負担が増加している。特に加算算定や内部資料の作成は属人化しやすく、ミスが許されない領域であり、管理職や事務員の負担は限界に近い。今回のリニューアルは「現場がケアに集中できる環境づくり」を最大の目的としており、介護事業所の生産性向上と採用力強化に直結する取り組みといえる。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースからの学びは3点ある。
まず、① 非コア業務は外注するという流れが介護業界でも加速している こと。採用、人事、SNS、資料業務などは外部に任せることで、内部人材が本質業務に集中できる環境が整う。
次に、② 採用広報は「業務の一部」ではなく「経営の柱」へ変わりつつある こと。求職者がSNSで情報収集する時代において、投稿代行など外部の力を借りる選択肢は合理的だ。
最後に、③ 現場の業務削減=採用成功 という構図。現場が疲弊していれば新人定着率は下がり、採用コストは上がる。業務負担軽減は“採用施策そのもの”だと理解したい。
■ 自分の事業所で検討できること
まずは業務の棚卸しを行い、外部委託できる領域を洗い出す。特に「資料作成」「SNS」「加算更新」「議事録」は成果が出やすい分野。また、採用広報についてはテンプレート化や外部活用を進め、現場の負担を最小化する。さらに、外注の評価軸として「応募数」「残業削減」「書類ミス削減」など費用対効果を明確にし、自法人に最適なアウトソーシングの形を作ることが重要だ。
② 激変する介護施設の入所経路|紹介頼みから脱却へ求められる「向き合う力」
■ 記事の要約
介護施設の入所経路が大きく変化している。かつて主流だったケアマネや病院の紹介に依存した集客モデルは限界を迎え、家族が自らインターネット検索や口コミで比較検討する時代へと移行している。この流れを受け、「やさしい手 × カンリー」による無料オンラインセミナーが開催され、地上戦(現場営業)と空中戦(Webマーケティング)の両面から入所者獲得の手法が解説される。Googleマップ、口コミ、AIシミュレーションなど、デジタル活用を前提とした入所促進戦略が紹介される一方で、最も重要とされるのは「利用者・家族にどれだけ真摯に向き合えるか」という本質的な姿勢である。単なる施策ではなく、組織の価値提供そのものが成果を左右するというメッセージ性の強い内容となっている。
■ 人事担当者にとっての学び
この記事は入所促進の話に見えるが、採用にも直結する示唆が大きい。
① 採用も“紹介頼み”では限界がある。ハローワークや紹介会社だけでなく、SNS・Google・口コミ対策が不可欠。
② 現場のリアルな姿勢・理念の可視化は採用の核心。利用者への価値提供を語れる職場は求職者にも魅力的に映る。
③ デジタルマーケと現場営業の組み合わせが採用力を決める。学校訪問や地域連携などの“地上戦”と、SNSやHP改善の“空中戦”を同時に進めることで、応募率・入社率が大きく向上する。
■ 自分の事業所で検討できること
まず、Googleマップや口コミ改善など“オンラインの見られ方”の強化から着手する。次に、SNSで現場の理念・日常を発信し、求職者と家族双方に透明性を示す。また、学校や地域との連携を進め、若い世代に事業所を知ってもらう“地上戦”も並行する。オンラインとオフラインの両軸で採用と入所促進を一体化した戦略が求められる。
③ 介護現場の事務負担が深刻化|請求業務に月21時間以上が3割、質低下の声も
■ 記事の要約
プラス株式会社の調査で、介護現場の事務負担の深刻度が浮き彫りになった。特に介護報酬請求(レセプト)業務について、約3割が月21時間以上を費やしている と回答。また、約4割が「事務負担が介護の質を下げている」と危機感を訴えている。請求業務は専門性が高くミスが許されない一方、加算要件やルールが頻繁に変わり、多くの事業所で属人化が進んでいる。調査では、LINEを活用した電子請求システムに「導入したい」と回答した割合が7割を超えており、介護業界における事務DXへのニーズが急速に高まっていることも明らかになった。
■ 人事担当者にとっての学び
① 事務負担は離職率に直結する。介護職の離職理由の上位は「記録・書類が多すぎる」「残業が減らない」であり、事務量削減は採用と定着の最重要施策である。
② 事務DXは“採用広報”としても強い武器になる。求職者は働きやすさを重視しており、電子記録や自動化の仕組みがある事業所は選ばれやすい。
③ 管理者・事務員不足にも対応する施策としてDXは有効。事務職の採用難が続く中、業務自動化は事務方の負担軽減にも直結する。
■ 自分の事業所で検討できること
まずは「請求」「記録」「人事労務」の3領域の業務を棚卸しし、時間がかかっている業務を可視化する。その上で、請求業務の電子化(外注・システム導入)を最優先で検討する。導入したDX施策はSNSやHPで“働きやすさの証拠”として発信し、採用強化にも活用する。
④ 長崎県が「介護のしごと魅力伝道師」を新たに13名認定|次世代への魅力発信が加速
■ 記事の要約
長崎県が若い世代に介護の魅力を伝えるため実施している「介護のしごと魅力伝道師」制度で、今年度13名が新たに認定された。伝道師は若手介護職員が中心で、中学生・高校生に講話を行い、介護のやりがい、仕事の魅力、現場のリアルを伝える。今回、初の外国人伝道師も誕生し、多文化共生型の魅力発信が進んでいる。制度開始以来、102名が認定され、学校や地域イベントで介護のイメージ向上に取り組んでおり、人材確保と業界理解促進の“地域ぐるみの取り組み”として注目されている。
■ 人事担当者にとっての学び
① 若年層への認知活動は採用の最重要テーマ。介護業界は若手が集まりにくいが、若い世代にとっての「初めての介護体験」が将来のキャリア選択を左右する。
② 現場職員のリアルな声は最強の採用資産。動画・SNS・学校訪問など、職員の言葉を採用広報に活かすことで応募率が大きく向上する。
③ 外国人材の活躍は魅力発信そのもの。外国人職員が“伝える側”に立つことは、外国人採用・定着の象徴となり、組織の多様性・柔軟性を高める。
■ 自分の事業所で検討できること
若手職員を中心に「採用広報チーム」をつくり、SNSやHPで“働く人の声”を発信する。また、地域の学校と協力し、講話・見学会・ボランティア受け入れを実施。外国人材については、教育・メンター制度の整備と、活躍を可視化するPRが重要になる。
⑤ 神戸大学が“大学×介護施設”の日本版CCRCを推進|研究・教育・住まいが融合
■ 記事の要約
神戸大学は名谷キャンパスに、認知症グループホーム(18室)、サ高住(47戸)、介護付き有料老人ホーム(49戸)、学生マンション(20戸)を併設した多世代交流型の複合施設を整備する。学研ココファンと協働し、認知症予防、運動・栄養・睡眠など生活データの研究、多世代交流による社会実験を進める。政府が推進する日本版CCRCの大学連携型モデルとして、産学官の共同による“未来型の高齢者支援拠点”となる。施設は2027年9月開業予定で、1階には交流ホールを設け、地域との結びつきを強化する設計になっている。
■ 人事担当者にとっての学び
① 若い世代との接点づくりが介護人材確保の最重要テーマ。大学・学生との交流は、将来の介護職志望者の増加につながる。
② 研究データは採用の差別化要素になる。科学的介護・エビデンスに基づく運営は求職者の安心感を高め、採用広報の強力な武器となる。
③ 外部連携は教育・研修・働きやすさ向上に直結。大学・企業と組むことで、研修体系やDX導入が加速し、人材定着にもつながる。
■ 自分の事業所で検討できること
地域の大学・専門学校と連携し、インターン・実習・講話協力を進める。また、研究機関やメーカーと協働し、エビデンスに基づくケア体制を整備する。多世代交流イベントを開催し、地域コミュニティの中で“存在が選ばれる事業所”になる戦略を検討したい。
今回取り上げた5つのニュースは、一見バラバラに見えて、実は共通するメッセージがあります。
それは――
「採用も定着も、もう一つの方法だけでは成り立たない」
ということです。
● アウトソーシングによる業務削減(ゲオム)
● ネット比較時代の入所者・求職者との向き合い方(Joint記事)
● 事務DXの加速(プラス株式会社)
● 若手/外国人が伝える“介護の魅力”(長崎)
● 大学/企業との連携による人材創出(神戸大学×ココファン)
これらすべてが示すのは、
「現場の働きやすさ」
「デジタルの活用」
「地域・若者との接点づくり」
この3軸が同時に揃ってこそ、人材が自然と集まる事業所になれるということです。
採用難が続く時代だからこそ、
・現場の負担を軽くし
・働きやすさを可視化し
・若い世代への接点を増やし
・外部と連携して組織を開いていく
この一連の取り組みが“採用ブランディング”となり、応募と定着の両方を強化します。
いまの小さな一歩が、1年後の採用力を大きく変える。
あなたの事業所でも、できるところから一つずつ取り入れてみてください。
完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年11月10日~11月16日の注目ニュース
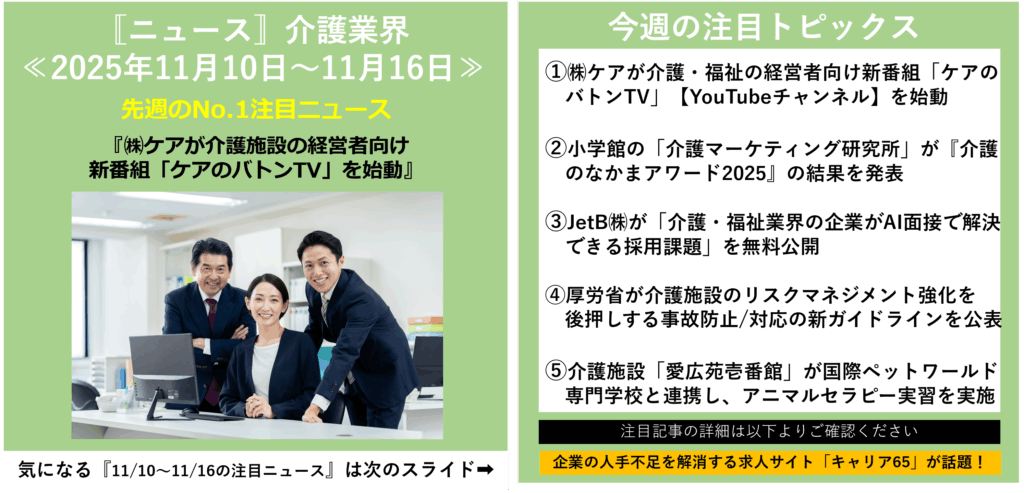
介護業界の採用環境は、ここ数年で大きく変化しています。人材不足の深刻化に加え、業務負担の増加、職員の定着難、採用スピードの重要性など、現場と人事部の双方に複合的な課題が押し寄せています。こうした状況の中で、今週も介護業界では「採用」「人材育成」「職員の働きやすさ」に直結する重要なニュースが多数発表されました。
本記事では、介護施設の事故防止ガイドラインの改訂、AI面接による採用の効率化、現場の負担を左右する製品アワード、アニマルセラピーなどの質向上の取り組み、そして経営の未来に関わる事業承継を扱ったYouTube番組の始動まで、多角的な視点から“人事担当者が押さえておくべき最新トピック”をまとめています。
「採用がうまくいかない」「現場の不満を減らしたい」「定着率を改善したい」「他社の最新トレンドを知りたい」
そんな企業の人事担当者が、“今日からの施策”として活用できる学びを凝縮しました。ぜひ戦略づくりに役立ててください。
① 介護・福祉の経営者向け新番組「ケアのバトンTV」始動【YouTubeチャンネル】
■ 記事の要約
株式会社ケアのバトンが、介護・福祉事業者向けに「ケアのバトンTV」をYouTubeでスタートしました。テーマは「事業承継・M&A」。実際に事業承継を経験した経営者のリアルな声や、専門家による成功・失敗事例、承継時に必要な考え方など、経営者が直面する課題に寄り添った内容をわかりやすく動画で解説しています。介護業界では後継者不足や事業継続の不安が高まっており、経営者が気軽に学べる媒体として注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
事業承継・M&Aは採用にも直結するテーマです。組織の将来性が見えない事業所は求職者から敬遠されがちで、逆に「承継の準備が整っている」「安定した経営基盤がある」とわかる事業所は採用力が強くなります。また、承継時には組織文化が揺らぎやすいため、人事部は“離職防止・情報共有・職員説明会”などを設計し、職員の不安を丁寧に取り除く役割を担う必要があります。
■ 自事業所で検討できること
・経営者の理念や今後の事業方針を採用ページで明確に示し、求職者に安心感を提供する
・事業承継や組織再編があった場合に「誰に / 何を / いつ伝えるか」をまとめた人事マニュアルを作成
・承継期における離職防止策(職員説明会 / Q&Aの整備 / 相談窓口)を準備
・若手育成やミドル層のリーダー育成を強化し、“経営の継続性”に結びつく組織基盤を整える
② 『介護のなかまアワード2025』結果発表(小学館 × 介護マーケティング研究所)
■ 記事の要約
小学館「介護ポストセブン」と介護マーケティング研究所が共同開催した『介護のなかまアワード2025』の受賞製品が発表されました。対象カテゴリーは、大人用紙おむつ・介護食・栄養補助食品・消臭剤の4つ。特徴は“現場のリアルな声”をもとに評価されている点で、介護職員・家族介護者の使用感、安全性、使いやすさなどが重視されています。
■ 人事担当者にとっての学び
介護現場の働きやすさは“人材の数”だけでなく“使用する製品の質”にも大きく影響します。使いにくい紙おむつや負担の大きい消臭作業は、職員のストレスや離職の原因にもなります。逆に、職員の声を反映した備品選びができる施設は“働きやすい職場”として採用力が向上します。また、求職者は「身体負担の少ない職場」を求めているため、こうした取り組みは大きなアピールポイントになります。
■ 自事業所で検討できること
・職員アンケートを通し、紙おむつ / 消臭剤 / 手袋などの備品の満足度を可視化
・アワード受賞製品のテスト導入や、現場スタッフが選べる購入制度を検討
・“備品へのこだわり”を採用ページで公開し、働きやすい職場であることを明示
・レクリエーション用品や介護食など、現場負担軽減につながる選定基準を整備
③ 介護企業向け「AI面接の導入資料」無料公開(JetB株式会社)
■ 記事の要約
JetB株式会社は、介護・福祉業界が抱える採用課題をAI面接で解決するための資料「介護・福祉業界の企業がAI面接で解決できる採用課題」を無料公開しました。資料では、応募者対応の自動化、面接調整の効率化、選考の属人性解消、辞退防止、採用スピード改善など、介護業界ならではの課題にAI面接がどう貢献するかを具体的に紹介しています。
■ 人事担当者にとっての学び
介護採用は“スピード勝負”であり、応募から24〜48時間以内に連絡できないと辞退率が急上昇します。AI面接は初期対応を高速化し、人員不足で採用が遅れる事業所の強い味方になります。また、面接官による判断のバラつきや主観的な評価を減らせるため、採用基準の統一にも効果的です。特に「忙しい現場が面接に出られない」「応募者対応で疲弊している」施設には大きなメリットがあります。
■ 自事業所で検討できること
・初期選考をAI面接に任せ、面接日程調整 / 応募者対応を自動化
・AIの評価データをもとに「活躍人材の特徴」を分析し、採用基準の改善につなげる
・面接スピードKPI(応募から面接までの時間 / 内定までの日数)を可視化して改善
・忙しい介護現場でも採用が停滞しない体制(AI+人のハイブリッド選考)を構築
④ 介護施設の事故防止・対応の新ガイドライン公表(厚労省)
■ 記事の要約
厚生労働省は、事故防止・事故対応に関する新たなガイドラインを公表しました。2012年の旧ガイドラインから大幅にアップデートされ、要介護度の高い利用者増加や介護テクノロジーの進化を踏まえた内容に改訂。体制整備、委員会の設置、研修体系、ヒヤリハットの活用、家族連携、事故種別ごとの再発防止策などを包括的に示しています。
■ 人事担当者にとっての学び
事故防止は“採用力・定着率”と密接に関係します。事故の不安や責任の重さは離職理由の上位であり、安全対策が整った職場は求職者から高評価を得ます。また、研修体系の整備やテクノロジー導入は働きやすさを高め、“安心して働ける環境”をアピールできる強力な採用資源となります。さらに、ミスを責めず改善につなげる組織文化づくりは、人材定着に欠かせません。
■ 自事業所で検討できること
・事故防止委員会の役割 / フローの明確化と定期ミーティングの実施
・研修体系(事故防止 / テクノロジー活用 / ヒヤリハット共有)の整理 / 公開
・報告しやすい文化づくり(責任追及型から改善型へ)
・転倒 / 誤薬 / 誤嚥など事故種別のマニュアルを新ガイドラインに合わせて更新
・安全対策を採用ページで発信し、求職者の安心材料とする
⑤ 介護施設でアニマルセラピー実習を開催(愛広会 × ペットワールド専門学校)
■ 記事の要約
医療法人愛広会と国際ペットワールド専門学校が連携し、介護施設でアニマルセラピー実習を実施したという開催報告です。学生とセラピードッグが施設を訪問し、利用者の情緒安定・リラクゼーション・コミュニケーション促進を目的としたプログラムを提供。利用者の笑顔や会話が増えた様子が紹介されています。
■ 人事担当者にとっての学び
アニマルセラピーなど“利用者満足度を高める取り組み”は、働く側にとっても魅力的な職場の象徴です。外部教育機関と連携している施設は「学べる職場」「地域と連携している施設」として求職者に好印象を与えます。また、セラピー導入により施設全体の雰囲気が柔らかくなり、感情労働の負担軽減やメンタルケアにも寄与します。
■ 自事業所で検討できること
・地域の学校 / 大学 / 団体と連携した療法(アニマル / 音楽 / 園芸など)の導入
・レクリエーションの質向上を採用ページで可視化し、魅力訴求につなげる
・SNSや採用広報で取り組みを発信し、施設の“やさしい文化”を見せる
・職員の負担が少ないレクリエーションを外部と協働で設計
・月1回の少人数 / 短時間セラピーなど、予算に合わせたスモール導入
今週発表されたニュースは、いずれも介護業界の「採用」「育成」「定着」「業務改善」に直結するものでした。事業承継による組織の安定性、現場負担を軽減する製品選び、採用スピードを改善するAI面接、安全文化を醸成するガイドライン改訂、そして利用者満足度を高めるアニマルセラピーなど、どれも“働きやすい施設づくり”に欠かせない要素です。
介護の採用は、単に人を集めるだけでは成り立ちません。
「魅力的な職場をつくり、安心して働ける環境を整え、その価値をわかりやすく伝えること」
この一連の流れがあってこそ、応募が増え、定着が進み、人材が育つ好循環が生まれます。
現場が抱える課題は事業所ごとに異なりますが、今回紹介したニュースの中には、どんな施設でも“すぐに活用できるヒント”が必ずあります。
ぜひ、気になったトピックから小さく取り入れてみてください。
一つの改善が、働く人の安心につながり、採用成功への大きな一歩になります。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年11月3日~11月9日の注目ニュース
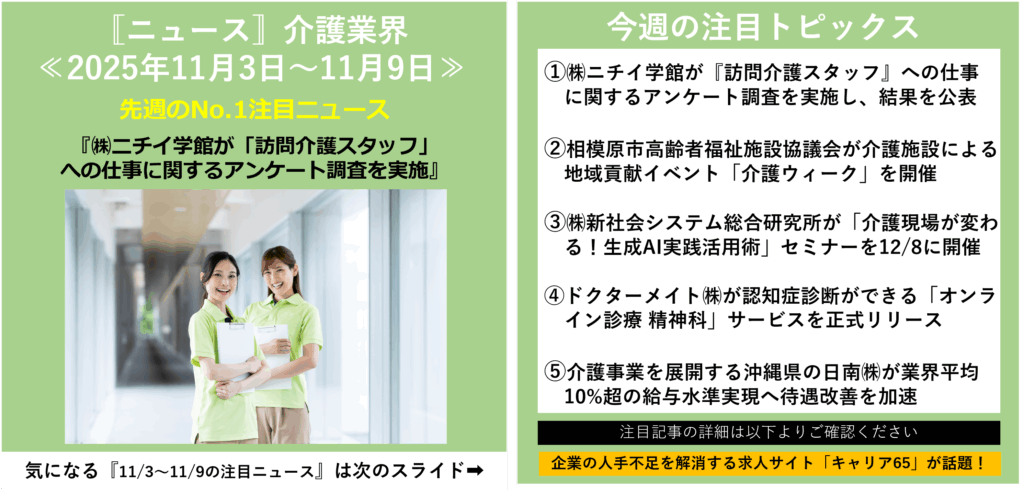
人材不足が続く介護業界では、「採用力の強化」「離職防止」「働き方改革」をめぐる動きが相次いでいます。
今週は、大手企業の意識調査から地域イベント、AI活用、オンライン診療、待遇改革まで、現場の人事担当者に役立つ5つのトピックをピックアップしました。
ぜひ、自社の採用や人材育成のヒントとしてお役立てください。
① ニチイ学館「介護の日アンケート」|“やりがい”が働き続ける理由に
株式会社ニチイ学館は、「介護の日」にあわせて訪問介護スタッフ8,388人を対象にアンケートを実施。仕事の魅力1位は「利用者様と1対1で向き合える」(42.2%)、約9割が「今後も続けたい」と回答しました。理由のトップは「自分に合っているから」(52.8%)で、働く意欲の源泉が“感謝”や“つながり”にあることが明らかになりました。
■ 人事担当者にとっての学び
介護職は「きつい仕事」という印象が強い中で、実際には“前向きなモチベーション”で働く人が多数。採用広報では「働く喜び」や「感謝される瞬間」を現場の声として伝えることが、応募意欲を高めるカギです。
■ 自事業所での実践ポイント
・現場スタッフの声をアンケートで収集し、採用ページで発信。
・「利用者と1対1で向き合える」など、“やりがいの実感”を伝えるコピーを活用。
・研修/定着施策に「仕事の意義」を再確認する時間を組み込む。
② 相模原市「介護ウィーク」|地域とつながる介護施設の発信力
相模原市では11月11日〜18日、市内17施設が参加する「介護ウィーク」が開催。福祉器具体験、防災士講演、バザー、コグニサイズ体験、認知症予防講演など、介護施設と地域住民が交流する場として注目を集めています。
■ 人事担当者にとっての学び
採用において「地域から信頼されているか」は大きな要素。地域とつながる施設ほど、応募者から“雰囲気が良い職場”と感じられやすくなります。こうしたイベントは採用ブランディングにも有効です。
■ 自事業所での実践ポイント
・地域住民向けの健康講座や見学会を定期開催。
・SNSや採用サイトで、イベントの様子を積極発信。
・スタッフが地域貢献を実感できる仕組みを整え、エンゲージメントを向上。
③ SSKセミナー「生成AI活用術」|AIで広がる採用・人材育成の可能性
新社会システム総合研究所(SSK)は、「医療・介護現場が変わる!生成AI実践活用術」セミナーを開催。講師の長 英一郎氏(東日本税理士法人 所長)は、AIによる文書作成・職員教育・経営分析の効率化事例を紹介予定です。
■ 人事担当者にとっての学び
生成AIは採用・教育の“見えない負担”を軽減するツールに。求人票作成、面接質問、応募対応、教育資料作成などを自動化することで、少人数でも高品質な採用活動を実現できます。
■ 自事業所での実践ポイント
・採用業務の一部をAI化(求人原稿/問い合わせ対応など)。
・マニュアルやOJT教材の自動作成に活用。
・個人情報保護を前提に、AI利用ガイドラインを整備。
④ ドクターメイト「オンライン診療 精神科」|職員負担を軽減するDX連携
ドクターメイト株式会社は、介護施設向けに「オンライン診療 精神科」サービスを正式リリース。精神科医がオンラインで診療・処方まで行うことで、医療過疎地域の入居者支援と、介護職員の心理的負担軽減を同時に実現します。
■ 人事担当者にとっての学び
医療DX化は、単に業務効率ではなく「職員の安心感」を高める施策。メンタルケアの外部連携体制が整うことで、現場のストレス軽減・離職防止にも直結します。
■ 自事業所での実践ポイント
・精神科 / 内科のオンライン診療導入を検討。
・「専門職が支える安心の職場」として採用広報に活用。
・DX推進人材を育成し、チームケアと情報共有を強化。
⑤ なんじょう苑グループ「待遇改革」|“介護は稼げない”を変える挑戦
沖縄県のなんじょう苑グループ(日南株式会社)は、開設11周年を機に「介護は稼げない」という固定観念を覆す待遇改革を発表。業界平均より10%以上高い給与水準を目指し、資格取得支援や夜勤体制の見直しを進めています。
■ 人事担当者にとっての学び
給与アップはコストではなく“採用・定着への投資”。キャリアパスや研修をセットで整備することで、職員に「ここで長く働ける」と思わせる環境が作れます。
■ 自事業所での実践ポイント
・地域 / 業界平均と比較し、給与水準を定期的に見直す。
・キャリアパスと給与レンジを可視化し、採用時に明示。
・「待遇+働きやすさ」を両立した改革を発信。
“人が集まる職場”は変化に前向きな職場
今週のニュースから見える共通点は、「変化を恐れずに、新しい仕組みを取り入れる施設ほど、人が集まり、定着する」ということ。
AI、オンライン医療、地域交流、待遇改革――どの取り組みも共通しているのは、「職員が安心して働ける環境づくり」が採用ブランディングの核心にあるという点です。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年10月27日~11月2日の注目ニュース
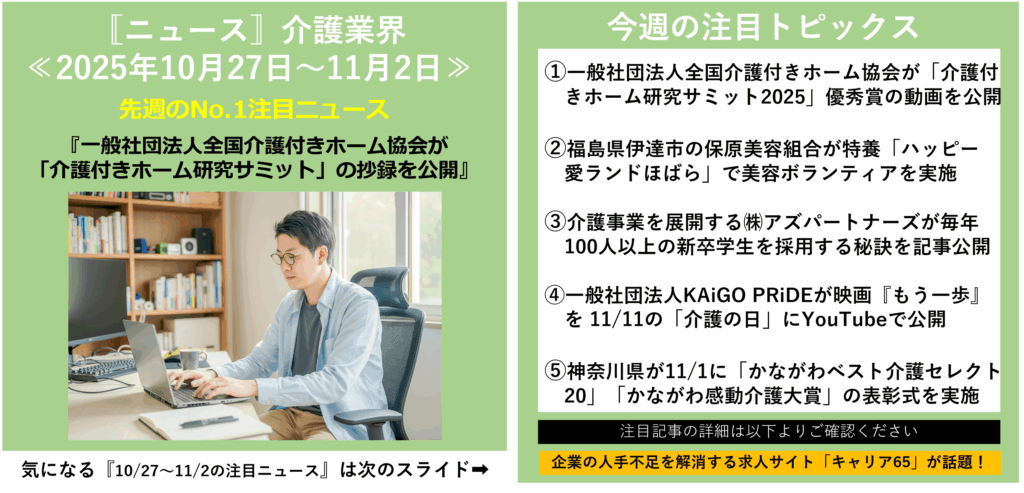
① 介護付きホーム研究サミット2025 優秀賞15組の動画・抄録公開
全国介護付きホーム協会は、2025年9月29日より「介護付きホーム研究サミット2025」における優秀賞15組の動画と抄録を公開しました。これは、第13回事例研究発表全国大会の開催に先立ち、全国の介護付きホームが取り組む“現場改善”の成功事例を共有する取り組みです。
公開された事例には、「外国人職員の定着支援」「週休3日制度」「柔軟な日勤シフト導入」など、人材確保や働き方改革に直結するテーマが並び、業界全体における“人事・労務改革の実践モデル”として注目を集めています。
人事担当者にとって学べるのは、現場の課題解決を“共有財産化”する仕組みの重要性です。他法人の取り組みを可視化し、ベンチマークできる環境が整うことで、「定着率向上」「離職防止」「職員エンゲージメント強化」など、自社でも即実践できるヒントが得られます。また、優秀事例として外部に発信すること自体が、採用ブランドの向上にもつながります。
自社でもこうした事例発表の文化を取り入れることが有効です。まずは「職員のアイデアを評価する」「社内ミニ表彰を設ける」「取り組みを動画化し社内外に共有する」など、小さなアクションから始めるとよいでしょう。発信を通じて、“現場が主役の組織づくり”を促すことが、採用力強化にも直結します。
② 高齢者にメイクやネイル 伊達・保原美容組合、特養でボランティア
福島県伊達市の保原地区美容組合に所属する美容師らが、特別養護老人ホームでメイクやネイルのボランティアを行いました。高齢者に「美を通じて笑顔と自信を取り戻してもらう」ことを目的としたこの活動では、入居者が久しぶりに口紅をつけたり、爪を整えたりしながら会話を楽しむ姿が見られました。
利用者からは「若返った気がする」「久しぶりに鏡を見るのがうれしい」といった声があがり、職員にも「利用者の新しい一面を知れた」と好評だったようです。
この取り組みから学べるのは、介護における“感情ケア”の重要性です。身体的支援だけでなく、心理的な満足感や自己肯定感を高めることが、QOL(生活の質)の向上につながります。また、地域の専門職と連携することで、現場職員の負担軽減や新しい刺激にもなります。
介護職員の“やりがい”を生み出す仕掛けとしても、こうした外部コラボは大きな効果を持ちます。
自事業所でも「地域×介護×美容」「学生×介護×福祉」など、異業種連携のボランティア企画を定期化するのがおすすめです。SNSで発信すれば採用広報にも活用でき、働く意義や誇りを伝える絶好の機会にもなります。
“美”や“笑顔”をキーワードに、介護現場の価値を地域に広げていく取り組みは、採用・定着の両面で注目すべき新しい動きといえるでしょう。
③ “ボランティアではなくサービス業”から始まった介護事業の意識改革
アズパートナーズ社長・植村健志氏のインタビューでは、介護を“ボランティアではなくサービス業”と位置づけ、職員に「お客様に選ばれる価値を提供する」という意識改革を浸透させた経営方針が紹介されています。
同社は首都圏を中心に介護付き有料老人ホームを展開し、年間100人以上の新卒を採用するなど、業界でも採用力に定評があります。
施設の快適さや給与条件だけでなく、「誇りを持てる仕事文化」を重視する姿勢が、若手人材の定着を支えています。
人事担当者にとっての学びは、採用ブランドは“理念”で決まるという点です。給与や勤務条件だけでは差別化できない時代に、“どういう想いで介護に向き合うか”を明確に語れるかが、採用力の鍵となります。
また、職員にとっても“サービス提供者”としての誇りを持てる文化があることが、長期的なモチベーション維持につながります。
自社でも採用メッセージや求人コピーを見直し、「○○を叶える介護」「人の心に寄り添うサービス業」など、価値観を明確に打ち出すとよいでしょう。
さらに、キャリアパスを可視化し、「3年後・5年後にどんな成長ができるか」を提示することで、採用後のギャップを防ぎ、若手・中堅の双方に安心感を与えることができます。
④ ―“介護を誇る国へ”を目指すKAiGO PRiDE、新たな社会発信を始動―
介護業界の魅力を社会全体に発信するプロジェクト「KAiGO PRiDE」は、厚生労働省の補助事業として制作した短編映画『もう一歩』を、11月11日の「介護の日」からYouTubeで一般公開します。
映画は、介護現場で働く若手職員と利用者の心の交流を描き、「介護の仕事=誇りある職業」というメッセージを込めた作品。公開と同時に、「介護を誇る国へ」を掲げた全国的なキャンペーンも始動する予定です。
人事担当者にとって注目すべきは、採用広報に“感情訴求”を取り入れる重要性です。KAiGO PRiDEは「大変」よりも「やりがい」「誇り」「感動」を前面に出すことで、介護職の社会的イメージを刷新しました。
映画や映像は、“共感を生む求人広報ツール”としても非常に効果的です。採用現場でも「理念動画」「職員ストーリー」などを活用し、応募前の心理的共感を生み出す仕組みが求められます。
自社でも「介護の日」や「敬老の日」に合わせて、自社職員のインタビュー動画やショートドキュメンタリーを制作し、SNSやホームページで発信するとよいでしょう。
職員の誇りを可視化することで、採用・定着の双方にポジティブな循環が生まれます。
⑤ 「かながわベスト介護セレクト20」「感動介護大賞」表彰・認証交付
神奈川県は、介護サービスの質向上と職員の働きやすさ向上に取り組む事業所を表彰する「かながわベスト介護セレクト20」および「感動介護大賞」の表彰式を11月1日に開催しました。
さらに、一定基準を満たした優良介護サービス事業所には「かながわ認証」が交付され、奨励金(最大100万円)が支給されます。選定基準には人材育成、処遇改善、働き方改革など“人を軸とした経営”が重視されています。
この取り組みは、人事部門が“表彰を目指す採用戦略”を設計できる好機です。認証取得や表彰実績は、求人応募者にとって大きな安心材料であり、「働きやすい職場」としてのブランドを高めます。
また、奨励金を活用すれば、教育・研修・福利厚生などへの再投資も可能です。
自社でもまず、「離職率」「満足度」「育成制度」を指標化し、改善サイクルを設けることから始めましょう。
「受賞を目指す職場づくり」は、スタッフの意識改革とチーム力強化につながります。採用・定着・サービス品質の三位一体を実現する道筋として、神奈川県のこの仕組みは大いに参考になるでしょう。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年10月20日~10月26日の注目ニュース
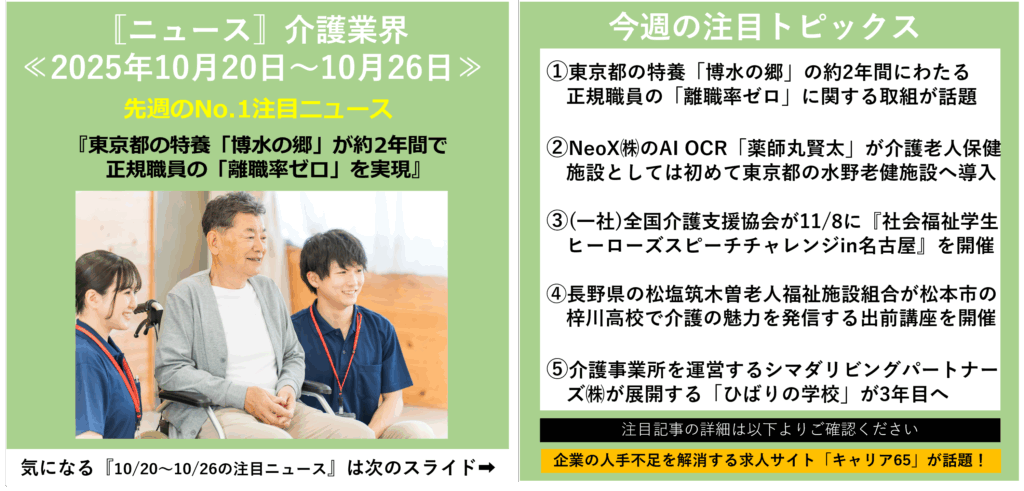
シニア人材の採用・育成・定着を考える人事担当者に向けて、今週注目された介護業界の最新ニュースをピックアップ。
現場発の実践事例からAI・DX、教育連携まで、採用や人材戦略に役立つ動きをまとめました。
① 離職率ゼロ実現|残りたくなる介護現場の設計図 特養「博水の郷」
東京都世田谷区の特別養護老人ホーム「博水の郷」が、2022年9月~2024年8月まで離職率ゼロを達成。
待遇改善、キャリア支援、業務効率化、心理的安全性をすべて連動させた「多層的な定着デザイン」が話題を呼んでいます。
「任せて支える」文化を軸に、若手も挑戦できる組織風土を形成。
介護報酬や補助金を積極的に職員へ還元し、“働く意欲が循環する職場”を実現しています。
👉 学びポイント:
採用後の体験設計こそ離職防止の要。
制度よりも“人間関係設計”を重視することが、採用・定着力の両面を強化します。
👉 事業所でできること:
・月1回の雑談型1on1を導入
・「ありがとうカード」制度で感謝の文化を可視化
・新人フォローを3カ月→半年に延長
・ICT導入/清掃外部化で業務軽減
② AI-OCR「薬師丸賢太」が介護施設の分包業務を効率化
埼玉県の水野老人介護施設が、介護老人保健施設として初めてAI-OCR「薬師丸賢太」を導入。
処方箋の内容を自動で読み取り、電子カルテ・分包システムへ転記する業務を自動化しました。
これにより人的ミスの防止と残業削減を実現。
職員からは「入力作業が減り、利用者との会話時間が増えた」と好評です。
👉 学びポイント:
AI導入は「業務効率化」だけでなく、“介護の本質時間を取り戻す”DX。
生産性向上が“働きやすさ”や“定着”へ直結する好例です。
👉 事業所でできること:
・AI/ICT導入を採用ブランディングに活用
・「DX=介護を豊かにするツール」としてメッセージ化
・バイタル/記録入力/スケジュール管理などDX化領域を棚卸
・若手職員をDX推進リーダーに任命
③ 若者が語る「創造する介護」|学生ヒーローズスピーチチャレンジin名古屋
名古屋市で11月開催の「社会福祉学生ヒーローズスピーチチャレンジ」は、介護を“支える仕事”から“創造する仕事”へをテーマに、学生が福祉の未来を語る全国イベント。
高校・短大生たちが、DX・地域共創・遊びの要素を交えながら、介護の新しい価値を提案しました。
「けん玉で人の成長を支える喜び」「ICT活用で広がる未来のケア」など、学生ならではの柔軟な発想が集まり、介護の創造性を社会へ発信しています。
👉 学びポイント:
若者世代にとって、介護は“守る”ではなく“創る”仕事。
採用メッセージも「挑戦」「共創」「デザイン」といったキーワードに転換が必要です。
👉 事業所でできること:
・学校連携/学生インターンを強化
・若手発信型プロジェクト(地域イベント、SNS企画など)を導入
・「創造型介護」を採用キャッチコピーに活用
・DX/デザイン思考を現場改善に取り入れる
④ 介護職の魅力を高校生へ|梓川高校で出前講座を実施
松本市の梓川高校で、地元施設職員による「介護職出前講座」が開催。
「身体的ケア・精神的ケア・社会的ケア」の3軸で仕事内容を紹介し、生徒たちと質疑応答を行いました。
「利用者との信頼関係の築き方」「給料やボーナス」などリアルな質問が寄せられ、介護職の“現場の声”に生徒が強く関心を示しました。
参加後には「笑顔が多い職場」「人と深く関われる仕事」との感想も。
👉 学びポイント:
採用は求人からではなく、“教育現場との対話”から始まる。
地域の高校生に介護の魅力を伝えることは、未来の人材づくりに直結します。
👉 事業所でできること:
・高校/専門学校と連携し出前講座を定期開催
・若手職員による体験談講演を導入
・職場見学/介護体験イベントを設計
・地域メディアと協働し、活動を発信
⑤ 未経験からプロへ導く!シマダグループ「ひばりの学校」3年目へ
シマダリビングパートナーズ(東京都渋谷区)が運営する「介護職員初任者研修講座 ひばりの学校」が3年目を迎え、12月コース受講生を募集。
現役介護士による実践的少人数授業と、資格取得後の就労支援制度を特徴とする教育モデルです。
「ガーデンテラス」シリーズでの就労サポート、講師の全国コンテスト受賞歴、北欧風の学び空間など、学びと働く意欲を両立させる仕組みが整っています。
👉 学びポイント:
採用難時代の鍵は「教育の内製化」。
資格取得支援と就労支援を一体化することで、採用を“教育から逆算”する新しい人事戦略が可能になります。
👉 事業所でできること:
・自社内での初任者研修/OJT講座の企画
・教育機関との提携で受講料補助制度を導入
・「働きながら学べる職場」ブランドを打ち出す
・社内講師を育成し、現場教育の質を標準化
今週の5つのトピックに共通するキーワードは、
👉 「育てる」「創る」「つながる」。
採用を“入口”ではなく“仕組み”として設計することで、
介護現場はより魅力的な職場へと進化します。
人事が動けば、介護の未来も動く。
今こそ、“辞めない採用”から“続く介護”へ。
完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年10月13日~10月19日の注目ニュース
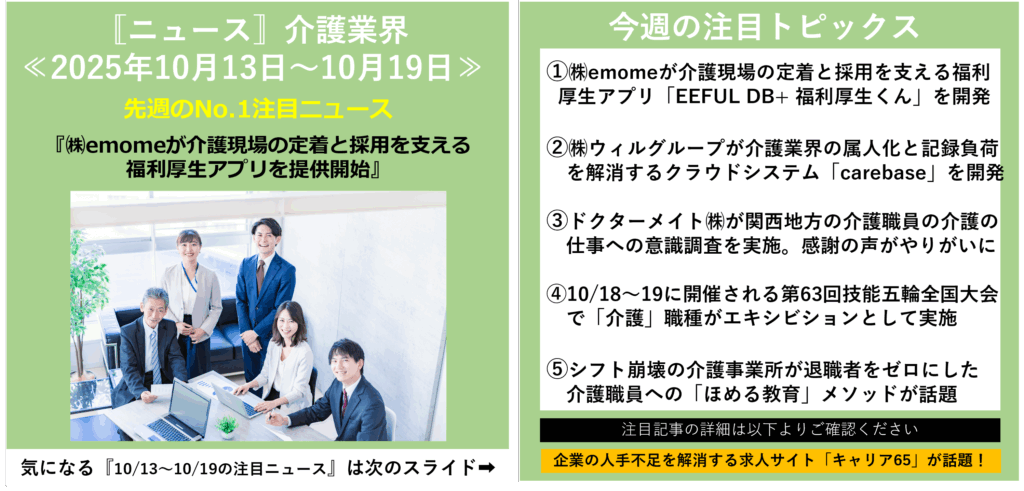
① 介護職員の“暮らしの安心”を支える!低コスト福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」提供開始
記事の要約
株式会社emomeは2025年10月16日、介護現場向けの福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」をリリースしました。
このアプリは、給与や勤怠データと連携しながら、割引サービスや健康支援機能を提供。職員の“暮らしの安心”を支えることで、離職防止と採用力向上を両立する仕組みです。
月額制のため中小施設でも導入しやすく、「職員を大切にする姿勢」をアピールできる点が特徴です。
人事担当者にとっての学び
採用・定着のカギは給与だけでなく、職員の生活満足度の向上にあります。
福利厚生を整えることは、求職者に「働きやすさ」を伝える強力な採用ツールになり、既存職員にも安心感を与えます。
特に、クラウド型アプリを使えば、人事担当者の管理負担を増やさずに“定着施策の仕組み化”が可能です。
自分の事業所で検討できること
・求人票や採用サイトに「福利厚生の充実」を明記し、応募者への訴求力を高める。
・低コストの福利厚生アプリを比較検討し、小規模でも始められる仕組みを導入。
・職員アンケートなどで満足度を定期的に把握し、定着率アップのデータを蓄積。
② 介護現場の「属人化」と「記録負荷」を解消!クラウドシステム「carebase」提供開始
記事の要約
ウィルグループは2025年10月14日、介護現場の業務支援クラウド「carebase(ケアベース)」の本格提供を開始しました。
このシステムは、動画マニュアル×記録管理を一体化し、介護現場で課題とされる“属人化”と“記録の手間”を解消するもの。
動画を活用した研修やマニュアル共有により、新人・未経験者の教育を効率化。さらに、音声入力やスマホ操作による記録の簡略化で、スタッフの残業削減やミス防止を実現します。
初期費用0円キャンペーンも実施中です。
人事担当者にとっての学び
このニュースが示すのは、「採用」だけでなく「教育」と「業務効率化」も人事の守備範囲になっているということ。
人材不足を根本から改善するには、入職後の育成スピードや職員の働きやすさを整えることが不可欠です。
動画マニュアルのような仕組みは、教育のバラつきを減らし、離職防止にもつながります。
自分の事業所で検討できること
・研修/OJTを動画化し、誰でも同じ内容を学べる環境を整える。
・紙の記録をクラウド化し、事務負担を削減。
・「教育DX(デジタル教育)」を採用広報にも活用し、「成長できる職場」として発信する。
③ 関西介護職員の約半数が「地域介護の将来に不安」──現場の声が示す課題とは
記事の要約
株式会社ドクターメイトは2025年10月14日、関西の介護職員500名を対象にした意識調査を発表しました。
調査では、45.8%が「地域の介護体制の将来に確信を持てない」と回答し、将来不安を抱える職員が多い実態が明らかに。
一方で、「やりがい」を感じる理由の1位は「利用者や家族からの感謝」(38.0%)と、仕事自体への誇りは強いことも分かりました。
不安要因としては、「賃金水準の低さ」(42.1%)、「人材不足」(30.3%)、「利用者重度化」(26.9%)が上位に挙げられています。
人事担当者にとっての学び
この結果から見えるのは、職員は“やりがい”より“将来の安心”を求めているという現実です。
採用広報では「やりがいのある仕事」と伝えるだけでなく、“安定して働ける環境”をどう保証するかを示すことが重要です。
また、現場の負担感を放置すれば、離職や定着不安につながります。
教育制度やICT導入による業務軽減、キャリアパスの明示など、“安心して続けられる職場設計”が不可欠です。
自分の事業所で検討できること
・5年後/10年後の事業方針を職員と共有し、将来ビジョンを明確化する。
・感謝や評価を「見える化」する仕組み(ありがとう掲示板/表彰制度など)を導入。
・賃金以外の支援策(休暇・研修・相談体制)を整備し、“働きやすさ”で差別化する。
④ 介護が“技能職”として脚光!技能五輪全国大会で初の「介護職種」エキシビション開催
記事の要約
厚生労働省は、2025年10月18日(土)・19日(日)開催の「第63回技能五輪全国大会」で、初めて「介護」職種をエキシビション種目として実施すると発表しました。
大会では、若手介護職員による介護技能の実演や、専門家によるトークセッション「介護の世界」も同時開催。
これまで製造・建築中心だった技能五輪に“人を支えるケア技術”が加わることで、介護を「感情労働」ではなく「専門技能」として社会に発信する試みとなっています。
人事担当者にとっての学び
この動きは、介護業界の採用・教育戦略において大きな転換点です。
“介護=スキル職”という認識が広がれば、若手層へのイメージ向上と採用力強化につながります。
人事担当者は、「介護職の専門性」「技術としての成長性」を打ち出すことで、これまで採用が難しかった若年層や異業種人材へのアピールが可能になります。
自分の事業所で検討できること
・研修/育成制度を「技能ステップアップ制」に再設計し、成長が見える仕組みを整える。
・資格取得支援や技能評価制度を導入し、“技術で昇進できる職場”をアピール。
・社内掲示やSNSで技能五輪の話題を共有し、「介護は誇れる専門職」という文化を醸成。
⑤ 「ほめる教育」で離職ゼロを実現!介護現場に学ぶ“人が育つ職場”の仕組み
記事の要約
ダイヤモンド・オンラインの連載「福祉・介護ニュース3面鏡」では、株式会社スパイラルアップ代表の原 邦雄氏(ほめ育財団代表理事)が、“ほめる教育(ほめ育)”を取り入れて離職ゼロを達成した介護事業所を紹介しています。
20名中7名が1年で辞めるほどの離職率だった現場が、「ほめる文化」を根づかせた結果、職員の表情・チームワーク・サービス品質が大きく改善。
上司から部下、同僚同士での「ありがとう」「助かったよ」といった言葉の循環が、組織の一体感を生み出しました。
人事担当者にとっての学び
この記事が教えてくれるのは、人は“評価”だけではなく“承認”で動くということ。
介護のように感情労働の比重が高い職場では、メンタルケアが離職防止に直結します。
特に、採用や処遇改善だけでは解決できない“人間関係の質”こそ、現場定着のカギです。
「ほめ育」はコストをかけずに始められる心理的安全の仕組みであり、教育よりも文化づくりが重要であることを示しています。
自分の事業所で検討できること
・朝礼や会議で「1日1回、仲間をほめる・感謝を伝える」仕組みを導入。
・ほめる文化を評価制度やOJTに組み込み、マネジメントに定着させる。
・離職率や面談アンケートで“心理的安全度”を測定し、職場の温度を可視化。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年10月6日~10月12日の注目ニュース
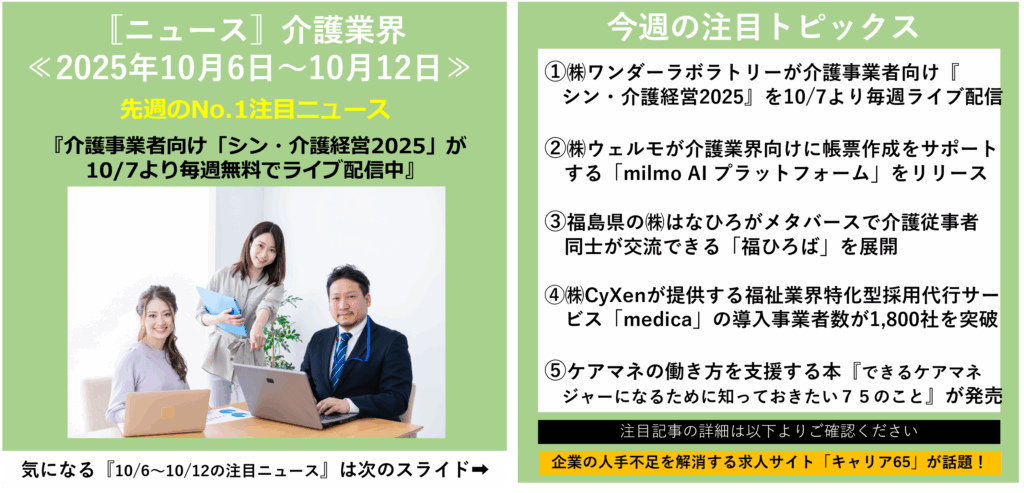
① 40代経営者が語る「2050年構想」|未来を見据えた介護経営の視点とは
株式会社ワンダーラボラトリーが発表した新シリーズ『シン・介護経営2025』では、全国の40代介護経営者10名が登壇し、2050年を見据えた介護の未来を語ります。
AI、地域共生、ブランディング、人材育成など、介護業界が直面する課題を横断的に議論する内容です。
人事の学び:
・若手経営層の“未来志向”から、長期的な人材戦略の重要性を再認識できる
・ICTや地域共生など、複数テーマを組み合わせた組織設計が今後の主流に
・外部の学びや交流を通じた「人事センス磨き」が必要
自社で検討できること:
2050年を見据えた人材育成ビジョンを立て、中堅リーダーの発信機会を増やす。
ライブ配信や業界ウェビナーを社内研修に組み込み、未来志向の人事文化を醸成する。
② AIが帳票作成をサポート!「milmo AI プラットフォーム」正式リリース
ウェルモ社が発表した「milmo AI プラットフォーム」は、介護業界特有の帳票作成をAIが支援する新サービス。
ケアプランや計画書を自動生成し、業務効率化を図る仕組みです。
人事の学び:
・事務負担軽減=職員定着率向上につながる
・DX化は「人を減らす」ではなく「人を活かす」視点で進めるべき
・導入には教育と安心感(セキュリティ説明)が欠かせない
自社で検討できること:
一部部署でAI帳票化を試験導入し、効果を数値化して段階展開を検討する。
導入後は、誤記・ミス検出フローを整備し、現場教育と並行して改善ループを回す。
③ メタバースで業界交流を実現|福島発「福ひろば2.0」の挑戦
福島県の株式会社はなひろが、福祉・介護ポータル「福ひろば」をメタバース空間に拡張。
研修、相談、イベントを仮想空間上で行える仕組みを構築しました。
人事の学び:
・地域を超えた学び・交流が人材の孤立防止につながる
・メタバース採用説明会は、遠隔地応募者への新しい接点になる
・DXの“体験価値”を高める施策として注目
自社で検討できること:
仮想空間を活用した法人説明会・職員交流会を企画。
まずはZoom等を活用した「仮想拠点版」から始め、職員同士の横のつながりを促進する。
④ 導入1,800社突破!採用代行サービス「medica」に見る“伴走型”の強み
CyXen社の「medica(メディカ)」が、介護・医療・福祉業界で導入1,800社を突破。
AIによる求人最適化と、人による伴走支援を組み合わせた採用支援モデルが注目されています。
人事の学び:
・“分析+伴走”のハイブリッド支援が採用成功を左右
・採用アウトソースでも「成果を見える化」する契約が重要
・採用業務を委託し、人事担当者が戦略業務へ移行できる
自社で検討できること:
小規模パイロット導入で効果を検証し、KPI(応募数・採用単価・スピード)を設定。
定期レビューとフィードバック体制を整え、外部パートナーと成果改善を進める。
⑤ テクノロジー時代だからこそ問われる「対人支援力」|新刊『できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと』
学研グループから刊行された本書は、AI・ICTが進む中でも「人と人をつなぐ力」の重要性を説く実践書。
制度理解からストレス管理まで、現場で信頼されるケアマネ像を具体的に示しています。
人事の学び:
・技術より“人間力”の評価が差別化要因に
・実践知を共有し、現場ナレッジを組織の資産に変える
・メンタルケアやキャリア支援の設計にも活かせる
自社で検討できること:
ケアマネ向け読書会や研修を通じて、対人支援力の強化に取り組む。
また、評価基準に「共感力」「調整力」など人間的要素を組み込み、育成と表彰制度に反映させる。
完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年9月29日~10月5日の注目ニュース
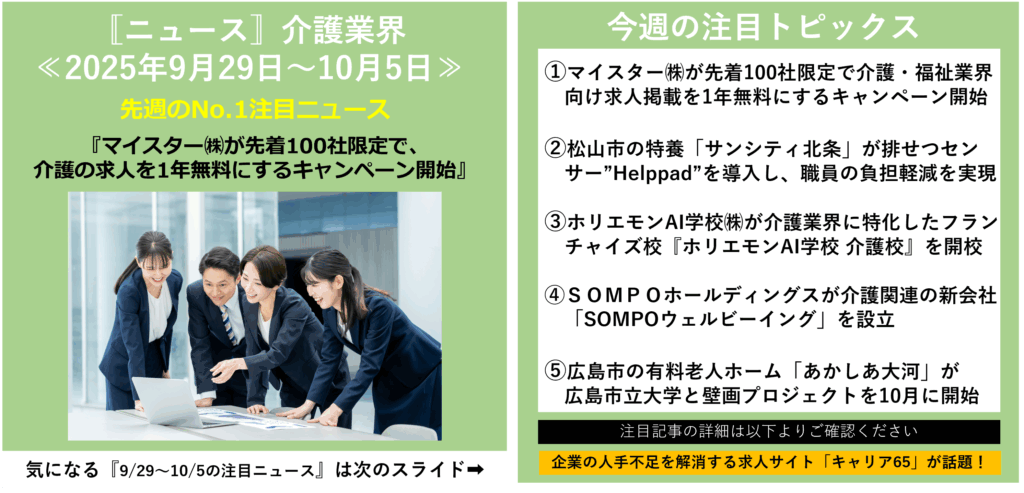
① 【先着100社限定】MAPJOBが1年間無料掲載キャンペーンを開始
マイスター株式会社が運営する求人サイト「MAPJOB」は、介護・福祉業界の事業者向けに求人掲載を1年間無料化するキャンペーンを開始しました。
応募や採用時の費用も一切不要で、先着100社限定というインパクトのある内容です。
この動きは、採用コストを抑えながら求人露出を拡大できる好機です。特に地元密着型採用に強いMAPJOBの特性を活かし、「通いやすい職場」「地域に根ざした施設」を訴求することで、応募効果を最大化できます。
まずはキャンペーンを試験利用し、応募数や面接率などのデータを比較・検証してみるとよいでしょう。
② 松山の特養「サンシティ北条」が厚労大臣表彰|AIで介護職員の負担軽減
愛媛県松山市の特別養護老人ホーム「サンシティ北条」が、AIとセンサーを活用しておむつ交換のタイミングを自動判定するシステムを導入。
職員の巡回回数を減らし、身体的・精神的負担を軽減したことで、厚生労働大臣表彰を受けました。
この事例は、テクノロジー活用が「働きやすい職場づくり」として正式に評価される好例です。
AI導入は人員削減ではなく、離職防止・業務効率化・職員定着につながる投資と位置づけられます。
導入コストや運用体制を含め、まずは夜勤帯や特定ユニットから段階的に試験導入するのが現実的です。
③ 『ホリエモンAI学校 介護校』が開校|生成AI人材の育成を本格化
ホリエモンAI学校が、介護現場に特化したフランチャイズ校「介護校」を新たに開校。
生成AIを活用して記録業務や報告書作成を自動化し、職員の作業負担を軽減するスキルを教育する仕組みを提供します。
介護現場でもAIリテラシーが新たなスキル指標になりつつあります。
採用活動においても「デジタルに強い人材」「AI活用を学びたい人」に訴求できる点は大きな魅力。
社内研修や外部講座を活用し、介護×AIの基礎理解を持つ人材育成を進めていくことが重要です。
④ SOMPOホールディングスが新会社「SOMPOウェルビーイング」設立
SOMPOホールディングスは、介護・老後生活の無料相談や金融支援を一括提供する新会社「SOMPOウェルビーイング株式会社」を設立。
介護・保険・資産形成の各サービスを横断的にサポートし、企業向けの「介護と仕事の両立支援」サービスも展開します。
介護業界は今後、金融・保険など他業種との連携が不可避になります。
この動きは「総合生活支援ビジネス」への転換を示しており、人材面でも相談力・調整力を備えた新しい職種像が求められます。
施設経営者としても、地域包括ケアや金融機関との提携を検討する視点が欠かせません。
⑤ 広島「あかしあ大河」×広島市立大学|壁画で地域と介護をつなぐ
広島市南区の介護付有料老人ホーム「あかしあ大河」と広島市立大学芸術学部が、中庭の外壁に巨大な壁画を制作するアートプロジェクトを10月より開始。
入居者・地域住民・学生が協働し、廃棄塗料を再利用するサステナブルな試みとして注目されています。
このような地域連携プロジェクトは、施設ブランディングや採用広報にも直結します。
「地域とともにある職場」「文化・交流を重視する職場」という印象を与え、若年層や学生ボランティアの関心を高める効果が期待できます。
今後はクラウドファンディングや地域イベントとの連動も進む見込みで、地域共生の新モデルとして注目です。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年9月22日~9月28日の注目ニュース
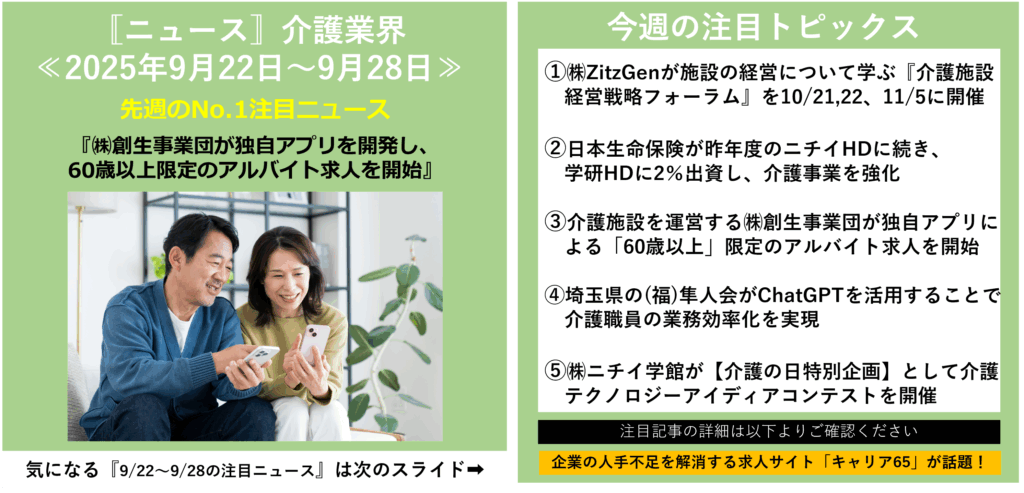
① 介護施設経営戦略フォーラム2025|経営改善と人材定着の成功事例
■ 記事の要約
2025年問題を目前に控え、介護業界では深刻な人材不足と経営環境の厳しさが浮き彫りになっています。厚生労働省の推計では、2025年には介護人材が約32万人不足するとされ、加えて最低賃金の引き上げ(全国平均1,100円超)や物価高騰によるコスト増、さらに2024年の介護事業者倒産件数が過去最多の172件に達するなど、事業運営の危機感が広がっています。こうした背景を受けて開催される「介護施設経営戦略フォーラム2025」では、実際に「儲かった・採用できた・定着した」という成功事例が共有され、売上確保・業務効率化・人材育成や評価制度の改善などの戦略が取り上げられます。現場の課題に即した実践的なノウハウを学べる点で注目を集めています。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の時代において重要なのは、単に「採用数を増やす」ことではなく「辞めない人材を育てる」ことです。賃金改善はもちろん、教育研修やキャリアパス、評価制度を通じて職員のモチベーションを高め、長期的な成長を支える仕組みが必要です。また、経営戦略と採用・人事施策は切り離せない関係にあるため、管理部門が経営層と一体となって事業方針を考えることも求められます。
■ 自分の事業所で検討できること
・報酬制度の見直し:最低賃金水準を超えた魅力的な給与体系を提示できるか検討する。
・教育研修プログラムの導入:新人から中堅まで、成長を後押しする体系的な研修を整える。
・キャリアパスと評価制度:働き続ける動機を与えるため、職員の成長段階を可視化し、評価と報酬を連動させる。
・経営の安定化戦略:集客や稼働率向上を通じた収益基盤の強化と、経営・人事の連携を意識する。
このような取り組みは、採用競争が激化する中で「働きやすい職場」を外部に発信する力となり、応募者への訴求力を高める効果も期待できます。
② 日本生命が学研HDに2%出資、介護事業強化狙う 2024年にはニチイHDを買収
■ 記事の要約
日本生命(日本生命保険相互会社)が、教育・出版企業である 学研ホールディングス(学研HD) に対し 2%の出資 を行う方針を発表したというニュースです。この出資は、同社が今後さらに 介護・ライフケア領域 に事業を拡大したいという意向を示すものとみられています。さらに、報道によれば、日本生命は 2024年に介護大手のニチイHDを買収 する計画も進めており、ニチイグループを傘下に置くことで介護・保険・生活支援のシナジーを追求しようとする戦略が透けます。この動きは、日本生命が保険事業のみならず、周辺領域(介護・福祉)への拡張を図る“ポートフォリオ拡大型”の構えとも解釈でき、業界にとって注目すべき M&A・資本提携の一例となります。
■ 人事担当者にとっての学び
・大手金融保険が介護に本気で参入する動きは、業界構造を大きく揺るがす可能性がある
→資本力を背景に、待遇改善、人材育成、制度整備などで競争優位に立てる余地を持つ企業がこれまで以上に強くなる可能性あり。
・シナジー重視の事業統合における人材マネジメントの重要性が増す
→保険営業網、顧客基盤、介護サービス網を融合させる際、異なる文化や制度を持つ組織をどう統合するかは人事部門にとって大きな課題。
・中小/地域系の介護事業者にも警鐘
→資本力やブランド力を持つ企業が業界に参入してくると、従来の競争環境が激化する。人材流出リスクや待遇格差への対応を急ぐ必要。
■ 自分の事業所で検討できること
・M&A/出資動向を常時ウォッチし、戦略上の脅威と機会を見極める
・自社の強み(地域密着、柔軟性、きめ細かさなど)を明文化し、採用メッセージに反映
・将来、大手企業との統合や提携の可能性を視野に入れ、組織制度をある程度標準化・見直し
・従業員キャリアパスを明確にし、給与/福利厚生/働き方面で「大手に負けない魅力」を打ち出す
・提携先候補(保険/医療/福祉系企業など)との連携を模索し、将来の統合に備える
③ 求人条件は「60歳以上」限定|介護業界で広がるスキマバイトの新潮流
■ 記事の要約
介護大手の創生事業団が、60歳以上の高齢者を対象にしたアルバイト求人を10月から開始する。募集職種は配膳・洗濯・清掃などの介護助手業務で、応募時に履歴書や面接は不要。勤務は1日数時間から可能で、報酬は即日払いに対応する。背景には、人材不足のなかで若年層やフルタイム人材の確保が難しくなり、短時間で働きたい高齢層をターゲットとする動きがある。首都圏を中心に展開される予定で、従来の「週数日・長時間勤務」が主流だった介護パート採用とは一線を画す試みだ。
■ 人事担当者にとっての学び
・高齢者層へのアプローチが新たな労働力確保につながる
→応募条件を「60歳以上」と限定することで、働く意欲はあるが従来の求人条件に合わなかった人材を掘り起こせる。
・応募ハードルを下げる工夫が効果的
→履歴書不要・即日払いなどの仕組みは「とりあえず試してみよう」と思わせる心理的障壁の低減につながる。
・柔軟性が差別化ポイントになる
→シフトや勤務形態を細かく調整できる職場は、他社と比べて選ばれやすくなる。
■ 自分の事業所で検討できること
・「高齢者限定/短時間枠」のアルバイト制度を試験的に導入する
・応募プロセスを簡素化し、スピード感を重視した採用フローを設計する
・即日払い/日払い制度の導入可否を検討し、応募者への魅力を高める
・業務を分解し、高齢者でも負担なく従事できるタスク(清掃/洗濯/配膳等)を切り出して配置する
・健康面に配慮した勤務設計(短時間・軽作業・休憩制度)を取り入れる
このような取り組みは、高齢者の「社会参加意欲」を活かしつつ、介護現場の慢性的な人手不足を補う実効性の高い手段となり得るでしょう。
④ AIで業務効率化と外国籍職員支援|埼玉・隼人会の挑戦
■ 記事の要約
埼玉県で介護施設を展開する社会福祉法人「隼人会」は、生成AIや専用システムを活用して業務効率化を進めている。具体的には、外国籍職員向けの書類翻訳、デイサービスの送迎ルート作成、日常的な事務作業をAIに代替させる取り組みを実施。職員数は600名規模で、外国籍スタッフは6か国56名にのぼる。これまでは翻訳や送迎計画に多大な時間を要していたが、AI導入により作業時間は大幅に短縮。さらに、送迎業務では「DRIVEBOSS」というAI搭載システムを導入し、計画作成時間を従来の3分の1に削減した。隼人会はAIを「負担軽減のための投資」と位置づけ、ケアプラン作成やICT連携への拡張も視野に入れている。
■ 人事担当者にとっての学び
・AI導入が人事/採用業務にも波及する
→日常的な雑務を効率化することで、管理部門が本来注力すべき採用・教育にリソースを振り分けやすくなる。
・多様な人材の受け入れを支える仕組み
→外国籍職員の比率が増えるなか、多言語対応をAIで補う発想は採用の幅を広げる有効策。
・導入の現場抵抗に配慮する姿勢
→利用を任意制にしたことは、現場の自主性を尊重しながら新技術を浸透させる好例。
・段階的拡張の重要性
→初期は翻訳や送迎など定型業務に限定し、徐々にケアプランやICT連携に広げる計画性は、他法人の参考になる。
■ 自分の事業所で検討できること
・書類作成や翻訳など定型業務にAIを試験導入し、効率化の効果を検証する
・外国籍人材を採用する場合は、多言語支援体制をシステム面から整える
・AI導入は「任意利用」から始め、現場の不安を軽減する
・送迎計画やシフト作成といった時間のかかる業務をシステム化する
・将来的には人事評価や教育研修支援へのAI活用を見据え、データ基盤を整備する
この事例は、単なる業務効率化にとどまらず、「多様な人材を受け入れる職場環境づくり」に直結するものであり、採用戦略にも大きな示唆を与えます。
⑤ 介護の日特別企画|介護テクノロジーアイディアコンテスト開催
■ 記事の要約
ニチイ学館は11月11日の「介護の日」に合わせて、介護現場で役立つテクノロジーアイディアを公募するコンテストを実施する。テーマは「介護をする際に便利なアイディア」で、応募資格は一般市民や家族、子どもまで広く対象とされている。入賞者にはギフトカードや同社サービスの割引特典が贈られる予定。介護人材不足の深刻化や現場職員の業務負担軽減を背景に、テクノロジーによる革新的な解決策を探る取り組みとして注目されている。現場の声を社会全体で共有し、未来の介護を支える新しい仕組みづくりにつなげる狙いがある。
■ 人事担当者にとっての学び
・人材不足は現場の負担軽減とセットで解決する必要がある
→採用を増やすだけでなく、日常業務を効率化する仕組みがあってこそ定着につながる。
・現場発のアイディアが改革の出発点になる
→従業員や家族の声を取り入れる姿勢は、エンゲージメントを高めると同時に、採用広報において「従業員を大切にする会社」というブランド形成につながる。
・テクノロジーの活用は人材戦略と直結する
→新しいシステムや機器導入は「働きやすさ」を訴求でき、応募者に魅力的な職場と映る。
■ 自分の事業所で検討できること
・現場職員や家族から「こうだったら助かる」という声を募る社内アイディアコンテストを実施する
・ICTやAIへの小規模投資を通じて、まずは事務業務や介護周辺業務の軽減を試みる
・提案制度を整え、従業員が安心して意見を出せる環境を整備する
・導入したアイディアや仕組みを採用広報に活用し、「働きやすさ」を対外的に発信する
こうした取り組みは、採用難が続く中で「選ばれる職場」への進化を後押しし、従業員の定着や企業ブランド強化に寄与します。
■過去のニュースはこちらから


