〚ニュース〛保育業界

□福祉人事.comのSNSでも注目ニュースを配信中!
Instagram / X(旧Twitter) / Facebook
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
このページでは、福祉業界の「保育分野」に関わるニュースを紹介していきます
■本ページのアジェンダ
・保育業界の週ごとの注目ニュース一覧
2026年2月16日~2月22日の注目ニュース
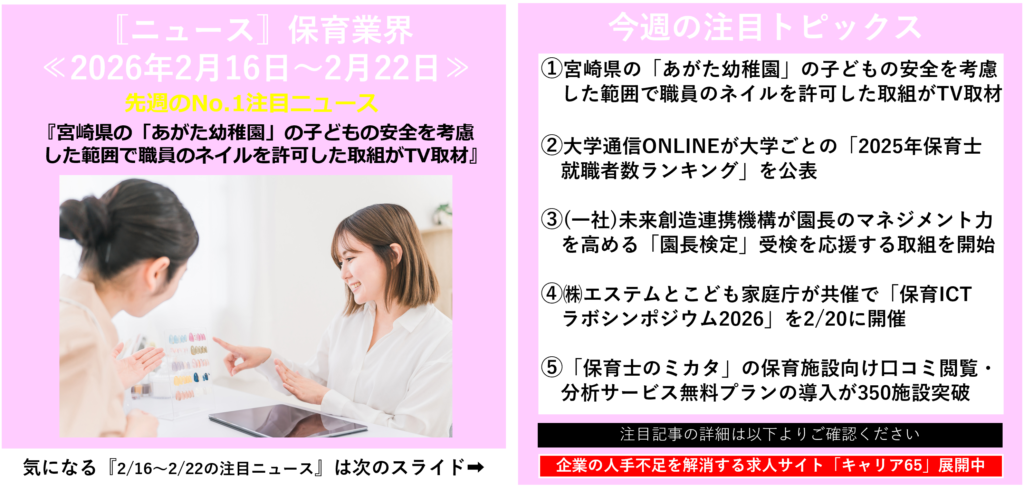
慢性的な人材不足、若手離職の増加、そして少子化。
保育業界の人事担当者にとって、採用は年々難易度を増しています。
「求人を出しても応募が来ない」
「採用しても定着しない」
「他園との差別化ができない」
こうした悩みを抱える中で、今週も保育業界では人事・採用に直結する重要なニュースが発表されました。
ICT導入による働きやすさ改革、大学ランキングから見る人材供給の動向、園長のマネジメント強化、口コミ可視化サービスの拡大など――
採用力を高めるヒントが、数多く含まれています。
本記事では、今週注目度の高い保育業界の人事・採用ニュース5選を、人事担当者視点で「学び」と「自園での活用策」に分解して解説します。
採用を“作業”から“戦略”へ。
次の一手を考える材料として、ぜひご活用ください。
① 働いていて幸せと思える職場に|AI導入とネイル許可でモチベーション向上
■ 記事の要約
宮崎県の保育現場で、AIカメラを活用した午睡チェックの自動化や、ネイル許可など職員の自己表現を尊重する取り組みが進んでいる事例が紹介されました。慢性的な人材不足が続く中、「働きやすさ」を軸にした現場改革が進行。さらに、潜在保育士の復職支援を行うセンターの活動により、ブランクのある人材のマッチング成功事例も生まれています。
保育士不足を“採用強化”だけでなく、“職場環境改善”で解決しようとする動きが明確に見えるニュースです。
■ 人事担当者にとっての学び
給与改善だけでは人材確保は難しい時代です。「業務負担軽減(AI・ICT)」と「心理的満足度(自己表現の尊重)」の両輪が、採用競争力を高める要素になっています。特に潜在保育士の復職支援は、即戦力確保の現実的な打ち手として有効です。
■ 自分の事業所で検討できること
・午睡チェックや記録業務のICT化検討
・身だしなみルールの見直し
・潜在保育士向けの柔軟な勤務制度設計
・復職説明会や見学会の開催
② 2025年保育士就職者数ランキング
■ 記事の要約
2025年春の保育士就職者数ランキングが発表されました。東京家政大学、聖徳大学、桜花学園大学などが上位に入り、実践的なキャリア支援や国家資格取得支援体制が充実している大学が多くの人材を輩出していることが明らかになりました。大学ごとの“輩出力”が可視化されたことで、採用活動のターゲット設計に具体的なヒントが得られます。
■ 人事担当者にとっての学び
大学との接点強化は、安定的な母集団形成につながります。ランキング上位校=人材輩出力の高い大学であり、合同説明会やインターン、OB訪問の強化は効果的です。
■ 自分の事業所で検討できること
・上位校への訪問や関係構築
・学生向け園見学ツアー企画
・奨学金返済支援制度の検討
・実習受け入れ体制の強化
③ 「園長検定」応援プロジェクト開始
■ 記事の要約
保育施設運営管理士(園長検定)の受検を、職員や保護者が匿名で応援できる仕組みがスタート。園長のマネジメント力や経営知識向上を目的とし、割引価格で講座受講が可能になります。園長の専門性強化が、組織の質向上・離職防止・採用力向上につながるという考え方が背景にあります。
■ 人事担当者にとっての学び
採用は“トップの質”に大きく左右されます。園長のマネジメント力向上は、職員満足度向上→口コミ改善→採用力強化という好循環を生みます。
■ 自分の事業所で検討できること
・管理職研修の体系化
・外部検定/資格取得支援
・園長評価制度の見直し
・マネジメント勉強会の実施
④ 保育ICTラボシンポジウム2026開催
■ 記事の要約
保育ICTラボシンポジウム2026が開催され、ICTやAIを活用した保育業務効率化の事例が共有されました。少子化時代に「選ばれる園」になるためには、保育の質と働きやすさの両立が重要であると示されています。
■ 人事担当者にとっての学び
ICT導入は単なる業務効率化ではなく、採用広報にも活用可能です。「ICT導入済み」「業務効率化推進園」という訴求は、若手世代にとって大きな魅力になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入状況の可視化
・求人票へのICT活用記載
・補助金活用の検討
・業務削減効果の数値化
⑤ 保育士のミカタ 導入350施設突破
■ 記事の要約
口コミ分析サービス「保育士のミカタ」の導入が350施設を突破。自園の口コミ確認や業界平均との比較が可能になり、職場改善や採用戦略立案に活用されています。“選ばれる園”になるためのデータ活用が加速しています。
■ 人事担当者にとっての学び
今や口コミは採用力に直結します。応募前に求職者が口コミを確認するのは一般的であり、放置はリスクです。
■ 自分の事業所で検討できること
・口コミモニタリング体制構築
・職員満足度アンケート実施
・改善内容の求人票反映
・広報戦略の見直し
今週のニュースを俯瞰すると、明確な共通点が見えてきます。
それは――
採用は求人広告だけで決まる時代ではないということです。
・ICT導入による業務負担軽減
・園長のマネジメント力強化
・大学との連携による母集団形成
・口コミの可視化と改善
・潜在保育士の掘り起こし
これらはすべて、「組織の魅力を高める取り組み」です。
特に人事担当者の役割は、単なる採用担当ではなく、“組織変革の推進者”へと変化しています。
今後の保育業界では、
✔ 働きやすさを数値で示せる園
✔ マネジメント力が高い園
✔ データで改善を続ける園
が、選ばれる存在になります。
もし今、採用に苦戦しているのであれば、求人原稿を見直す前に、
「自園は求職者からどう見えているか?」
「園長・管理職の魅力は言語化できているか?」
「業務効率化は進んでいるか?」
この3点を問い直すことが、次の成功への近道です。
採用は未来への投資。
今日の一歩が、3年後の組織力を決めます。
次回の採用戦略会議で、ぜひ今回のニュースを活かしてみてください。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年2月9日~2月15日の注目ニュース

人手不足が続く保育業界において、採用や人材定着のヒントは「現場の外」で起きている変化の中にあります。ITの進化、若年層への職業理解の促進、AIによる求人検索、業務効率化の取り組み、そして職員のメンタルケアまで──。今週も、人事・採用の視点から見逃せないニュースがいくつも発表されました。
本記事では、保育業界の人事担当者が押さえておきたい最新トピックを5つ厳選し、「何が起きているのか」だけでなく、「自園の採用や組織づくりにどう活かせるのか」という視点で解説します。現場改善のヒントや採用力強化の気づきとして、ぜひ参考にしてみてください。
① 【子育てIT】優れた育児IT商品コンテスト「BabyTech® Awards 2025-26」殿堂入り・大賞・優秀賞発表!
■ 記事の要約
育児IT商品の優れた取り組みを表彰する「BabyTech® Awards 2025-26」の受賞結果が発表され、殿堂入り・大賞・優秀賞を含め38商品が選出されました。ベビーテック市場は成熟期に入り、見守り・健康管理・教育支援など幅広い分野で高品質な商品が増えていることが特徴です。ITの進化により、保護者支援だけでなく保育現場の業務効率化や安全性向上にもつながる可能性が高まっています。
■ 人事担当者にとっての学び
保育業界にも本格的なDXの流れが来ていることが明確になりました。ITを活用する施設は、業務負担の軽減や働きやすさの向上につながり、求職者からも選ばれやすくなります。今後は「ITに抵抗がない人材」「新しい仕組みに適応できる人材」が重要な採用ポイントになっていきます。
■ 自分の事業所で検討できること
連絡帳のデジタル化、見守りシステム、保護者アプリの活用など、小さなDXから始めることで職員の負担を減らせます。「ICTを活用している園」という打ち出しは、採用時の差別化にもつながります。
② 保育の価値を次世代へ。中学校での職業講話レポートを公開
■ 記事の要約
保育専門の派遣会社が中学校で職業講話を実施し、保育の仕事のリアルや誇りを伝える取り組みのレポートが公開されました。進路選択前の中学生に対し、保育の社会的意義ややりがいを伝えることで、将来の職業としての認知を高める狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
採用は「募集する時だけの活動」ではなく、「未来の人材を育てる活動」へと変わっています。早い段階から職業の魅力を伝えることで、将来の母集団形成につながるという発想は非常に重要です。
■ 自分の事業所で検討できること
地域の学校との連携、職場見学の受け入れ、体験イベントなどを通じて保育の魅力を発信することで、中長期的な採用力の強化につながります。地域との関係づくりはブランディングにも有効です。
③ 【保育士の求人検索にAI時代到来】生成AIで求人を探す保育士、約半数が今後も積極活用
■ 記事の要約
保育士の求人探しに生成AIを活用する求職者が増えており、約半数が今後も積極的に使いたいと回答。AI検索時代に入り、求職者が情報収集する手段が大きく変わってきていることが明らかになりました。
■ 人事担当者にとっての学び
求人は「掲載すれば見つかる」時代から、「検索される情報設計」が必要な時代へと移行しています。AIに拾われる情報量や内容の質が、応募数に直結する可能性があります。
■ 自分の事業所で検討できること
仕事内容・職場環境・魅力を具体的に文章化し、情報量の多い求人を作ることが重要です。写真、1日の流れ、働くメリットなどを充実させることで、AI検索でも選ばれやすくなります。
④ 保育DXを加速──対話型音声AI SaaS「アイブリー」導入で業務負担と安全性の課題に挑む
■ 記事の要約
社会福祉法人ヒトトナリが対話型音声AI「アイブリー」を導入し、電話対応などの業務を効率化。職員が保育に集中できる環境づくりと安全性向上を目的にDXを推進しています。
■ 人事担当者にとっての学び
DXは単なる効率化ではなく、働きやすさ向上による離職防止や採用力強化につながります。「業務に集中できる環境」は求職者にとって大きな魅力になります。
■ 自分の事業所で検討できること
電話対応や事務作業など、保育以外の業務を減らす仕組みを検討することで、職員満足度の向上が期待できます。「負担を減らす取り組みをしている園」という発信は採用面でも効果的です。
⑤ 絆友会 × 国立あゆみ保育園 不適切保育防止・メンタルヘルス研修を実施
■ 記事の要約
社会福祉法人絆友会が、不適切保育の防止とメンタルヘルスをテーマにした研修を実施。地域に開かれた学びの場として約30名が参加し、保育の質と職員ケアの両面を重視した取り組みとなりました。
■ 人事担当者にとっての学び
保育の質を守ることと、職員の心身を守ることは採用・定着の両面で重要です。メンタルケアや教育体制が整っている職場は、安心して働ける環境として評価されます。
■ 自分の事業所で検討できること
定期的な研修や相談体制の整備、職員ケアの取り組みを強化することで、離職防止につながります。「人を大切にする園」というメッセージは採用ブランディングにも効果的です。
今回のニュースを振り返ると、保育業界の人材戦略は確実に次のステージへ進んでいることが分かります。ITやAIの活用による業務効率化、未来の人材を育てるための職業理解の促進、働きやすさを高めるDX、そして職員のメンタルケア。これらはすべて「人が集まり、長く働ける職場」をつくるための重要な要素です。
採用が難しい時代だからこそ、求人条件だけでなく、「どんな環境で働けるのか」「どんな組織なのか」を伝えることが大切になります。今回紹介した取り組みの中には、すぐに実践できるヒントも多く含まれています。小さな改善の積み重ねが、応募数や定着率の向上につながる第一歩になるはずです。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年2月2日~2月8日の注目ニュース
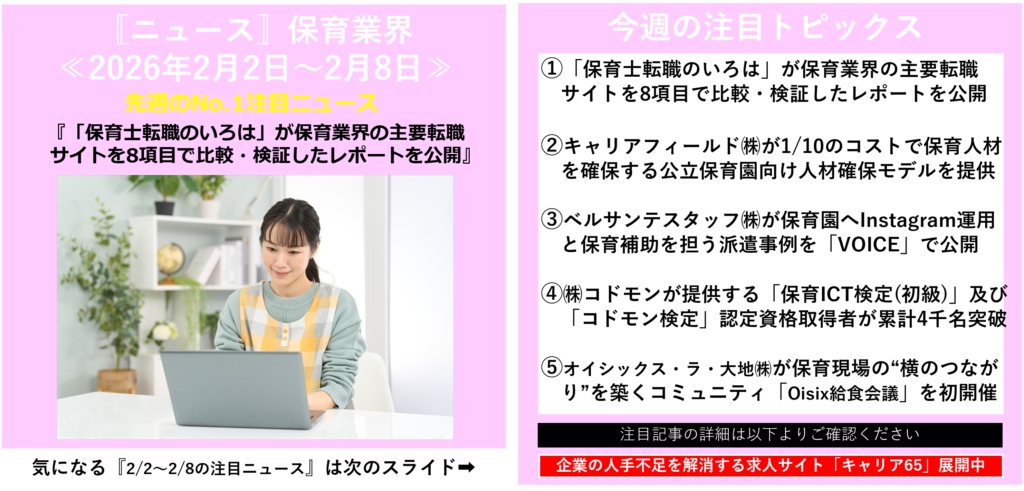
保育業界では今、人材不足・園児数減少・業務効率化・職員定着といった複数の課題が同時に進行しています。その中で、人事担当者に求められる役割はますます広がり、採用だけでなく育成・広報・働きやすい環境づくりまで視野に入れた取り組みが必要になっています。
そこで今回は、今週注目された「保育業界の人事・採用」に関する最新ニュースを5つ厳選し、それぞれを人事目線で解説します。
「他園はどんな取り組みをしているのか」「自園でも活かせるヒントはあるか」——そんな視点で読み進めていただくことで、明日からの採用活動や組織づくりのヒントが見えてくるはずです。
① 保育士の転職市場データ【2026年版】
■ 記事の要約
本記事では、2026年時点の保育士の転職市場に関する最新データが紹介されています。保育士の有効求人倍率は依然として高く、慢性的な人材不足が続いている状況が明確に示されています。特に年度末は退職や転職が増え、採用競争が激化しやすい時期であることも指摘されています。求職者側にとっては選択肢が多く、職場環境や待遇が重視される傾向が強まっていることから、従来の募集方法だけでは採用が難しくなっている現実が浮き彫りになっています。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースから読み取れる最大のポイントは、「採用難は構造的な問題であり、短期的な対策だけでは解決しない」という点です。求人数が多い状況では、給与や勤務条件だけでなく、職場の雰囲気や働きやすさ、教育体制などが採用の決め手になります。また、年度末に採用競争が激化するという事実は、採用活動のタイミング戦略が重要であることも示しています。人材不足を前提に、早期募集・通年採用・情報発信の継続といった複数の施策を組み合わせる必要性があるといえるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
まずは、自園の採用時期が遅くなっていないかを見直すことが重要です。年度末だけに頼るのではなく、年間を通じて求人を出し続ける体制づくりが有効です。また、求職者が比較する時代だからこそ、ホームページやSNSで職場の魅力を発信する取り組みも欠かせません。さらに、離職防止の視点も採用戦略の一部として捉え、既存職員の満足度向上に取り組むことが、結果的に採用成功につながります。
② 公立保育園向け人材確保モデルを提供開始(キャリアフィールド株式会社)
■ 記事の要約
キャリアフィールド株式会社が、公立保育園向けに新たな人材確保モデルの提供を開始したという発表です。従来の約1/10のコストで人材を確保できる仕組みとされ、会計年度任用職員の安定的な確保を目的とした「育成型採用」が特徴です。即戦力採用に頼るのではなく、未経験者や若手を育てながら人材を定着させていくアプローチが強調されています。予算が限られる公立園にとって、持続可能な採用の形として注目される取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースが示すのは、「即戦力の奪い合いから、育てる採用へ」という流れです。保育業界では経験者採用が中心になりがちですが、人材不足が続く中では採用コストも上昇します。そこで、未経験者やブランク人材を育成しながら戦力化するモデルは、長期的な人材確保の視点として非常に参考になります。また、採用コストを抑えるという観点からも、従来の求人媒体頼みの採用を見直すきっかけになるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
まず検討したいのは、「育成前提の採用枠」を設けることです。保育補助や短時間勤務からスタートし、段階的にスキルを身につけてもらう仕組みを作ることで、採用の間口を広げることができます。また、シニア人材や子育て経験者など、潜在的な人材層に目を向けるのも有効です。採用コストを抑えつつ人材を定着させるためには、教育体制の整備が重要なテーマになります。
③ 園児数減少に直面する保育園へ、PR人材を派遣(ベルサンテスタッフ株式会社
■ 記事の要約
園児数減少に悩む保育園に対し、保育補助とInstagram運用を兼任する人材を派遣する事例が紹介されています。派遣スタッフが日々の保育をサポートしながら、SNSを活用して園の魅力を発信することで、園児募集や認知向上につなげるという取り組みです。採用だけでなく、広報力を強化することで入園希望者を増やすという、新しい課題解決のアプローチとして注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースのポイントは、「採用の前に、園の魅力が伝わっているか」という視点です。人材不足だけでなく、園児数減少も経営に大きく影響します。SNS運用を通じて園の雰囲気や取り組みを発信することで、保護者だけでなく求職者へのアピールにもつながります。つまり、広報活動は園児募集だけでなく採用力強化にも直結する重要な施策といえるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
まずはInstagramなどのSNSを活用し、日常の保育の様子や行事の取り組みを発信することが考えられます。専任担当を置くのが難しい場合は、職員が持ち回りで更新する形でも十分効果があります。また、広報を「採用活動の一部」として捉え直すことで、求人応募の増加にもつながります。園の魅力を可視化する取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。
④ 「保育ICT検定(初級)」と「コドモン検定」認定者が4,000名突破
■ 記事の要約
株式会社コドモンが提供する「保育ICT検定(初級)」および「コドモン検定」の資格取得者が累計4,000名を突破したと発表されました。保育現場でのICT活用を推進する人材の育成が進んでおり、業務効率化やDX推進の担い手が増えていることが示されています。保育業界においても、デジタルスキルが重要な能力として位置づけられ始めている流れが見て取れます。
■ 人事担当者にとっての学び
ICT活用が進むことで、事務作業の負担軽減や情報共有の効率化が期待できます。人材不足が深刻な業界だからこそ、「人を増やす」だけでなく「業務を効率化する」視点が重要になります。また、ICTに強い人材がいることで、現場の働きやすさが向上し、離職防止にもつながる可能性があります。採用時にデジタルスキルを評価する流れが強まる可能性も考えられます。
■ 自分の事業所で検討できること
職員のICTスキル向上を目的とした研修導入や資格取得支援を検討する価値があります。また、ICTに強い人材を採用することで、業務改善のスピードが上がる可能性もあります。特に若手や異業種経験者の中にはデジタルに強い人材も多く、採用の新たな視点として注目できます。
⑤ 「Oisix給食会議」初開催 保育現場の横のつながりを促進
■ 記事の要約
保育施設向け給食サービス「すくすくOisix」が、保育現場同士の横のつながりをつくるコミュニティイベント「Oisix給食会議」を初開催しました。イベント満足度は5段階評価で4.6点、参加者全員が「また参加したい」と回答するなど、高い評価を得ています。情報交換や悩み共有ができる場を提供することで、現場の孤立感を減らし、課題解決につなげることを目的とした取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースが示しているのは、「横のつながり」が職員の安心感やモチベーションに影響するという点です。他園との情報交換や交流の機会があることで、現場の不安や悩みを共有でき、結果として離職防止につながる可能性があります。人材確保だけでなく、定着支援の観点でもコミュニティづくりは重要なテーマといえるでしょう。
■ 自分の事業所で検討できること
地域の保育園同士での勉強会や交流会を企画するなど、外部とのつながりを持つ機会を増やすことが考えられます。また、給食や保育内容などテーマを絞った情報交換会を実施することで、職員同士の学びの場にもなります。職員が孤立しない環境づくりは、働きやすさ向上や定着率改善にもつながる重要な施策です。
今週のニュースから見えてくる大きな流れは、次の5つです。
・人材不足は続き、採用競争は今後も激しい
・即戦力採用だけでなく「育成型採用」が広がっている
・SNSなどの広報が園児募集・採用の両方に影響する
・ICT活用が現場の負担軽減と人材定着の鍵になる
・他園とのつながりが職員の安心感やモチベーションを支える
つまり、これからの保育業界の人事は、「採る」だけでなく「育てる・伝える・支える」までが仕事になる時代だと言えます。
特に人材不足が深刻化する中では、
・採用コストを抑える工夫
・潜在人材の活用
・職場の魅力発信
・定着を意識した環境づくり
こうした取り組みを少しずつ積み重ねていくことが、結果として採用成功につながります。
今回紹介したニュースは、どれもすぐに取り入れられるヒントばかりです。自園の状況と照らし合わせながら、「まず一つだけ試してみる」という視点で活用してみてください。小さな改善の積み重ねが、強い組織づくりにつながっていきます。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月26日~2月1日の注目ニュース
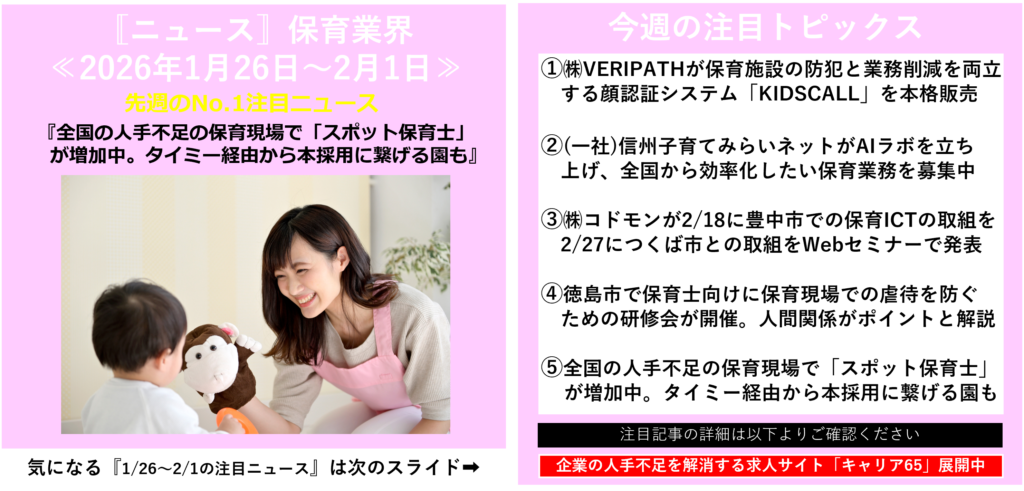
保育業界では今、人材不足の深刻化を背景に、「採用」だけでなく「定着」「職場環境改善」「ICT活用」まで含めた人事戦略が求められる時代に入っています。
単に人を集めるだけではなく、いかに働き続けられる職場をつくるかが、園運営の質を左右する重要なテーマとなっています。
そこで本記事では、今週の保育業界における人事・採用関連の注目ニュースを5本ピックアップし、人事担当者の視点で「何が学べるのか」「自園で何を検討できるのか」という切り口でわかりやすく解説します。
顔認証システムによる安全対策、AI活用による業務効率化、自治体主導のICT推進、不適切保育防止の取り組み、そしてスポット保育士活用まで、現場と経営の両面からヒントを得られる内容となっています。
① 保育園・幼稚園・こども園の「防犯」と「業務削減」を両立する、顔認証お迎えシステム「KIDSCALL」全国へ本格展開を開始
■ 記事の要約
兵庫県のスタートアップ企業が開発した、保育施設向け顔認証お迎えシステム「KIDSCALL(キッズコール)」が、2026年2月から全国展開を開始しました。本システムは、事前に登録された保護者の顔情報をもとに、入室時に自動認証・解錠を行う仕組みで、不審者の侵入防止と職員の業務負担軽減を同時に実現します。屋外設置にも対応した防水・高耐久設計で、既存の登降園管理システムとも連携可能な点が特徴です。これまで人の目に頼っていた入室管理をテクノロジーで補完することで、安全性と効率性の両立を目指しています。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースから読み取れるのは、「安全対策=人手で対応」という発想からの転換です。防犯業務は保育士の大きな負担となっており、本来の保育業務以外の緊張や責任を背負わせている側面があります。ICTによって安全管理を仕組み化できれば、職員の心理的負担を軽減し、結果として職場満足度や定着率の向上にもつながります。また、安全設備が整った園は、求職者や保護者からの信頼にも直結し、採用広報の強力な材料になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・登降園時の安全対策を「人依存」から「仕組み化」へ移行できないか
・防犯や見守り業務が現場の負担になっていないかの棚卸し
・ICT設備を「働きやすい職場環境」として採用広報に活用
・安全対策を福利厚生/職場環境改善の一部として位置づける
② 保育の仕事、子どもと向き合う時間を増やせるはず。保育現場の声を集める「みらいくAIラボ」始動
■ 記事の要約
長野県で複数の保育施設を運営する法人が、保育現場の業務効率化と質向上を目的に「みらいくAIラボ」を立ち上げました。連絡帳作成、引き継ぎ資料整理、日報作成など、保育士が日常的に行っている事務業務にAIを活用し、「子どもと向き合う時間を取り戻す」ことを目的としています。2026年4月からは全国の保育関係者も参加可能なオンラインラボとして展開予定で、現場主体の実証型プロジェクトとなっています。
■ 人事担当者にとっての学び
AI活用の本質は、単なる業務削減ではなく「人がやるべき仕事の再定義」です。保育士の専門性は、子どもの観察や関係構築にこそ価値があります。一方で事務業務が過重になると、疲弊や離職につながります。AIは人材不足を補うツールであると同時に、職場環境改善・定着率向上の戦略ツールでもあるという視点が重要です。
■ 自分の事業所で検討できること
・事務作業の中でAI化できる業務の洗い出し
・現場職員から「時間がかかっている業務」のヒアリング
・業務改善をトップダウンではなく現場参加型で設計
・AI導入を「働き方改革」「採用ブランディング」に位置づける
③ 自治体・保育施設向け保育ICT化ウェビナー(豊中市・つくば市)
豊中市 :https://newscast.jp/news/3307083
つくば市:https://www.atpress.ne.jp/news/6637973
■ 記事の要約
こども家庭庁と保育ICT企業が連携し、地域単位でのICT活用をテーマにした無料オンラインウェビナーが開催されます。茨城県つくば市では、ICT未導入園への支援施策や導入促進の工夫を紹介。大阪府豊中市では、保育AI活用やデータ活用による業務改善事例を共有します。両自治体とも、単なるツール導入ではなく「地域全体で保育の質と働きやすさを底上げする」モデルケースとして注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
この事例は、ICT化が「個別園の努力」ではなく「自治体レベルの政策」になりつつあることを示しています。人事担当者として重要なのは、自園だけで完結するのではなく、自治体の支援制度・補助金・研修と連動した人材戦略を描く視点です。ICT導入は採用力・定着率・業務効率を同時に改善できる構造改革施策といえます。
■ 自分の事業所で検討できること
・自治体主催のICT研修/補助制度の情報収集
・ICT未導入業務の可視化
・地域内他園との情報共有/共同導入検討
・ICTを人事戦略(採用/定着/育成)の柱に位置づける
④ 「不適切保育が起きる背景には…」保育士を対象に研修会【徳島】
■ 記事の要約
徳島市で、不適切保育や虐待を未然に防ぐための研修会が開催され、県内の保育士約130人が参加しました。専門家からは「不適切保育が起きる背景には、職場の人間関係や労働環境の悪化がある」という指摘があり、事故やトラブルが多い園ほど、職員間のコミュニケーション不全が見られる傾向があると説明されました。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースの本質は、不適切保育は「個人の問題」ではなく「組織の問題」であるという点です。過重労働、人間関係の悪化、相談できない環境が続くと、事故や虐待リスクが高まります。人事は採用だけでなく、「職場の空気づくり」「心理的安全性の確保」「管理職のマネジメント力」まで含めて責任領域です。
■ 自分の事業所で検討できること
・定期的な職員面談やストレスチェック
・管理職向けマネジメント研修
・人間関係トラブルの早期発見ルート整備
・事故防止を「予防型人事」のテーマとして設計
⑤ 広がる「スポット保育士」人材不足の現場で活躍中 でも保育の質は?
■ 記事の要約
人材不足を背景に、短時間・単発で働くスポット保育士の活用が広がっています。こども家庭庁の調査では、欠員補充として有効である一方、園児との関係構築の難しさや、園ごとのルール理解不足といった課題も指摘されました。自治体は、スポット保育士のみで配置基準を満たす運用には慎重な姿勢を示しています。
■ 人事担当者にとっての学び
スポット人材は「便利な補充要員」ではありますが、制度設計を誤ると現場の混乱や品質低下を招きます。重要なのは、スポット人材を「一時的戦力」ではなく「将来の採用候補」として位置づける視点です。育成・評価・登用ルートまで設計できて初めて、人材戦略として機能します。
■ 自分の事業所で検討できること
・スポット保育士の業務範囲の明確化
・初回勤務時のオリエンテーション整備
・優秀人材の常勤登用制度
・短期活用と中長期採用のバランス設計
今回紹介した5つのニュースに共通しているのは、保育業界の人事課題が「人が足りない」という単純な問題ではなく、「どう働ける環境をつくるか」「どう支える仕組みをつくるか」という構造的なテーマへと進化している点です。
安全対策のICT化、AIによる業務支援、自治体レベルでのICT推進、不適切保育の予防、スポット人材の制度設計――いずれも、採用と同時に「定着」「育成」「職場環境改善」を前提とした人事戦略が求められています。
これからの保育人事に必要なのは、
「人を集める力」だけでなく、
「人が辞めない職場をつくる力」、
そして「人が成長できる仕組みを設計する力」です。
ニュースを単なる情報として終わらせず、自園の人事戦略を見直すヒントとして活用することが、これからの保育経営における最大の価値になると言えるでしょう。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月19日~1月25日の注目ニュース

人材不足が慢性化する保育業界において、人事担当者にはこれまで以上に「情報収集力」と「戦略的な採用視点」が求められています。
単に求人を出すだけでは人が集まらず、制度変更・働き方改革・ICT活用・ブランディングなど、複数の視点を組み合わせた採用設計が不可欠な時代になりました。
本記事では、今週の保育業界における人事・採用関連ニュースの中から、特に注目度の高い5本をピックアップし、
「何が起きているのか」「人事担当者は何を学ぶべきか」「自園でどう活かせるか」 という実務目線でわかりやすく解説します。
① 満足度83%・参加者数300園の好評を受け第3弾 Googleマップ口コミ完全攻略セミナーをオンラインで開催
■ 記事の要約
株式会社アスカは、保育施設向けに「Googleマップ口コミ活用セミナー」第3弾を開催すると発表した。これまで300園以上が参加し、満足度83%という高評価を得た実績を持つオンラインセミナーである。
本セミナーでは、Googleマップ上での口コミ管理・返信方法、施設情報の見せ方、求職者・保護者双方に好印象を与える情報発信のコツなどを解説する内容となっている。近年、求職者は求人サイトだけでなく、Google検索やマップで園の評判を確認するケースが増えており、口コミは「採用広報の一部」として重要度が高まっている。
■ 人事担当者にとっての学び
これまで口コミは「保護者向け」と捉えられがちだったが、今後は明確に「採用チャネルの一部」として扱う必要がある。特に若手保育士は、応募前に必ず園名で検索し、口コミをチェックする傾向が強い。
採用力の高い園ほど、口コミ返信が丁寧で、ネガティブ評価にも誠実に対応している点が共通している。
■ 自分の事業所で検討できること
・Googleマップの口コミ返信を人事担当が定期チェック
・園の写真、説明文を採用目線で更新
・退職者や不満投稿への改善アクションを内部共有
② 自治体が注目する、“法人専門・保育士試験対策サポート”という新しい人材育成モデル
■ 記事の要約
キャリアフィールド株式会社は、自治体・保育法人向けに「法人専門・保育士試験対策サポートモデル」の説明会を開催すると発表した。このモデルは、未資格者や潜在保育人材に対して、法人が主体となって試験対策を支援し、合格後の就業まで一貫してサポートする仕組みである。
個人努力に任せていた従来型から、「育成前提の採用」へと発想を転換した点が特徴で、慢性的な人材不足に対する中長期的解決策として注目されている。
■ 人事担当者にとっての学び
即戦力採用が難しい時代において、「採ってから育てる」だけでなく、「育てながら採る」という考え方が重要になる。特に地域密着型法人では、地元人材の掘り起こしと育成が最も安定した採用戦略になり得る。
■ 自分の事業所で検討できること
・無資格補助員向けの資格取得支援制度
・自治体と連携した育成型採用
・合格後のキャリアパス提示
③「こども誰でも通園制度」に保育士の53.7%が不安と回答
■ 記事の要約
レバレジーズの調査によると、2026年度本格実施予定の「こども誰でも通園制度」について、保育士の53.7%が不安を感じていることが明らかになった。主な理由は「業務負担の増加」「安全管理への不安」「職員体制が追いつかない」などである。
制度自体は子育て支援として期待される一方、現場では受け入れ準備が不十分との声が多い。
■ 人事担当者にとっての学び
制度導入は「人手不足リスク」をさらに拡大させる可能性がある。制度対応を理由に離職が増えれば、採用コストはさらに上昇する。人事としては制度対応=業務設計・人員配置の見直しとセットで考える必要がある。
■ 自分の事業所で検討できること
・制度対応業務の棚卸し
・短時間、スポット人材の活用
・制度説明を含めた職員向け説明会
④ 県内保育関係者が集まり、埼玉県のICT活用の取り組みを共有
■ 記事の要約
保育ICT推進協会は、埼玉県内でICT活用事例の成果報告会を実施。出欠管理、連絡帳、記録業務などをICT化することで、事務負担を軽減し、保育士が「子どもと向き合う時間」を増やす効果が紹介された。
■ 人事担当者にとっての学び
ICTは単なる業務効率化ではなく、「働きやすさ」という採用ブランディング要素になる。若手人材ほどICT環境を重視する傾向があり、導入有無が応募数に影響する。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入状況を求人票に明記
・職員満足度アンケート実施
・導入補助金の活用
⑤ 園の73%が保育時間内に習い事、保護者の72%が園選びのポイントに
■ 記事の要約
千株式会社の調査では、約73%の保育園が保育時間内で習い事を実施しており、保護者の72%が「園選びの重要ポイント」と回答。英語、体操、リトミックなど多様化している。
■ 人事担当者にとっての学び
保育内容の魅力は、採用広報にも直結する。特色ある保育は「働く側の誇り」にもなり、定着率向上にも寄与する。
■ 自分の事業所で検討できること
・外部講師連携
・特色保育の言語化
・採用ページで保育方針を発信
今回の5本のニュースを通して見えてくるのは、保育業界の採用がすでに「人を探す時代」から「選ばれる園をつくる時代」へと完全に移行しているという事実です。
口コミやICTといったデジタル活用、育成型採用モデル、制度対応による業務設計の見直し、
さらには保育内容そのものをブランディングに活かす視点まで、人事の役割は“求人担当”から“経営戦略の一部”へと進化しています。
これからの人事担当者に求められるのは、
「採用活動=経営課題の解決手段」として捉え、
現場・制度・広報・育成を横断的に設計できる視点です。
日々のニュースを「ただの業界情報」で終わらせず、
自園の採用戦略にどう落とし込めるかという視点で読み解くことが、
これからの保育人事の成果を大きく左右していくでしょう。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月12日~1月18日の注目ニュース
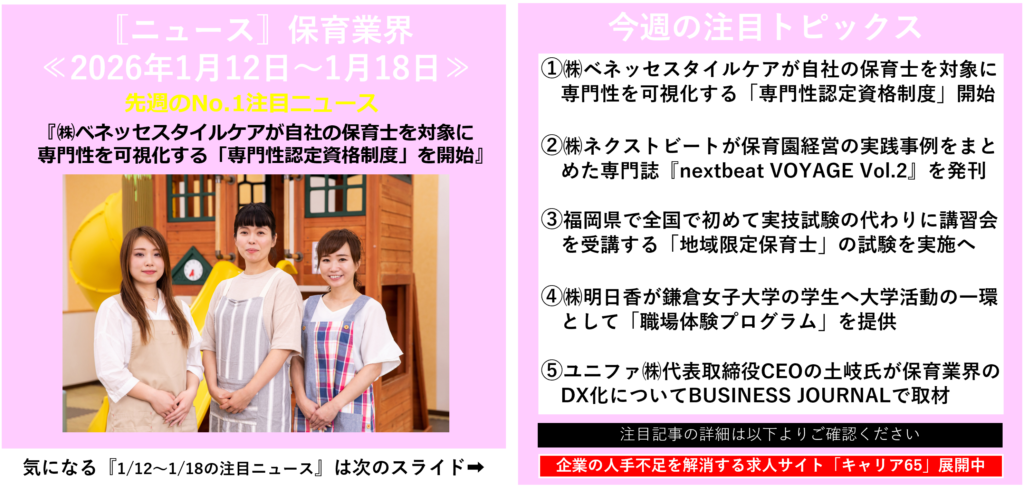
保育業界では、慢性的な人材不足が続く中で、採用や定着に向けた新しい取り組みが次々と生まれています。
「なかなか応募が来ない」「採用しても定着しない」と悩む人事担当者にとって、他社や自治体の最新事例は大きなヒントになります。
今週は、
・保育士の専門性を可視化する人事制度
・経営、人事の実践知をまとめた専門誌の発刊
・地域限定保育士という新しい資格制度
・学生との早期接点づくりによる採用強化
・DXによる働きやすさ改革
という、採用・育成・定着を一気通貫で考える上で重要な5つのニュースがそろいました。
本記事では、人事担当者の視点で「何を学び、どう自園に活かすか」をわかりやすく解説します。
① ベネッセ保育園、保育士の専門性を可視化する「専門性認定資格制度」を開始
■ 記事の要約
ベネッセスタイルケアは、保育士の専門性を可視化し、キャリア形成を支援するため「専門性認定資格制度」を2025年度から開始すると発表しました。本制度では、異年齢保育などの専門領域ごとに評価基準を設け、実地評価や実践レポートを通じて認定します。資格取得者は処遇面でも優遇され、スキル向上と定着率向上の両立を狙っています。保育の質を高めながら、人材育成と評価制度を連動させる先進的な取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
「頑張っても評価されない」をなくす仕組みづくりが、離職防止のカギになります。スキルを見える化し、評価・処遇と連動させることで、成長実感を持てる人事制度が実現できます。
■ 自分の事業所で検討できること
・保育の専門領域(乳児保育、異年齢保育など)を定義する
・スキル評価基準を作り、育成と評価を連動させる
・「資格」「認定」などの称号で成長を可視化する
② ネクストビート、保育業界向け専門誌で経営・人事の実践知識を共有
■ 記事の要約
ネクストビートは、保育園経営・人事・現場改善の実践事例をまとめた専門誌『nextbeat VOYAGE Vol.2』を発刊しました。ICT導入による業務効率化、働き方改革、職員定着の工夫など、現場課題に直結するテーマを網羅。成功事例や自治体・大学との連携事例も掲載され、保育業界の人事・経営者にとって実践的なヒントが詰まった内容です。
■ 人事担当者にとっての学び
「採用」だけでなく「定着」「育成」「働きやすさ」まで含めて設計することが、人材不足解消の本質だと分かります。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入による業務負担軽減の検討
・定着率向上のための職場改善プロジェクト
・他園事例を参考にした人事制度の見直し
③ 【全国初】福岡県、保育士不足解消へ「地域限定保育士」制度を導入
■ 記事の要約
福岡県は保育士不足対策として、地域限定で働ける「地域限定保育士」制度を導入します。実技試験を廃止し、筆記試験と講習で資格取得が可能に。まずは3年間福岡県内で勤務し、その後は全国で働ける仕組みです。資格取得のハードルを下げ、潜在保育士や未経験層の参入を促進する狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
「資格要件を満たす人材がいない」から「育てながら採用する」時代へシフトしています。
■ 自分の事業所で検討できること
・未経験者、潜在保育士向けの育成型採用
・資格取得支援制度の導入
・地域連携による人材育成モデル構築
④ 鎌倉女子大学で㈱明日香が保育学生向け職場体験プログラムを提供
■ 記事の要約
鎌倉女子大学では、保育学生が実際の保育・ベビーシッター現場で企画や運営を体験する職場体験プログラムを実施しました。学生は現場業務だけでなく、マーケティングや訪問支援も体験し、多様な働き方を学びました。教育と実務をつなぐ取り組みとして、採用前からの関係構築に成功しています。
■ 人事担当者にとっての学び
「採用は入社前から始まっている」。学生との早期接点づくりが、将来の採用力を左右します。
■ 自分の事業所で検討できること
・インターン、職場体験の受け入れ
・学校との連携プログラム構築
・採用前コミュニティづくり
⑤ ユニファ、保育DXで人材定着と業務改革を加速
■ 記事の要約
ユニファは、保育現場の業務負担を軽減する統合ICTプラットフォーム「ルクミー」を展開。AIによる安全管理や業務効率化で、保育士が本来の保育に集中できる環境を実現しています。DXを「人材定着戦略」として位置づける点が特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
DXは「システム導入」ではなく「働きやすさ改革」。採用競争力を高める人事戦略です。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入ロードマップの作成
・業務棚卸しとDX対象業務の明確化
・採用広報で「働きやすさ」を訴求
今週のニュースから見えてきたのは、「採用だけでは人は集まらない」時代に入ったという明確なメッセージです。
・スキルを可視化し、評価と処遇につなげる
・学生や未経験層と早期につながる
・DXで働きやすさをつくる
・育てながら採用する仕組みを整える
これらはすべて、人事が主導して設計できる領域です。
「人が集まらない」は環境のせいではなく、人が集まる仕組みをつくれていないだけかもしれません。
まずは、今日からできる小さな一歩(職場体験の受け入れ、評価制度の見直し、ICT導入検討など)から始めてみてください。
その積み重ねが、採用成功と定着率向上につながる強い組織をつくります。
なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2026年1月5日~1月11日の注目ニュース
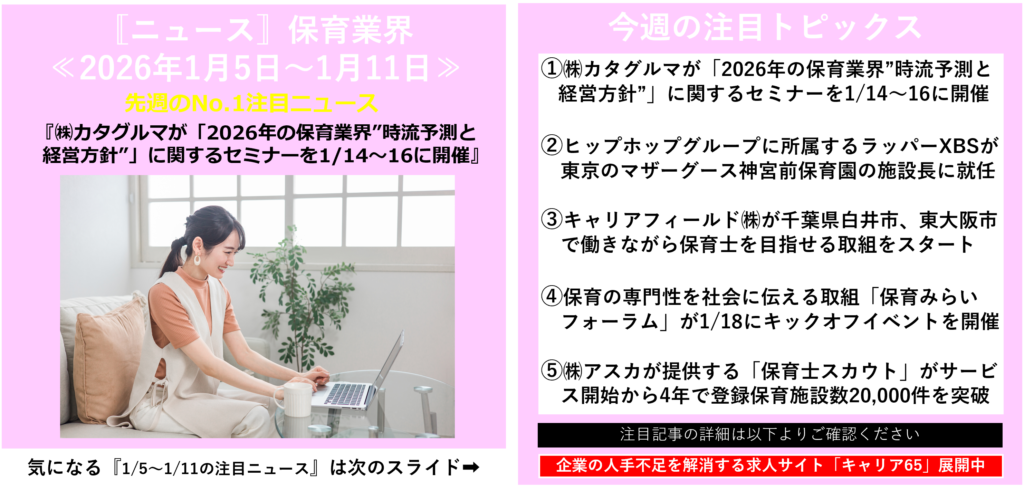
人手不足が慢性化する保育業界において、いま「人事」と「採用」は園経営の成否を分ける最重要テーマになっています。
保育士の確保が難しい、定着しない、応募が来ない──こうした課題は、もはや一部の園だけの問題ではありません。
その一方で、業界では
・異業種人材の参画
・育成型採用モデル
・スカウト型採用
・保育の専門性の可視化
といった、新しい人材戦略の動きも加速しています。
本記事では、今週の保育業界で注目度の高い人事・採用関連ニュースを5本厳選し、「なぜ重要なのか」「人事として何を学ぶべきか」「自園で何ができるか」という視点で解説します。
日々の採用に追われがちな人事・園長の皆さまが、「次の一手」を考えるヒントとしてお役立ていただければ幸いです。
① 経営者・園長限定!2026年の保育業界 時流予測と経営方針を解説する無料オンラインセミナー
📌 記事の要約
保育・教育・療育施設の経営者や園長を対象に、2026年度の保育業界の時流予測と経営方針をテーマにした無料オンラインセミナーが、1月14日〜16日に開催されます。少子化の進行、保育ニーズの減少、供給過多、人材不足という構造変化を背景に、今後の園経営に必要な視点や実践的な判断基準を解説する内容です。市場環境の変化と経営・採用戦略の関係について学べる貴重な機会となっています。
🔎 人事担当者にとっての学び
のセミナーの最大のポイントは、採用や人材配置に関する最新トレンドを俯瞰的に整理できる点です。保育ニーズの減少と供給過多という市場構造の中では、従来型の採用手法が通用しなくなる可能性が高まっています。「経営 × 人事」の両面から現場の課題を掘り下げ、自園にとって本当に必要な人材モデル・採用戦略を見直す視点が得られます。
💡 自分の事業所で検討できること
・来年度の採用計画を“質重視 × 市場変化対応”で組み直す
・保育ニーズの変化に合わせたポジション設計の見直し
・経営/人事が一体となった採用戦略会議の開催
・セミナー内容をベースにした社内勉強会の実施
② ラッパーXBS、保育園の園長になる(音楽ナタリー)
📌 記事の要約
ヒップホップグループ「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」のラッパー XBS が、東京・渋谷の マザーグース神宮前保育園 の施設長(園長)に就任することが発表されました。これは話題づくりのためではなく、研修を修了し、制度・現場対応力を備えたうえで就任する本格的なものです。文化・芸術と保育を結びつけ、子どもたちに多様な価値に触れる機会を提供する新しい教育モデルとして注目されています。
🔎 人事担当者にとっての学び
XBSの就任は単なる異業種人材の採用ではなく、施設運営・現場理解・制度対応力を前提にした“多様な人材ポートフォリオ”の導入という観点で価値があります。従来の保育士中心モデルを超え、文化人や多様な背景を持つ人材を採用することによって、園の価値観やブランディングを強化する可能性を示しています。
💡 自分の事業所で検討できること
・異業種人材を運営や人材育成に巻き込む役割設計
・園のブランド価値を高める多様な人材の関与/広報戦略
・転職者以外の地域人材との連携モデルの実装
・現場との意思疎通を重視した新たな評価/キャリアパス制度の構築
③ 「働きながら保育士を目指す」千葉県白井市で新しい取り組みがスタート
📌 記事の要約
千葉県白井市の保育施設において、保育補助として働きながら保育士資格取得を目指す制度が導入されました。この取り組みは、講座受講料の法人負担、勤務時間内での学習支援、合格後の正規職員登用など、実務と学びを両立できる仕組みが特徴です。人材不足が深刻な中、潜在的な人材の掘り起こしと育成につながる地域密着型モデルとして注目されています。
🔎 人事担当者にとっての学び
この取り組みは、育成型採用(Work & Learn モデル)の好例です。資格や経験がなくても、現場での実践経験と理論的学習を同時に進めることで、即戦力となる保育士を育てられる可能性を高めます。
採用市場で競争するだけでなく、自園独自の育成パイプラインを構築する視点が学べます。
💡 自分の事業所で検討できること
・保育補助〜保育士へのキャリアパス制度の整備
・教育支援費用の負担や学習時間の確保など支援制度の導入
・地域自治体との連携による人材育成協定の模索
・潜在保育士(資格未取得者)を積極的に採用する戦略設計
④ 「実習って、遊んでるだけでしょ?」その一言に保育学生らが挑む ― 保育みらいフォーラム
📌 記事の要約
学生主体で保育の実践知を社会に伝えるイベント 「保育みらいフォーラム」が2026年1月18日に長野県で開催されます。技能五輪金メダル指導者を迎え、保育の専門性や技能の評価方法を再考するプログラムや実践型コンテンツを実施。保育の“価値・技能・評価”を社会的に可視化する取り組みとして注目されています。
🔎 人事担当者にとっての学び
このフォーラムは、保育の専門性・技能を言語化し評価する新たな視点を提示しています。保育現場で求められる判断力や関係構築力は、定量化が難しいものでしたが、評価基準の議論が進むことで、採用・評価設計に新たな指標が出てくる可能性があります。
💡 自分の事業所で検討できること
・保育評価の仕組みを数値/言語化する試み
・面接/育成に活かせるスキル評価基準の策定
・現場教育と専門性育成をつなぐ研修制度の強化
・次世代人材育成に資する学生インターン受け入れ制度
⑤ 保育士スカウト、サービス開始から4年で登録保育施設数20,000件を突破
📌 記事の要約
株式会社アスカが運営する 保育士スカウト(スカウト型採用支援サービス)の登録施設数が 20,000件を突破しました。全国の多くの保育施設がこのサービスを活用しており、職場・人材の価値観マッチングによる採用成功率の向上に寄与しています。条件だけでなく、施設の特徴・方針を前面に出す採用戦略が評価されています。
🔎 人事担当者にとっての学び
このニュースが示すのは、従来の求人掲載だけではなく、採用マーケット全体を見据えた“スカウト・マッチング戦略” の有効性です。求職者は条件だけでなく、園の理念や方針との共感を重視する傾向があります。スカウト型サービスを活用したターゲティング採用は中長期的な人材確保につながります。
💡 自分の事業所で検討できること
・求職者の静的閲覧に頼らないスカウト戦略の導入
・求職者の価値観と園の理念をマッチングするPRページ強化
・求人媒体以外のSNS/メディア発信戦略の最適化
・データ分析を使ったターゲット人材像の策定
今回の5つのニュースを俯瞰すると、保育業界の人事・採用は明確に「量の確保」から「価値と構造の設計」へシフトしていることが分かります。
・経営視点での人材戦略(セミナー)
・異業種/文化人材の参画(XBS園長就任)
・働きながら育てる採用モデル(資格取得支援)
・専門性の見える化(保育みらいフォーラム)
・マッチング重視のスカウト採用(保育士スカウト)
これらはすべて、
「誰でもいいから人がほしい」
から
「どんな人が、この園に合うのか」
へと発想を切り替えることを求めています。
少子化が進むこれからの時代、採用力はそのまま“園の競争力”になります。
求人を出すだけでなく、
・園の価値観を言語化する
・人材の入り口と育成の仕組みを設計する
・異なる背景を持つ人が活躍できる組織をつくる
こうした人事戦略こそが、これからの保育園経営を支える最大の資産になるでしょう。
今週のニュースを、ぜひ「自園の人事をアップデートする材料」としてご活用ください。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月29日~1月4日の注目ニュース
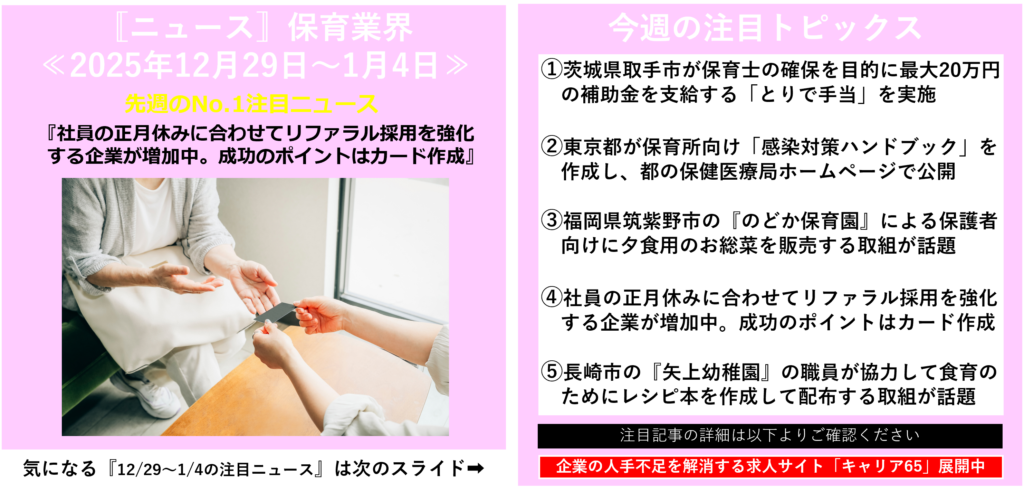
保育業界では今、人材不足が「慢性化」から「構造的課題」へと変わりつつあります。
採用が難しいだけでなく、定着・育成・働きやすさまで含めて考えなければ、組織が持続しない時代に入りました。
そんな中、各地の自治体や保育施設では、
・処遇改善に踏み込む制度づくり
・職員の安心感を高める環境整備
・園の価値観や魅力を“見える化”する工夫
など、人事・採用のヒントになる取り組みが次々と生まれています。
この記事では、今週注目された保育業界の人事・採用関連ニュース5本を取り上げ、人事担当者の視点で「何が学べるのか」「自園でどう活かせるのか」を整理して解説します。
日々の採用活動や職場づくりを見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
① 自治体が本気で保育人材を確保──取手市「最大20万円の手当」制度
■ 記事の要約
茨城県取手市では、保育士や保育関連職員の確保を目的に、最大20万円の補助金を支給する「とりで手当」を実施しています。
新規採用者だけでなく、一定年数勤務した職員への功労金も含まれており、「採用」と「定着」の両面を意識した制度設計が特徴です。自治体が人材不足を自分ごととして捉え、金銭的支援を明確に打ち出している点が注目されます。
■ 人事担当者にとっての学び
・保育人材確保は「園単体」ではなく、自治体も巻き込む時代
・処遇改善は給与だけでなく、補助金/手当の活用設計が重要
・採用広報で「自治体支援がある職場」であることを伝える価値が高い
■ 自事業所で検討できること
・自治体の補助金/手当制度を正確に把握し、採用情報に反映しているか
・「実質年収」「実質手取り」を応募者に分かりやすく伝えているか
・行政支援を含めた“安心して働ける職場像”を整理できているか
② 感染対策は人事課題──東京都の保育所向けハンドブック
■ 記事の要約
東京都は、乳幼児保育施設向けに感染症対策を体系的にまとめたハンドブックを作成しました。
感染発生時の初動対応、保護者対応、職員配置の考え方など、現場で「迷いやすいポイント」を整理した実務寄りの内容です。
職員の安全確保と業務負担軽減を両立するための指針として活用が期待されています。
■ 人事担当者にとっての学び
・感染対策は「現場任せ」ではなく、組織としての人事責任
・安全対策が整っているかどうかは、求職者が職場を選ぶ重要要素
・マニュアル整備は教育コスト削減/離職防止にもつながる
■ 自事業所で検討できること
・感染症対応ルールが属人化していないか
・新人/中途職員にも共有できる形になっているか
・「安心して働ける環境」を採用時に説明できているか
③ 保育園が総菜販売に挑戦──職員負担軽減という発想
■ 記事の要約
福岡の保育園では、共働き家庭を支援するため、金曜日に夕食用の手づくり総菜を販売する取り組みを始めました。
一見サービス施策に見えますが、背景には「保護者の負担軽減」だけでなく、「現場の業務設計を見直す」という視点があります。
■ 人事担当者にとっての学び
・人手不足対策は「人を増やす」以外にも選択肢がある
・業務の付加価値化は、職員のやりがいや誇りにつながる
・園の取り組みが“話題性”を持つと、採用広報にも好影響
■ 自事業所で検討できること
・現場の工夫や独自施策を、外部に発信できているか
・職員の負担が増える設計になっていないか
・「この園ならでは」の取り組みを言語化できているか
④ 正月休みに動く採用──リファラル採用の再評価
■ 記事の要約
年末年始の帰省シーズンをきっかけに、社員紹介(リファラル)による採用活動が活発化していることが紹介されています。
人材紹介会社に頼らず、信頼関係をベースにした採用手法として、コスト面・定着率の両面で注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
・採用チャネルは「求人広告だけ」では足りない
・既存職員が職場をどう語っているかが、採用成果に直結
・リファラルは“制度”よりも“文化づくり”が重要
■ 自事業所で検討できること
・職員が人に勧めたくなる職場になっているか
・紹介しやすい仕組み/メッセージが整っているか
・紹介=負担にならない配慮ができているか
⑤ 子ども目線のレシピ本が示す「共感で人が集まる園」
■ 記事の要約
長崎市の矢上幼稚園では、補食レシピをまとめた「子ども目線のレシピ本」制作に取り組んでいます。
管理栄養士、フードコーディネーター、写真家など外部専門家と協働し、「食べる楽しさ」や「自分らしさ」を表現するプロジェクトです。
■ 人事担当者にとっての学び
・園の価値観を“形”にすると、共感型採用につながる
・管理栄養士や調理スタッフも含めたチーム価値の可視化
・「ここで働く意味」を語れることが、定着率向上に直結
■ 自事業所で検討できること
・園の想いや強みを、外に伝えられているか
・職員の専門性を活かす場を用意できているか
・採用広報で“ストーリー”を語れているか
今週のニュースから見えてくるのは、「人が足りないから採る」ではなく、「人が働き続けたくなる環境をどうつくるか」という視点の重要性です。
自治体による手当制度、感染対策の仕組み化、現場発の新しい取り組み、
そして園の価値観を物語として伝える工夫――
いずれも共通しているのは、人事を経営課題として捉えている点にあります。
保育人材の確保に正解はありません。
しかし、
・働く意味が伝わる
・安心して働ける
・誇りを持てる
この3つが揃った職場には、少しずつでも人が集まり、定着していきます。
ぜひ今回のニュースをヒントに、「自園なら何ができるか」「何を伝えられるか」を改めて考えてみてください。
人事の一工夫が、園の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月22日~12月28日の注目ニュース
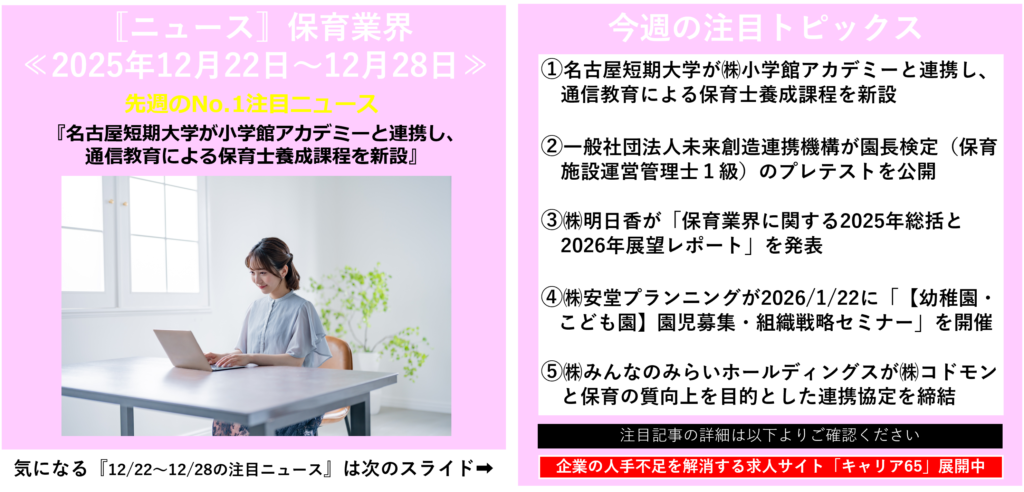
人手不足が慢性化する保育業界において、「採用できない」「定着しない」という悩みは、もはや一部の事業所だけの問題ではありません。
少子化が進む一方で、制度改正や保育ニーズの多様化により、人材に求められる役割やスキルはむしろ高度化しています。
今週の保育業界ニュースを見ると、単なる採用ノウハウではなく、
・人材育成の入口をどう広げるか
・管理職 / 園長人材をどう育てるか
・ICTや外部連携をどう人事戦略に組み込むか
といった、中長期視点の人事戦略が各所で動き始めていることが分かります。
本記事では、今週注目された保育業界の人事・採用関連ニュースを5本ピックアップし、人事担当者の視点で「学び」と「自園で検討できるポイント」を整理して解説します。
① 保育士不足の突破口に?短大×民間企業が挑む「通信教育」という新しい養成モデル
■ 記事の要約
保育士不足が深刻化する中、愛知県の名古屋短期大学が、東京の保育サービス企業である 小学館アカデミー と連携し、通信教育による保育士養成課程を新設しました。背景には、保育士養成校そのものが定員割れに直面しているという構造的な問題があります。今回の取り組みでは、社会人や子育て中の人でも「働きながら資格取得」が可能となり、従来取り込めていなかった層へのアプローチが期待されています。人材不足と教育機関の経営難、双方の課題を同時に解決しようとする試みです。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースからの最大の学びは、「採用」だけでなく育成の入り口を広げる視点の重要性です。現場経験者・潜在保育人材・異業種人材など、これまで採用対象になりにくかった層も、育成前提であれば戦力化できる可能性があります。また、教育機関や民間企業との連携は、単独では難しい人材確保を補完する有効な手段であることを示しています。
■ 自分の事業所で検討できること
自園単独で養成機能を持つのは難しくても、
・通信制 / 夜間制の養成校情報を採用広報に明示する
・「資格取得支援あり」を前提とした採用枠を設ける
・実習 / アルバイト受け入れから採用につなげる
といった形で、育成型採用を取り入れる余地は十分にあります。人材不足時代だからこそ、「今すぐ即戦力」に限定しない発想が重要です。
② 園長検定スペシャリスト誕生が示す、保育現場に求められるマネジメント力
■ 記事の要約
保育施設の運営力・マネジメント力を可視化する「園長検定スペシャリスト」の初回試験が実施され、合格者が誕生しました。同時に、誰でも挑戦できるプレテストも公開されています。これまで属人的になりがちだった園長・管理職の力量を、一定の基準で評価・学習できる仕組みが整いつつあります。
■ 人事担当者にとっての学び
人材不足の中で重要なのは、「現場を回せる管理職」をどう育てるかです。今回の検定は、保育スキルだけでなく、人材育成・労務・組織運営といった観点を重視している点が特徴です。評価軸を明確にすることで、管理職候補の育成計画やキャリアパス設計にも活用できます。
■ 自分の事業所で検討できること
・園長 / 主任向けに外部検定や研修を推奨する
・管理職要件を「経験年数」だけでなくスキル基準で整理する
・将来の園長候補を早期に見つけ、育成計画を立てる
といった形で、管理職育成を属人化させない仕組みづくりが検討できます。
③ 少子化でも人材不足は続く?2025年総括レポートから見る保育人事の論点
■ 記事の要約
本レポートでは、2025年の保育業界を総括し、2026年に向けた展望が示されています。少子化が進む一方で、保育士不足は依然として解消されていません。背景には、誰でも通園制度の拡充や多様な保育ニーズへの対応があり、保育の「量」と「質」の両立が求められています。
■ 人事担当者にとっての学び
重要なのは、「子どもが減る=人が余る」ではないという点です。むしろ制度拡充により、人材需要は質的に高度化しています。今後は、配置の柔軟性や多様な働き方を前提にした人事設計が不可欠になります。
■ 自分の事業所で検討できること
・フルタイム前提ではない勤務設計
・シニア / 子育て経験者など多様な人材活用
・業務分解による保育士負担の軽減
など、人材の使い方を見直す視点が求められます。
④ 定員割れは人事の問題?幼稚園・こども園向けセミナーが示す本質
■ 記事の要約
幼稚園・こども園の定員割れに対し、教育内容だけでなく「組織の在り方」や「発信力」に注目したセミナーが開催されます。内部の組織力と外部評価を同時に高めることで、選ばれる園づくりを目指す内容です。
■ 人事担当者にとっての学び
定員割れは集客の問題であると同時に、人材定着・職場環境の問題でもあります。働く人が誇りを持てる組織づくりが、結果として採用・広報力にも直結する点が示唆されています。
■ 自分の事業所で検討できること
・職員満足度の可視化
・園の理念や強みの言語化
・採用広報と内部施策の連動
といった、人事と経営をつなぐ取り組みが検討できます。
⑤ ICT×研修で保育の質を底上げへ―コドモンとみんなのみらいHDの連携
■ 記事の要約
保育ICTを提供する コドモン と、みんなのみらいホールディングスが連携協定を締結。保育者向けの専用学習サイトや研修プログラムを構築し、全国の施設で継続的な人材育成を進める取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
ICTは業務効率化だけでなく、人材育成インフラにもなり得ることがポイントです。属人的なOJTに頼らず、学びの機会を平準化することで、離職防止やスキル底上げにつながります。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICTツールを研修 / 評価と連動させる
・学びを「個人任せ」にしない仕組みづくり
・成長実感を可視化する評価制度
といった、人材定着を意識したICT活用が検討できます。
今週のニュースを通して見えてきたのは、「採用が難しい時代だからこそ、人事の役割が広がっている」という事実です。
即戦力を待つだけの採用から、
・育成を前提とした採用
・管理職 / 園長の計画的な育成
・ICTや外部パートナーを活用した人材基盤づくり
へと、人事戦略そのものがアップデートされつつあります。
人材不足は短期的に解消できる課題ではありません。
だからこそ、今できる小さな見直し――
「採用条件を少し緩める」「学びの仕組みを整える」「人が育つ環境を言語化する」
こうした積み重ねが、数年後の組織力を大きく左右します。
ぜひ今回のニュースを、自事業所の人事・採用を見直すヒント集として活用してみてください。
ら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月15日~12月21日の注目ニュース
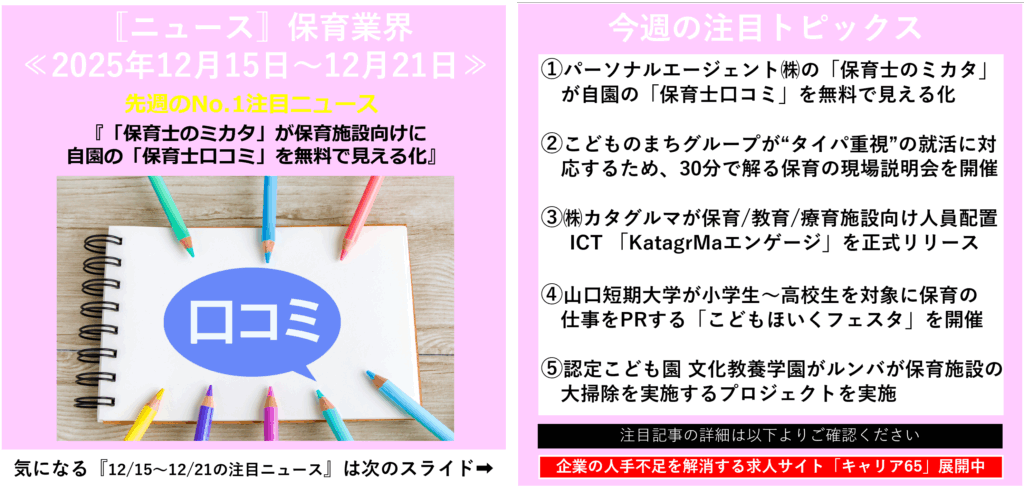
人材不足が慢性化する保育業界では、いま 「採る」だけでなく「辞めさせない」「現場を支える」人事施策 がこれまで以上に求められています。
今週も、保育士の口コミ可視化、短時間型の採用説明会、人員配置のICT化、仕事理解を深める体験イベント、そして業務負担軽減の取り組みなど、採用・定着・働きやすさを軸とした人事関連ニュースが相次ぎました。
本記事では、保育業界の人事・採用担当者が押さえておきたい 今週の注目ニュース5本を取り上げ、
・何が起きているのか
・人事として何を学べるのか
・自事業所でどう活かせるのか
という視点で、実務に役立つ形で解説します。
「すぐに取り入れられるヒント」を見つけるための、週次インプットとしてご活用ください。
① 保育士口コミを“見える化”する無料サービスが登場 ― 現場の声を採用・定着に活かす新たな一手
■ 記事の要約
保育士向け口コミサービス「保育士のミカタ」が、保育施設運営法人向けに無料プランの提供を開始しました。保育士が感じている職場環境・人間関係・業務負担などのリアルな声を可視化し、園運営の改善につなげることを目的としています。2026年度以降の「子ども誰でも通園制度」本格化を見据え、保育現場の受け入れ体制整備が急務となる中、現場理解を深める新しい手段として注目されています。
■ 人事担当者にとっての学び
・離職理由は「待遇」だけでなく人間関係・業務の不透明さにある
・採用広報と実態にギャップがあると、早期離職につながりやすい
・口コミは“ネガティブ対策”ではなく改善のヒントの宝庫
■ 自分の事業所で検討できること
・口コミを「怖いもの」とせず、改善テーマ抽出ツールとして活用
・園長/主任だけでなく、人事が横断的に現場を把握する仕組みづくり
・採用ページや説明会で「改善に取り組んでいる姿勢」を言語化
② 30分で伝える「保育の現場」オンライン説明会 ― 忙しい求職者に届く、新しい採用導線
■ 記事の要約
こどものまち株式会社は、就職・転職を検討する人向けに30分で保育の現場を理解できるオンライン説明会を実施しています。短時間・オンライン形式とすることで、在職中の保育士や学生でも参加しやすく、業界理解を促進する取り組みです。
■ 人事担当者にとっての学び
・求職者は「長時間説明会」を負担に感じている
・情報量よりも参加ハードルの低さが応募数を左右する
・事前に業界理解が進むことで、ミスマッチ採用を防げる
■ 自分の事業所で検討できること
・施設独自の「30分説明会」や動画コンテンツの作成
・求人票では伝えきれない1日の流れ/人間関係を簡潔に発信
・応募前の不安解消を目的としたライトな接点づくり
③ 人員配置を最適化するICTサービス「KatagrMaエンゲージ」 ― 配置・加算・希望管理を一元化
■ 記事の要約
株式会社カタグルマは、保育・教育・療育施設向けに人員配置支援ICTサービス「KatagrMaエンゲージ」を正式リリースしました。職員の希望や面談履歴、法定配置基準、加配要件などを一元管理し、複数園をまたいだ配置検討も可能です。
■ 人事担当者にとっての学び
・人員配置は「現場任せ」では限界がある
・加算の取りこぼしは人事の見える化不足が原因
・データ化により属人化を防げる
■ 自分の事業所で検討できること
・Excel管理からの脱却、配置業務の標準化
・職員の希望を踏まえた納得感ある配置設計
・中長期の人員計画を見据えた人事DXの第一歩
④ 保育の魅力を体感で伝える「こどもほいくフェスタ」 ― 仕事理解が採用につながる
■ 記事の要約
保育の仕事に興味を持つ人を対象に、「こどもほいくフェスタ」が開催されました。実際の保育体験や現場との交流を通じて、保育のやりがいや魅力を直感的に伝えるイベントです。
■ 人事担当者にとっての学び
・説明よりも「体験」が志望度を高める
・保育の魅力は文章だけでは伝わりにくい
・業界全体で入口を広げる取り組みが重要
■ 自分の事業所で検討できること
・職場体験/見学会の積極的な実施
・地域イベント/合同説明会への参加
・「まず知ってもらう」ための接点設計
■ 記事の要約
アイロボットジャパンは、保育施設を対象に「ルンバのお助け大掃除プロジェクト」第3弾を実施。清掃業務の負担軽減を通じて、保育士が本来の業務に集中できる環境づくりを支援します。
■ 人事担当者にとっての学び
・離職理由は「忙しさ」より雑務の多さ
・福利厚生=給与だけではない
・環境改善は採用広報にも使える
■ 自分の事業所で検討できること
・清掃/洗濯など周辺業務の見直し
・外部サービス/機器導入の検討
・「働きやすさ」を言語化し、求人に反映
今週の保育業界ニュースを俯瞰すると、共通して見えてくるのは、「人を増やす」よりも「現場を理解し、支える」方向へのシフトです。
・保育士の口コミを通じて、現場の声を可視化する動き
・短時間/オンラインなど、応募者視点に立った採用導線の工夫
・ICTを活用した人員配置/加算管理の効率化
・体験型イベントによる仕事理解の促進
・清掃など周辺業務の負担を減らす環境整備
これらはすべて、人事が現場とどう向き合うかを問い直す取り組みと言えます。
採用難の時代だからこそ、
「なぜ辞めるのか」「どうすれば働き続けられるのか」を構造的に捉え、
小さくても確実な改善を積み重ねることが、結果的に採用成功と定着率向上につながります。
今週のニュースをきっかけに、自事業所の人事施策を一段アップデートするヒントとして、ぜひ現場での検討につなげてみてください。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
2025年12月8日~12月14日の注目ニュース
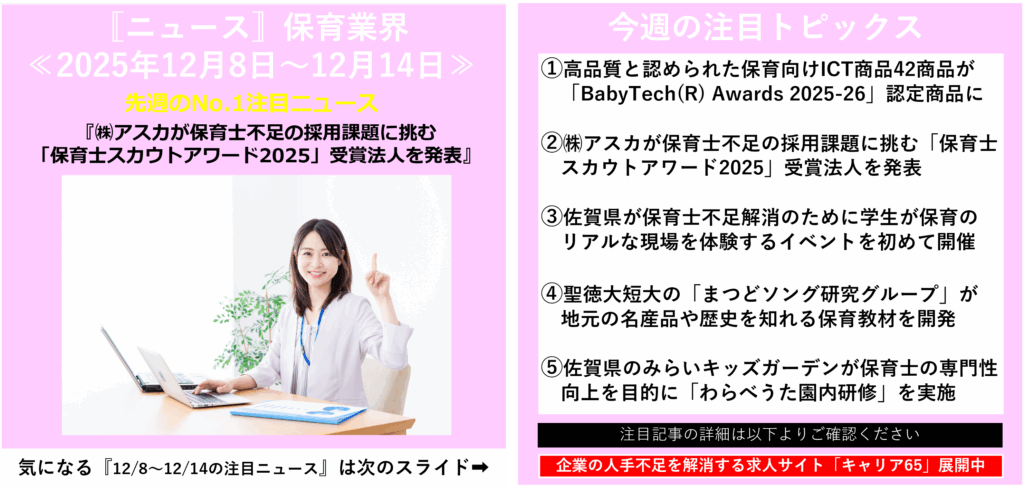
保育業界では慢性的な人材不足が続く中、「どう採用するか」「どう定着させるか」 が経営・人事の最重要テーマになっています。
従来の求人掲載や紹介会社頼みの採用だけでは限界を感じている人事担当者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、今週、保育業界の人事・採用領域で特に注目度が高かったニュースを5本厳選し、
・何が起きているのか
・人事担当者として何を学ぶべきか
・自園/自事業所で何を検討できるのか
という視点で、実務に直結する形で解説します。
「情報収集で終わらせない」「明日からの人事施策につなげる」ためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
① BabyTech® Awards 2025-26|保育・育児ICT42商品が認定
■ 記事の要約
BabyTech® Awards 2025-26では、妊娠・出産・育児・保育分野のICT商品42点が認定されました。今回は「発達支援ツール部門」「社会的インパクト部門」などが新設され、保育現場の業務効率化だけでなく、保育の質向上や職員の負担軽減を目的としたサービスが多く選ばれています。連絡帳・シフト管理・保護者対応など、日常業務を支えるデジタルツールの進化が明確に示された形です。
■ 人事担当者にとっての学び
保育士不足が続く中、「人を増やす」だけでなく「業務を軽くする」発想が不可欠であることを示すニュースです。ICT導入は離職防止・定着率向上にも直結し、人事施策の一部として位置づける重要性が高まっています。
■ 自分の事業所で検討できること
・現場職員の業務負担が大きい業務の洗い出し
・既存システムの見直し、ICT導入の優先順位整理
・採用広報で「ICT活用園」である点を訴求
② 保育士スカウトアワード2025|採用成功法人に学ぶ
■ 記事の要約
「保育士スカウトアワード2025」では、スカウト型採用を活用し、採用数・定着率の向上に成功した法人が表彰されました。求人を出して待つのではなく、園の魅力や働き方を直接伝えることで、ミスマッチを減らす手法が評価されています。
■ 人事担当者にとっての学び
採用難の時代において、「応募数」よりも「納得感のある出会い」を重視する考え方が重要です。人事主導でメッセージを設計する採用は、結果的に離職リスクも下げます。
■ 自分の事業所で検討できること
・園の強みを言語化したスカウト文面作成
・人事と現場が連携した採用ストーリー整理
・紹介会社依存からの脱却検討
③ 佐賀県|学生向け保育現場体験・相談会
■ 記事の要約
佐賀県で開催された学生向けの保育現場体験・悩み相談会では、現役保育士と学生が直接交流しました。実体験を通じて仕事理解を深め、就職への不安を解消する狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
早期接点づくりは採用競争力の源泉です。就職直前だけでなく、学生段階からの関係構築が将来の採用を安定させます。
■ 自分の事業所で検討できること
・職場見学や体験型イベントの実施
・学生向け説明会への積極参加
・現場職員を巻き込んだ育成意識づくり
④ 産経新聞掲載|保育科学生の実践活動
■ 記事の要約
短大保育科の学生が、実践的な教材や活動を通じて地域と関わる様子が紹介されました。学内だけでなく、社会と接続した学びが保育士としての意欲向上につながっています。
■ 人事担当者にとっての学び
「育成前提」で人材を見る視点が重要です。即戦力だけでなく、伸びしろのある人材を受け入れる土壌が採用成功につながります。
■ 自分の事業所で検討できること
・教育機関との連携強化
・実習受け入れ体制の見直し
・若手育成を評価制度に組み込む
⑤ みらいキッズガーデン|保育士研修の取り組み
■ 記事の要約
みらいキッズガーデンでは、わらべうたを活用した発達支援研修など、継続的な保育士研修を実施しています。外部研修と現場実践を組み合わせ、学び続けられる環境づくりが特徴です。
■ 人事担当者にとっての学び
「育てる園」であることは最大の採用ブランディングです。研修制度はコストではなく、定着率向上への投資と捉える必要があります。
■ 自分の事業所で検討できること
・年間研修計画の整備
・外部研修の戦略的活用
・成長実感を可視化する仕組みづくり
今週の保育業界ニュースを通じて見えてきたのは、
「人を集める」から「選ばれ続ける園・事業所になる」 への明確なシフトです。
・ICT活用による業務負担軽減
・スカウト型採用によるミスマッチ防止
・学生段階からの関係づくり
・育成/研修を前提とした人材戦略
これらはすべて単発の施策ではなく、中長期的な人事戦略として設計することが求められています。
人材不足は一朝一夕に解決できる問題ではありません。
しかし、今回紹介した事例のように、小さな取り組みの積み重ねが、採用力・定着率・組織力を確実に高めていきます。
まずは、
・自園の採用方法は「待ち」の姿勢になっていないか
・職員が「ここで成長できる」と感じられる環境があるか
を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年12月1日~12月7日の注目ニュース
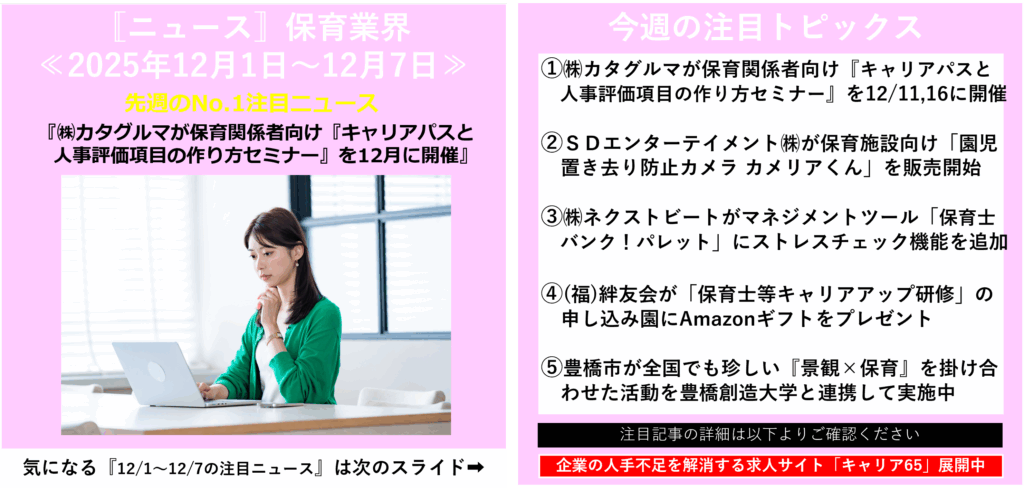
保育業界では、採用難と離職増加が同時に進行するなか、「採用して終わり」ではなく「採用・育成・定着」を一体として捉える動きが加速しています。
制度改正、ICT、安全対策、評価制度、研修制度、大学連携——
今週のニュースから見えてくるのは、現場の課題に対して 行政・企業・教育機関が連携し、人材確保や育成の仕組みをアップデートする流れが本格化しているということです。
特に、人事評価・キャリア形成・安全管理・メンタルヘルスケアなど、“働きやすさの構造をつくる施策”が採用力そのものになる時代へ。
本記事では、今週注目された5つの最新ニュースを、保育施設の人事担当者の視点から「学び」「自園で活かせるヒント」に整理して解説します。
「採用が難しい」ではなく、“選ばれる園づくり”を戦略的に進めるための情報としてお役立てください。
① 「キャリアパス」と「人事評価項目」の作り方セミナー開催|継続的経営情報の見える化と加算の一本化に対応
■ 記事の要約
株式会社カタグルマが、保育園・こども園の経営者・園長・人事担当者向けに、「キャリアパスの設計」と「人事評価項目の作り方」を解説するオンラインセミナーを開催。近年の政策改定「継続的経営情報の見える化」「処遇改善等加算の一本化」を背景に、評価・役割・処遇の紐づけを強化する必要が高まっており、現場では曖昧な評価基準や不公平感が離職要因になっていることが課題とされている。この制度変更は、単なる補助金対応ではなく、人事評価の透明性を求める方向へ進んでいることを明確に示す内容となっている。
■ 人事担当者にとっての学び
・キャリアパスは採用PRの材料になる時代。
➡明確な成長イメージが提示できる園は求職者に選ばれやすい。
・評価制度は管理ではなく定着施策と捉える。
➡曖昧な評価は不満を生み、給与差や役割期待とのズレが離職へ直結する。
・政策や加算と人事制度は密接に関係するため、「制度を知ることが人事戦略」になりつつある。
■ 自分の事業所で検討できること
・評価項目を言語化し、誰が見ても理解できる基準の整備。
・キャリアパス/評価/処遇の三位一体設計。
・セミナーや外部研修を活用し、自園の制度ブラッシュアップの機会を定期化する。
② 園児置き去り防止カメラ「カメリアくん」販売開始|ICTで安全管理と業務負担を軽減
■ 記事の要約
園児に装着するICタグと連携した置き去り防止カメラ「カメリアくん」が販売開始。園児が設定範囲から離れた場合、スマホに自動通知される仕組みで、園外活動や送迎、園内移動など見落としが発生しがちな場面の安全性を高める。ICTによる「見える化」は保育士の心理的負担軽減にもつながり、事故防止の観点から導入を進める園が増加している。
■ 人事担当者にとっての学び
・安全対策は「採用ブランド」の要素。
➡事故防止に投資する園は保護者にも求職者にも信頼が高い。
・ICTは人の目を代替するのではなく、現場職員の負荷を軽減し、「人的ミスが起きる前提で対策する」姿勢が求められている。
・福利厚生の一環として「安心して働けること」は、現場職員の定着に直結。
■ 自分の事業所で検討できること
・事故ヒヤリハットの洗い出しとICT/アナログ双方の改善策の検討。
・保護者説明会における「安全管理ポリシー」の明文化。
・採用サイトや求人票に「安全対策の取り組み」を明示し、差別化材料にする。
③ ネクストビート「ストレスチェック機能」リリース|保育士の定着支援を強化、無償提供キャンペーン開始
■ 記事の要約
ネクストビートが、保育施設向けマネジメントツールに職員のストレスチェック機能を追加。2025年の法改正に伴い、ストレスチェック義務化対象が拡大されることを見据え、先行対応として無償キャンペーンを実施。メンタル不調は保育士の離職理由として上位を占め、特に人間関係・業務負荷・役割期待のズレが課題として挙げられる。この機能により、見えにくいストレスを数値化し、面談・導線改善・配置検討へつなげることを狙う。
■ 人事担当者にとっての学び
・メンタル対策は義務対応ではなく、定着戦略の中核。
・定量データによる気づきと対話設計が、離職予防のスタート。
・ストレスケアを公に取り組む園は「安心して働ける環境」の印象につながり、採用PRとしても有効。
■ 自分の事業所で検討できること
・チェック→分析→フォローを仕組み化するオペレーション。
・心理的安全性を高める1on1、業務棚卸、業務改善の導入。
・「健康管理」を経営課題に位置づけ、求職者へ発信する。
④ 全国で受講OK「保育士等キャリアアップ研修」Amazonギフトキャンペーン実施
■ 記事の要約
社会福祉法人絆友会が全国オンライン形式で令和7年度キャリアアップ研修を開催。正規非正規問わずリーダー層を担う保育士が必要とされる制度であり、処遇・役割・キャリアの明確化と連動。Amazonギフト付与という導線で申し込みを促進し、受講機会の拡大を図る取り組み。地方の園で講師を呼べない状況を補完する点でメリットが大きい。
■ 人事担当者にとっての学び
・研修制度は「採用競争力」。
➡教育投資ができる園は応募率/承諾率が高い。
・非正規/シニアのリスキリングに活用し、人材層を厚くする取り組みへ。
・評価制度と連動しない研修は“やらされ感”となり逆効果になる。
■ 自分の事業所で検討できること
・研修受講後の役割定義/評価/処遇をセットで提示。
・リーダー候補育成計画を中期的(3年)視点で策定。
・採用サイトに「研修提供」を明記し差別化。
⑤ 豊橋創造大学×保育園|学生考案のプログラムを園で実施する共同取組
■ 記事の要約
豊橋市が、豊橋創造大学の教育学系学生が考案した活動プログラムを実際に保育園で実施する取り組みを開始。学生にとっては実践的学習、園にとっては新たな活動導入と若手人材との継続接点づくりが可能。行政が関与することで信用性と認知が高まり、地域協働モデルの先行事例として注目される。
■ 人事担当者にとっての学び
・大学連携は採用と人材育成の両面に効く。
➡見学/実習/課題解決の連続接点は承諾率を高める。
・求職者が「園の雰囲気を体験できる」導線は強力なブランディング。
・現場が教える側に回ることで職員の自信と定着促進に寄与。
■ 自分の事業所で検討できること
・近隣大学/専門学校とテーマ型実習の設計。
・新卒/中途採用導線とつなげる仕組化。
・自治体や地域広報と絡めたPR展開。
▼まとめ|保育業界の採用は「集める」から「育てて選ばれる」へ
今週のニュースに共通するメッセージは、採用は単発施策ではなく、制度・育成・職場環境の総合戦略だということ。
・キャリアパス → 将来の見通し
・ストレスケア → 安心して働ける環境
・安全対策 → 信頼とブランド
・研修制度 → 成長できる園
・大学連携 → 採用導線の構築
採用難の時代において「選ばれる園づくり」が企業の人事戦略の中心になりつつあります。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年11月24日~11月30日の注目ニュース
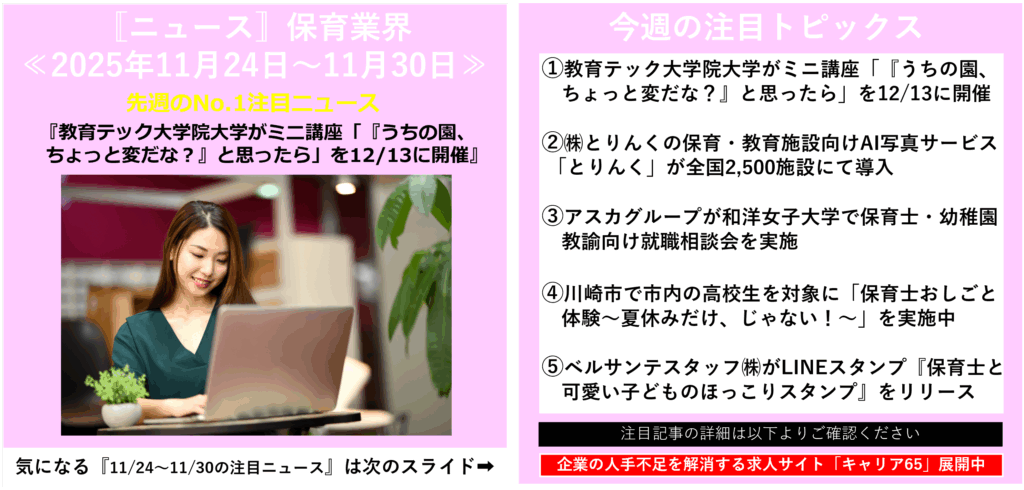
保育業界では、採用難・離職防止・職員の働きやすさ改善など、人事が直面する課題が年々複雑化しています。特に2025年以降は、DXの加速、教育機関との連携強化、若年層へのキャリア教育など、人材確保の取り組みが多様化しており、最新の動向を押さえることが採用力強化のカギとなっています。
本記事では、今週の保育業界で注目を集めた「人事・採用関連ニュース」を厳選して5本ピックアップ。
保育園の経営視点の講座、AIサービスの導入拡大、大学での就職相談会、高校生向けの保育体験、保育士を応援するLINEスタンプのリリースなど、採用担当者にとって重要なヒントが詰まった内容となっています。
「今、業界で何が起きているのか?」
「他園・他社はどんな取り組みをしているのか?」
「自分の園に取り入れられるものは何か?」
人事・採用に携わる方が“次の一手”を考える材料として、ぜひお役立てください。
① 保育園の「経営」とは 保育士の定着、園児の確保…マネジメントを学ぶ大学院ミニ講座
■ 記事の要約
教育テック大学院大学が、園経営者・主任・リーダー層向けに「保育園経営」をテーマとしたオンライン講座を開催するというニュース。講座名は「『うちの園、ちょっと変だな?』と思ったら ― 小さな違和感から見る組織のしくみ」。保育現場では、人間関係の不具合、役割分担の不公平感、情報共有不足など、日々の“小さな違和感”が積み重なることで離職につながるケースが多い。本講座では、こうした違和感の正体を組織論の観点から紐解き、採用難・離職・園児確保・組織運営の改善など、園の中長期的発展に向けたマネジメント力を学ぶ。続編として2026年1月には「忙しすぎる先生を助けるAI?」をテーマにした講座も予定されており、保育×経営×DXの流れがさらに強まっている。
■ 人事担当者にとっての学び
・離職は“突然起きるもの”ではなく、小さな違和感の積み重ねで発生する
・中堅層が経営視点を持つと、現場と管理の橋渡し役となる
・保育の質/採用/定着はすべて「園のブランド価値」に直結する
・経営視点を持った園づくりは、採用競争力の強化にもつながる
■ 自分の事業所で検討できること
・職員が日々の気づきを共有できる“早期サイン拾い”の仕組みを作る
・中堅職員の外部研修参加やキャリア支援を強化
・採用/定着施策をバラバラにせず、経営課題として一体で見直す
・次回のAI講座も含め、業務改善/DXの導入可能性を探る
② AI写真サービス「とりんく」全国2,500施設にて導入〜直近2カ月で500施設増加〜
■ 記事の要約
株式会社とりんくが提供するAI写真サービス「とりんく」が、全国2,500施設以上で利用されるまでに拡大した。特に直近2カ月で500施設も増加しており、急速な普及が進んでいる。「とりんく」は、AIが自動で子どもの笑顔や活動シーンを撮影・選別・整理し、保護者へスムーズに共有できる写真管理サービス。保育者の“写真撮影・整理・配信”といった時間のかかる業務を大幅に削減し、保育に集中できる環境づくりに寄与している。保護者からの評価も高く、園の魅力向上にもつながる取り組みとして注目されている。
■ 人事担当者にとっての学び
・ICT導入は働きやすさ向上だけでなく“離職防止”に直結
・写真業務の削減は、保育士の精神的/時間的負担を大きく軽減
・ICTを積極的に活用する園は、求職者から好印象を持たれやすい
・保護者満足度向上は園児募集にも影響し、“採用/定着と密接”
■ 自分の事業所で検討できること
・写真業務にかかる時間を可視化し、ICT導入の費用対効果を検討
・ICT導入を採用広報に活かし、「働きやすい園」をアピール
・保護者の満足度向上策として、写真共有システムの導入を検討
・ICT導入に使える助成金を調査し、低コストの導入案を検討
③ 保育学生向けサービス「園ぴった」が和洋女子大学で就職相談会を実施
■ 記事の要約
保育専門の人材サービスを展開するアスカグループが、和洋女子大学で保育学生向けの就職相談会を開催。保育学生向けサービス「園ぴった」と連携し、保育士・幼稚園教諭を目指す学生に対して、キャリアアドバイザーが個別に相談対応を行った。相談内容は「園の選び方」「働き方のリアル」「残業の実態」「人間関係」「園見学のポイント」など、求人票だけでは分からない“本音の不安”が中心。実習の振り返りや自己分析のアドバイスも行われ、学生側の満足度は高く、大学からも評価されている。
■ 人事担当者にとっての学び
・学生は“リアルな情報”を強く求めている
・大学との連携は採用接点として非常に効果的
・キャリアアドバイザーが介在すると、ミスマッチが減少する
・「園の選び方」を説明できる園は、信頼されやすく志望されやすい
■ 自分の事業所で検討できること
・保育系大学/短大との連携(個別相談会/説明会/園見学会)
・求人票では伝えにくい“リアルな情報”を整理して公開
・気軽に参加できる園見学イベントの常設化
・入職後のフォロー制度(メンター、1on1)を強化し、学生にアピール
④ 川崎市多摩区:高校生向け「保育士おしごと体験」受付中
■ 記事の要約
川崎市が、高校生を対象とした「保育士おしごと体験〜夏休みだけ、じゃない!〜」の参加者募集を開始。令和7年11月4日〜令和8年3月13日の期間で、市内の受け入れ施設(多摩区だけで15園以上)にて1日体験を実施。午前・午後のみも選択でき、参加費は無料。体験内容は、施設見学、保育体験、職員との交流、子どもとのふれあい、振り返りなど。高校生が保育の魅力や働き方を知ることで、進路選択の参考になると同時に、長期的な保育人材の育成を視野に入れた取り組みとなっている。
■ 人事担当者にとっての学び
・人材不足の時代は「高校生からの接点づくり」が重要
・行政と地域が連携した“人材育成の仕組み”は採用力の底上げにつながる
・現場体験はミスマッチ防止に効果的
・体験対応が良い園は、将来の志望度が高まりやすい
■ 自分の事業所で検討できること
・高校との連携による保育体験会/見学会の開催
・体験受け入れマニュアル(声かけ、案内、説明ポイント)の整備
・体験会を採用広報として活用し、園の魅力を発信
・体験後のフォロー連絡を行い、未来の求職者との関係構築
⑤ 保育士と子どもの笑顔を描いたLINEスタンプをベルサンテスタッフがリリース
■ 記事の要約
ベルサンテスタッフ株式会社が、保育士と子どもの笑顔をテーマにしたLINEスタンプをリリース。「先生ありがとうの日」(11月25日)に合わせて公開し、現場で働く保育士に“癒し”を届けることを目的とした企画。スタンプは「ありがとう」「おつかれさま」など、職員同士のコミュニケーションで使いやすい内容が中心となっており、忙しい現場でも気軽に使える工夫がされている。保育人材のメンタルケアや感謝文化を醸成する取り組みとして注目されている。
■ 人事担当者にとっての学び
・保育士のメンタルケアは離職防止に直結
・“感謝が伝わる仕組みづくり”が組織の雰囲気を大きく変える
・コミュニケーション活性は心理的安全性の向上に寄与する
・「職員をねぎらう文化」は採用広報でも強い魅力になる
■ 自分の事業所で検討できること
・ありがとうカード、称賛文化など感謝が伝わる仕組みの導入
・保護者対応にも使える柔らかいコミュニケーションツールの整備
・園独自のスタンプ制作によるブランド向上
・メンタルヘルス施策の一環として活用
今週のニュースを通して、保育業界の採用・人材育成は大きく変化していることが分かります。
AIによる業務効率化、大学・高校との連携、学生への情報提供の透明化、そして現場で働く保育士へのメンタルケアまで、採用活動は「人を集める」だけでなく、人を育て、職場を整え、現場の魅力を高める取り組みへと広がっています。
採用が難しい時代だからこそ、
・現場の声を拾う仕組み
・働きやすさを生むDX
・若年層との接点づくり
・感謝を伝え合う文化
といった、“園の魅力を高める地道な施策” が大きな差別化ポイントになります。
来週以降も、業界の動きを追いながら、採用・定着につながるヒントをお届けします。
あなたの園の採用成功と、そこで働く職員の笑顔が増えることを願っております。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年11月17日~11月23日の注目ニュース
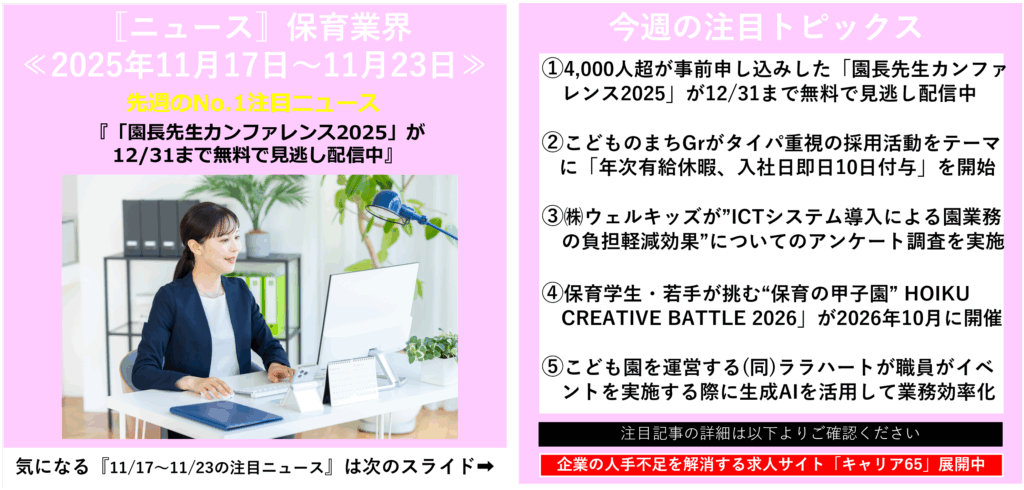
保育業界では、人材不足・採用競争の激化・職員の定着課題が年々深刻化しています。その一方で、ICT活用、新しいイベント企画、若手育成の仕組みづくりなど、各地の園では“人事・採用に直結する取り組み”が進んでいます。最新ニュースをキャッチすることは、単に情報収集をするだけでなく、「他園の成功事例を知る」「自園の改善ヒントを得る」「採用力を強化する」ために欠かせません。
本記事では、2025年11月17週に話題となった保育業界の人事・採用関連ニュース5本をピックアップし、人事担当者が押さえるべきポイントを“わかりやすく”“現場に落とし込める形で”解説します。
すべてのニュースに共通しているのは、
・職員の負担軽減
・働きやすさの向上
・若手の育成 / 確保
・ICT / AIの活用
これらが採用力のカギになっているということ。
「他園はどこまで進んでいるのか?」「自園では何を取り入れられるのか?」をイメージしながら読み進めてみてください。
① 園長先生カンファレンス2025が無料で見逃し配信中
■ 記事の要約
ICTサービス「コドモン」を運営する株式会社コドモンは、2025年10月に全国の園長・施設長を対象としたオンラインカンファレンス「園長先生カンファレンス2025」を開催しました。本イベントは3日間にわたり、保育の現状と未来をテーマにした全9セッションで構成。事前申込者数は過去最多となる4,479人に到達し、満足度96%、リピート希望99.5%という高い評価を獲得しました。オンライン開催により、全国から園長・施設長が気軽に参加できる点も評価され、「育成」「組織づくり」「ICT活用」「働き方改革」など、現場が直面する課題への関心の高さが浮き彫りになった形です。
■ 人事担当者にとっての学び
このニュースは、“園の学びの場”がすでにオンラインを中心に広がっていることを示しています。保育業界では人材不足が深刻化する一方、管理職層の成長意欲は高く、研修や学びの機会を求めるニーズが増加しています。
また、参加満足度の高さは「双方向性」「テーマの即時性」「実務に役立つ内容」が重要であることを示しており、人事側も研修設計のヒントを得られます。特に、ICT導入や職員育成に関する情報は採用力・定着率向上に直結するため、園の経営サイドとしても注視すべきポイントです。
■ 自分の事業所で検討できること
・園内研修も「オンライン+録画視聴」の形にすることで、忙しい職員でも学びやすい環境を作れる
・園長/主任クラス向けに月1回の“ミニ勉強会”を設け、学び続ける組織文化を育成
・採用説明会も双方向チャットや事例紹介を盛り込み、応募者の理解度・納得度を高める構成にする
・「現場課題の共有/改善会議」を定期的に設定し、経営陣とのコミュニケーション量を増やし、働きやすさ向上につなげる
② こどものまちグループ|入社即日10日有給付与の制度改定
■ 記事の要約
愛知県名古屋市を中心に保育園を運営する「こどものまちグループ」は、2026年4月より就業規則を改定し、正社員に対する年次有給休暇10日を“入社初日から付与する”制度に変更すると発表しました。従来の「6ヶ月後に付与」という一般的なルールから大きく踏み込み、働き方改革・タイムパフォーマンス(タイパ)の視点を取り入れたものです。背景には、保育士の早期離職を防ぎ、入社直後の不安や負担を軽減したいという狙いがあります。また、「時間=最も価値ある資源」と捉え、職員が自分の時間をより大切にできる環境をつくる取り組みの一環です。
■ 人事担当者にとっての学び
有給休暇は、採用競争力を高める強力なアピール材料になります。特に保育業界は「休めない」「休日が少ない」というイメージが根強いため、入社時点から休暇を確保できることは求職者にとって大きな安心材料です。また、入社初期の離職を防ぐためには“最初の1ヶ月のケア”が非常に重要であり、制度変更はそのケアの一環として効果的です。
さらに、「時間の価値」を制度で示すことで、園の文化や働き方の方針を社内外に強く発信できます。
■ 自分の事業所で検討できること
・「入社初月の特別休暇」「試用期間中の時短勤務」など柔軟な制度を追加
・採用ページで“時間の使い方を大切にする園”というメッセージを明確に打ち出す
・休暇取得率を上げるために、園長/主任が率先して有給取得を促す文化づくり
・中途採用者に対して、入社初月に1on1面談を必ず設定し、不安要素を早期に解消
③ ウェルキッズ|”ICTシステム導入による園業務
の負担軽減効果”についてアンケート調査
■ 記事の要約
株式会社ウェルキッズは、保育園・こども園におけるICTシステム導入効果の実態を明らかにするため、全国の保育従事者を対象にアンケート調査を実施。その結果、6割以上の職員が「明らかに業務が楽になった」と回答し、特に登降園管理・保育記録・保護者連絡の3領域で効果が高かったことが判明しました。また、ICTが現場にもたらす“保育に集中できる時間の創出”も評価されており、ICT化は単なる効率化ではなく、保育の質を高める要素として認識されつつあります。
■ 人事担当者にとっての学び
保育業界で深刻な課題となっている「事務負担の多さ」「残業の増加」に対し、ICT導入は直接的な解決策となり得ます。実際、離職理由の多くが事務作業の煩雑さであることから、ICT化は採用力向上にも寄与します。
また、導入後に“どの業務がどれだけ楽になったのか”を継続的に検証し、現場と改善を繰り返せる組織ほど職員満足度が高まります。人事としては、単にシステムを導入するのではなく、運用支援・定着支援までを含めた仕組みづくりが重要だと理解できます。
■ 自分の事業所で検討できること
・現場の業務量調査(事務作業の棚卸し)を実施し、ICT導入の優先順位を可視化
・ICT導入後のフォロー研修を定期的に実施し、職員の活用度を高める
・採用ページで「ICT化で残業削減」「記録がラク」という“働きやすさ”を明確にアピール
・保護者との連絡もデジタル化し、負担軽減とコミュニケーション品質の向上を同時に実現
④ “保育の甲子園”HOIKU CREATIVE BATTLE 2026が全国初開催
■ 記事の要約
一般社団法人信州子育てみらいネットは、2026年10月に全国の保育系学生・若手職員を対象とした“保育の甲子園”とも呼べる大型コンテストを長野県で開催すると発表しました。参加者はチームで理想の保育プログラムや未来の園像を企画し、プレゼンテーションや実践を通じて発表します。背景には、若い世代の保育離れや保育士不足があり、若者が“保育の未来を自分たちでデザインできる舞台”をつくることで、業界への関心を高める狙いがあります。
■ 人事担当者にとっての学び
若手の採用・定着には、“役割”“挑戦”“発信”の3つの要素が欠かせません。特に保育業界においては、若者が「保育は創造的な仕事だ」と感じられる機会が少ないため、こうしたチャレンジの場は非常に効果的です。採用活動においても、仕事内容の魅力を“ストーリー”として伝えることが重要であり、若手の声や挑戦事例を発信することは応募者増につながります。
■ 自分の事業所で検討できること
・学生インターンに「保育プログラム企画体験」などの創造型メニューを追加
・若手職員によるアイデアコンテストを社内で開催し、主体性を育む土壌づくり
・SNSで若手の活動や挑戦を積極発信して採用ブランドを強化
・短大/大学との連携イベントを企画し、早期母集団形成を進める
⑤ 合同会社ララハート|園職員が生成AIを活用したイベント開催
■ 記事の要約
合同会社ララハートは、秋の自然を舞台にした「親子の冒険イベント」に生成AIを活用したことを発表しました。園児と保護者が協力して楽しむこのイベントでは、キャラクター、ストーリー、イラスト、動画制作に生成AIを導入。これにより、外部委託していたクリエイティブ制作を園職員が自ら担えるようになり、企画の自由度が大きく向上しました。保育現場の表現力が拡張されただけでなく、職員の“主体的に企画・創造する経験”が働きがいにもつながり始めています。
■ 人事担当者にとっての学び
保育の仕事における「創造性」の価値が高まっています。ICTは業務効率化のためだけでなく、保育の質・園の魅力・職員のやりがいに直結するツールとして注目されます。デジタルスキルのある職員が活躍しやすい環境は、採用面でも強みとなり、若手・ミドル層の応募増が期待できます。また、園自ら情報発信できる力が高まることで、保護者からの信頼性や地域での存在感も向上します。
■ 自分の事業所で検討できること
・AIツールを使った広報動画/行事の企画を職員主体で進める環境をつくる
・「AI活用研修」を全職員に実施し、苦手な層のフォローアップも含めて定着支援
・採用広報で「ICT/生成AIを活用できる園」と明確にアピールし、応募者の幅を広げる
・地域イベントや季節行事と組み合わせて、園の魅力を発信する新しい企画を作成
今回取り上げた5つのニュースから、今後の保育業界の人事・採用において特に重要となる視点が明確になりました。
■① ICT・AI活用は“効率化”だけでなく“魅力づけ”の時代へ
業務削減ツールとして導入されたICTは、現在では「働きやすさ」「職員の創造性」「園のブランド力」を高めるための戦略的な施策へと進化しています。ICT化の有無は、求職者の応募の判断材料にもなる時代です。
■② 休暇・時間の価値を重視する制度が採用力を左右
入社初日からの有給付与のように、「安心して働ける」「無理なく働ける」制度は、採用の決め手になるだけでなく定着率向上にも効果的。保育業界全体で“時間の価値”を見直す動きが加速しています。
■③ 若手が“挑戦”できる環境づくりが必須に
若年層の業界離れが続く中、HOIKU CREATIVE BATTLEのような“挑戦の場”は、業界全体のイメージアップにも直結。園内における小さな挑戦機会であっても、若手採用・定着には効果があります。
■④ 研修・学びの場のオンライン化は定着
園長カンファレンスの盛況ぶりは、保育業界が「学ぶ文化」を求めている証拠。オンライン研修や双方向型イベントは今後さらに広がり、採用説明会にも応用可能です。
■⑤ 地域・保護者との共創が園の魅力になる
生成AIを活用したイベントのように、「園の特徴」や「職員の主体性」を見せる取り組みは、保護者からの信頼にもつながり、結果として採用力の強化にも寄与します。
総じて、今回のニュースは “働きやすさ”“学び続ける風土”“若手の挑戦”“ICT・AI活用” が、これからの採用戦略・組織づくりの中心になることを示しています。
ぜひ、自園でも取り入れられる要素から少しずつ試し、人材が集まり・育ち・定着する組織づくりにつなげていきましょう。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年11月10日~11月16日の注目ニュース
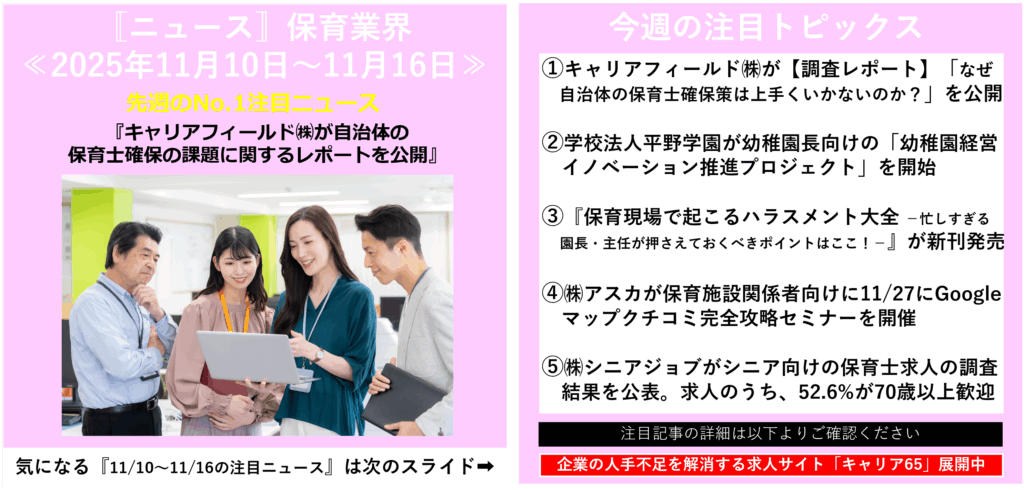
2025年11月10日週も、保育業界では「採用・人事」に関わる重要なニュースが多数発表されました。
少子化が進む一方で、保育士不足はますます深刻化し、各園では“採用力”そのものが園経営の生命線になりつつあります。
今回の記事では、
人事・採用担当者が必ず押さえておきたい最新ニュース5本 を厳選し、
それぞれの内容と“自園で活かせる実践ポイント”をわかりやすく整理しました。
① 保育士確保策が上手くいかない根本理由
② 園経営の質そのものを高める全国初の取り組み
③ ハラスメント対策の必読書
④ 口コミが採用を左右する時代の新戦略
⑤ シニア採用が保育現場の救世主になる理由
など、どれも“今日から改善できるヒント”にあふれています。
ぜひ、自園の採用戦略や園づくりに役立ててください。
① キャリアフィールド調査:潜在保育士110万人と“保育士確保”の現実
■ 記事の要約
キャリアフィールド株式会社の調査レポートでは、保育士不足の根底にある“構造的な問題”が明らかになっています。
表向きには「潜在保育士110万人」という大きな数字が存在するものの、実際に復職したいと考える人はごく一部にとどまり、その背景には「人間関係の悩み」「業務量の多さ」「給与の低さ」など、改善されていない現場の課題が横たわっていると指摘。また、自治体ごとの支援加算によって保育士の“奪い合い”が進んでおり、地域間競争が激化する一方で「業界全体のパイは増えていない」という現状が浮き彫りになっています。
■ 人事担当者にとっての学び
本レポートからの最大の学びは「お金の上乗せでは保育士不足は解決しない」という点です。
求職者が重視しているのは“園の雰囲気・人間関係・働き方の柔軟さ”。つまり、採用成功の鍵は“待遇より環境整備”にあります。
■ 自分の事業所で検討できること
・ICT導入による事務負担の軽減
・中堅層のマネジメント教育
・小さなトラブルを相談できる体制整備
・園としての理念や働き方の明文化
・採用ページに“働きやすさ”の根拠を掲載
② 全国初「幼児教育×経営学」K-Innovationプロジェクト開始
■ 記事の要約
岐阜県の学校法人平野学園(キートスガーデン幼稚園)は、日本初となる“幼児教育と経営学を体系的に学ぶ園長向けプログラム”を開始。
3年間で「財務・人的資本・業務改善・戦略・組織運営」などを段階的に学び、属人的な園運営から、持続可能で再現性のある経営体制へ移行することを狙います。昨年度のトヨタ生産方式の導入に続く大胆な取り組みとして、業界全体から大きな注目を集めています。
■ 人事担当者にとっての学び
このプロジェクトが示すのは「園長の経営力=採用力」ということです。
園のマネジメント品質は、離職率・求職者の安心感・園児募集・園のブランドに直結します。
■ 自分の事業所で検討できること
・園長 / 主任向けのマネジメント研修導入
・園内の理念 / パーパスの再整理
・業務改善サイクルの仕組み化
・チーム運営の標準化(属人性の排除)
・園児募集と採用戦略の連動
③ 保育業界向けハラスメント大全(新日本法規出版)発売
■ 記事の要約
新日本法規出版が、保育業界のハラスメントを具体例つきで体系的に解説した書籍『ハラスメント大全』を発売。パワハラ・セクハラ・マタハラ・介護ハラ・カスハラ・園児への不適切対応など業界特有の課題を網羅し、初動対応や再発防止策を詳しくまとめた“現場で使える実務書”となっています。
■ 人事担当者にとっての学び
ハラスメント対策は採用・定着の両面で最重要テーマ。
特に“保護者からのカスハラ”は園の信頼問題にも直結するため、正しい知識と対応フローが不可欠です。
■ 自分の事業所で検討できること
・園内ハラスメント規定の整備
・職員向け研修
・保護者対応ガイドライン
・園内相談窓口の設置
・トラブル事例の共有
④ アスカ:Googleマップ口コミ完全攻略セミナー
■ 記事の要約
株式会社アスカが開催する「Googleマップ口コミ対策」セミナー第2弾では、口コミを“園の採用力”として活かす手法を紹介。保護者からのレビューが求職者の応募判断に影響するようになった今、口コミ改善は採用戦略の重要要素となっています。
■ 人事担当者にとっての学び
・口コミ=園の第一印象
・マイナス評価は応募離脱の原因
・良い口コミは採用ブランディングになる
■ 自分の事業所で検討できること
・レビュー対応ルールの策定
・保護者満足度アンケートの実施
・口コミページの導線設置
・園の雰囲気を伝える動画制作
⑤ シニアジョブ:保育業界のシニア採用調査
■ 記事の要約
シニア専門求人サイト「シニアジョブ」による調査では、保育業界でシニア採用が急増。求人の52.6%が「70歳以上歓迎」と回答し、実際に就業した最年長は72歳。資格の有無による採用差も小さく、シニアの安定感や丁寧な関わりが高く評価されています。
■ 人事担当者にとっての学び
シニア採用は若手確保が困難な園にとって有力な解決策。
勤怠の安定、短時間勤務との相性の良さ、保護者からの安心感など多くのメリットがあります。
■ 自分の事業所で検討できること
・シニア向け短時間求人の設計
・担当業務の切り分け
・「70歳以上歓迎」を明記
・多年代チームの体制づくり
今回紹介した5つのニュースは、保育業界の“いま”を象徴しています。
共通するキーワードは 「園の魅力は園内でつくられる」 ということです。
① 職員が働きやすい環境
② 園長のマネジメント力
③ ハラスメント対策
④ 口コミによる透明性
⑤ 多年代の協働体制
どれも“採用力そのもの”につながる要素であり、
人事・園運営の両面で手を入れることで大きな改善が期待できます。
ぜひ、自園の状況と照らし合わせながら、できるところから取り組みを進めてみてください。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年11月3日~11月9日の注目ニュース
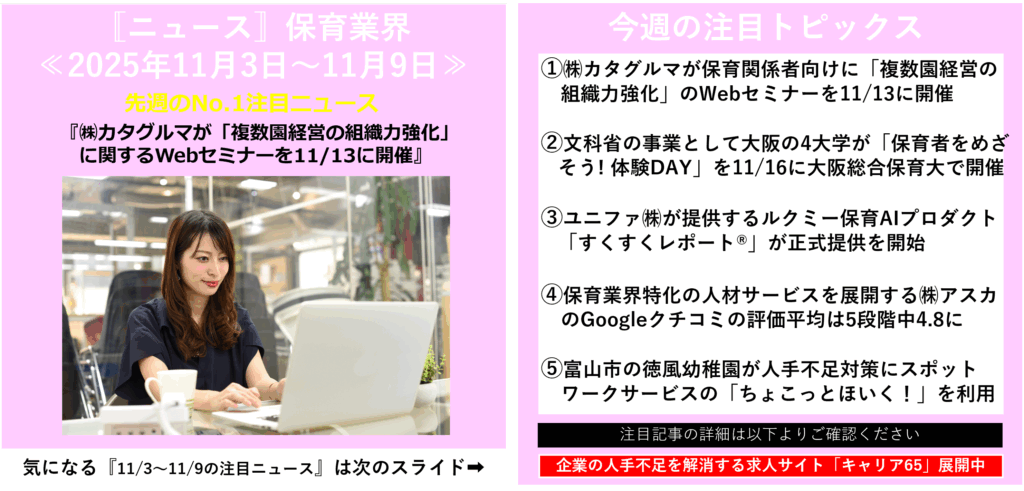
保育業界では「人材不足」や「採用の多様化」に関する動きが活発です。
今週は、組織づくり・採用広報・AI導入・口コミ活用・柔軟な働き方など、業界の変化を感じるニュースを5本ピックアップしました。
① 株式会社カタグルマ|「人依存」から脱却する仕組み経営セミナー
複数園を運営する法人を中心に注目されているのが、株式会社カタグルマが主催するオンラインセミナー「保育業界の未来を拓く!『人依存』からの脱却と『仕組み』で自律する組織へ」です。
このセミナーは、保育園運営の属人化を防ぎ、現場のノウハウを「人ではなく仕組み」で継承していくことをテーマにしています。
人材不足が続く中で、園の運営はどうしても“経験豊富な特定職員”に依存しがちです。そうした状況が続くと、担当者が異動・退職した際に業務が滞ったり、園全体の品質が低下するリスクがあります。
カタグルマは、こうした課題に対し、「業務の見える化」「マニュアル整備」「情報共有体制の構築」など、データと仕組みに基づく運営改革を提案しています。
人事担当者にとっての学びは、“採用して終わり”ではなく“定着し続ける仕組みづくり”の重要性にあります。
教育・評価・管理が属人的なままだと、優秀な人材も離れてしまいます。逆に、ルールや指針を明文化することで、新人も安心して働ける環境が生まれます。
採用広報でも、「仕組みで支える園運営」は求職者に安心感を与える強力なメッセージとなります。
今後は、業務フローを整理し、OJTの手順や情報共有の方法を標準化するなど、“誰でも回せる園運営”を目指す取り組みが加速するでしょう。
② 大阪総合保育大学|保育の魅力を伝える「体験DAY」開催
文部科学省の事業として、大阪総合保育大学が中心となり、大阪教育大学・大阪常磐会大学・大阪キリスト教短期大学の4校が連携して開催する「保育者をめざそう!体験DAY」。
このイベントは、中高生や保護者を対象に、保育の楽しさと社会的意義を“体験”で伝えることを目的としています。
会場では人工雪を使った「雪あそび」や「紙コップうさぎ工作」、音楽に合わせた「びよんびよんダンス」などが行われ、子どもと関わる仕事のリアルな楽しさを実感できる内容でした。
ゲストには全国で活躍する“ゆうちゃん”こと三原勇気氏が登場し、軽快なトークとダンスで会場を盛り上げました。
この取り組みが示すのは、「体験を通じた採用広報」という新しい方向性です。
保育の現場を知るきっかけが少ない若年層に対して、イベントを通して“憧れ”や“共感”を生み出すことは、将来の人材確保に直結します。
特に、保育士を目指す動機の多くが「子どもが好き」「ありがとうと言われる仕事がしたい」といった感情的要因であることを踏まえると、感情に訴えるアプローチは非常に有効です。
事業所としても、学校や地域団体と連携して“1日仕事体験会”や“園見学ツアー”を開催するなど、採用の裾野を広げる工夫が求められます。
③ ユニファ|AIで業務効率化「すくすくレポート®」提供開始
ユニファ株式会社は、保育AIブランド「ルクミー」シリーズの新製品として「すくすくレポート®」の正式提供を開始しました。
このプロダクトは、園児の生活記録をAIが自動で分析し、成長の傾向や日々の変化を“見える化”するもの。
2024年の試験運用ではすでに全国600施設が導入しており、業務負担の軽減や記録精度の向上が報告されています。
これまで、保育士の業務は「記録」「連絡帳」「報告書」など手作業が多く、1日あたりの事務作業時間が1〜2時間に及ぶケースもありました。
「すくすくレポート®」では、AIが自動で文章を提案し、データをもとに発達記録を作成するため、職員の作業時間を大幅に削減します。
AI導入は、単なる効率化にとどまらず、人材定着や採用力強化にも寄与します。
“テクノロジーで現場を支える”という姿勢は、求職者にとって「働きやすさ」の象徴です。
求人票や採用サイトにICT環境を明記することで、若手・復職希望者・子育て世代など幅広い層に魅力を訴求できます。
また、自治体とのデータ連携が進めば、園運営全体の最適化や職員教育の高度化にもつながる可能性があります。
AIの活用は、今後の「保育の質×人材戦略」を両立させる重要な鍵となるでしょう。
④ 株式会社アスカ|Googleクチコミ2,000件突破・平均評価4.8
保育人材専門の株式会社アスカが、Googleクチコミ2,000件を突破し、平均評価4.8という高い満足度を達成しました。
全国の求職者からは「担当者の対応が丁寧」「条件交渉も親身に行ってくれた」「紹介先の園の雰囲気まで教えてくれる」といった声が寄せられています。
この結果は、単なる“求人紹介”を超えた、伴走型のキャリア支援が評価されている証拠です。
保育士の転職市場では、働き方・人間関係・給与条件など多様な希望があり、それを一人で探すのは難しいもの。
アスカのような専門エージェントの存在が、求職者の心理的負担を減らし、保育業界全体の離職抑止にも寄与しています。
人事担当者にとって重要なのは、採用活動に「第三者の信頼」をどう活かすかです。
園の公式サイトや求人票での発信に加え、クチコミ・利用者の声・在職者インタビューを積極的に公開することで、“信頼できる職場”という印象を構築できます。
また、紹介会社とのパートナーシップを築き、定着支援まで見据えた採用戦略を練ることも有効です。
⑤ FNNプライムオンライン|注目の「スポットワーク」モデルが拡大
富山テレビの特集「急成長する『スポットワーク』市場」は、保育・介護・農業などエッセンシャルワークの現場で進む“単発雇用モデル”の広がりを紹介しています。
富山市の徳風幼稚園では、保育士マッチングサービス「ちょこっとほいく!」を導入。
資格を持ちながらフルタイム勤務が難しい“潜在保育士”が、1日単位・3時間単位で勤務し、欠員補助や行事サポートを行っています。
この仕組みのメリットは、働き手・園双方に柔軟性をもたらすこと。
職員が有給休暇や研修を取りやすくなり、現場には経験豊富なサポート人材が入る。
潜在保育士にとっても、子育てと両立しながらスキルを活かせる機会となっています。
富山県の保育士有効求人倍率は2.61倍と高止まりしており、従来の“常勤採用一本化”では人手不足を解消できません。
スポットワークは、「少し働きたい人」と「少し人がほしい園」を結ぶ新たな採用モデルとして注目されています。
今後は自治体や複数園の連携により、地域全体で人材をシェアする仕組みが広がる可能性があります。
今週の5本に共通するキーワードは、
「仕組み化」「共感採用」「デジタル活用」「口コミ信頼」「柔軟雇用」
人材不足が常態化するなかで、園運営に必要なのは「採用数」よりも「持続可能な働き方の設計」です。
仕組みで支える組織、共感で惹きつける採用、デジタルで負担を減らす仕組み、そして柔軟な雇用形態。
これらを組み合わせることで、職員も利用者も笑顔になれる“次世代の保育経営”が実現します。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年10月27日~11月2日の注目ニュース
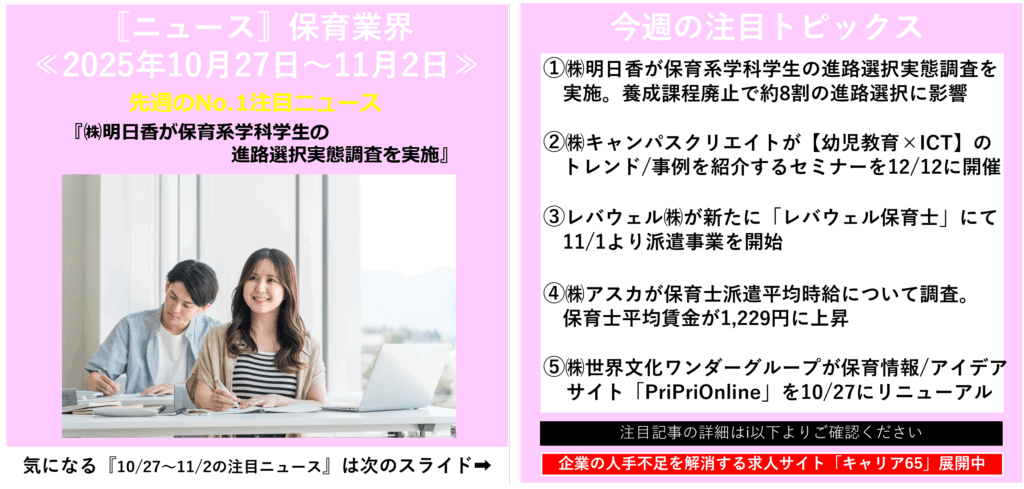
① 保育士を目指す学生に異変|養成校廃止で57.7%が「就職先確保に不安」
■記事の要約
株式会社明日香が実施した調査によると、保育士を目指す学生の57.7%が「就職先確保に不安」を感じている一方で、85.7%が「保育の仕事に就きたい」と回答しました。しかし、約3割が「他職業にも興味がある」と答えており、保育士志望者の意欲と不安が交錯する現状が浮き彫りとなりました。背景には、少子化の加速に伴う保育施設数の減少や、保育士養成校の閉校・縮小が相次いでいることがあります。これにより、学生が「安定して働ける職場を見つけにくい」という構造的課題が発生。記事は、保育人材確保の持続可能性を問う内容となっています。
■人事担当者にとっての学び
採用の現場では、“学生が抱く将来不安”への理解と支援が求められています。給与や待遇面だけでなく、「キャリアを描ける」「長く働ける」安心感を伝える採用設計が必要です。養成校の減少により採用母集団が縮小する今こそ、学校連携・地域連携・インターン企画などを通じた“早期接点づくり”が有効です。
■自分の事業所で検討できること
・養成校との協働で実習/見学/体験型説明会を開催し、早期から学生に職場を体感してもらう。
・採用広報で「研修制度」「キャリア支援」「人間関係の良さ」など、“不安を解消する情報”を打ち出す。
・新卒保育士に対してメンター制度やフォロー面談を整備し、入職後の定着支援を強化する。
このニュースは、採用難の要因が「志望者減」ではなく「不安の増大」にあることを示唆しています。信頼される保育現場づくりが、次世代の人材確保のカギです。
② 幼児教育×ICT|デジタル活用が保育の質を変える
■記事の要約
株式会社キャンパスクリエイトが開催したセミナー「幼児教育×ICT」では、国内外のデジタル教育事例や、保育現場の課題解決に挑むスタートアップの取り組みが紹介されました。海外ではAIやデジタルポートフォリオを活用した教育の個別最適化が進んでおり、日本でも登降園管理システムや保護者連絡アプリ、教育記録のクラウド化など、業務効率と保育の質向上を両立する動きが広がっています。ICTは単なる「省力化ツール」ではなく、「人が人に向き合う時間を生み出す手段」として位置づけられています。
■人事担当者にとっての学び
・保育人材の不足を「人手の拡充」だけでなく、“仕組みで補う”デジタル戦略として捉える視点が重要。
・ICT導入は採用/定着の両面で効果があり、現場負担を減らすことで離職率低下やモチベーション維持にも寄与。
・新たな採用基準として、ICTリテラシーを持つ保育人材の育成/採用が求められる。
■自分の事業所で検討できること
・登降園/連絡帳/勤怠管理のクラウド化を進め、事務負担を軽減。
・ICT導入にあたっては、現場職員の声を反映したツール選定を行い、現場との乖離を防ぐ。
・空いた時間を「子どもと関わる時間」や「研修/対話の時間」に充て、職員のやりがいを高める。
ICTは「人を減らす」ためではなく、「人の力を最大化する」ための仕組みです。保育業界におけるDXの進展は、今後の採用競争力にも直結するテーマとなるでしょう。
③ レバウェル保育士が派遣事業を開始|潜在保育士の復職を支援
■記事の要約
レバレジーズ株式会社のグループ会社・レバウェル株式会社は、保育人材に特化した新サービス「レバウェル保育士」を通じて派遣事業をスタート。ネオキャリアから保育士派遣事業を譲り受け、即戦力人材を柔軟に配置できる体制を整えました。同社は、出産や育児で一時的に離職した潜在保育士の復職支援にも注力。ブランクのある人が安心して再就労できる環境づくりを掲げています。
■人事担当者にとっての学び
・採用手段の多様化が進み、派遣/紹介予定派遣/パート雇用の組み合わせが主流に。
・潜在保育士を活かすには、勤務時間の柔軟性と復職サポートが不可欠。
・人材会社との連携を戦略的に活用することで、“採用できない”から“つながり続ける”へ発想転換できる。
■自分の事業所で検討できること
・常勤+派遣+短時間勤務のミックス型人員配置を導入し、安定的な人材運営を実現。
・ブランク人材を迎える際の「再教育プログラム」や「短期トライアル勤務制度」を設ける。
・採用後は派遣元企業と協働し、勤務フォローや評価面談を定期的に実施。
この動きは、保育人材の活用範囲が「採用」から「マネジメント」へ広がっている象徴的事例です。固定観念にとらわれず、柔軟な雇用戦略を描くことが今後の鍵です。
④ 保育士平均時給1,229円に上昇|待遇改善競争が加速
■記事の要約
株式会社アスカの調査によると、令和8年度の保育士派遣平均時給は1,229円と前年より上昇しました。物価高騰や最低賃金の引き上げに加え、経験者確保のための競争激化が背景にあります。同社は全国平均を上回る高水準を維持し、地方でも時給1,200円超の案件が増加中。記事では、賃金上昇が「人手不足」「採用コスト上昇」「待遇競争の常態化」という構造的課題を浮き彫りにしています。
■人事担当者にとっての学び
・給与水準の引き上げだけではなく、総合的な働きやすさ(シフト/福利厚生/人間関係)が重要。
・派遣/パート市場における報酬競争の中で、非金銭的な魅力をどう打ち出すかが採用の差別化ポイント。
・賃金情報を定期的に分析し、地域相場に見合った待遇設計をする必要がある。
■自分の事業所で検討できること
・自園の給与/時給を地域平均と比較し、採用競争力を可視化。
・「給与以外の魅力」として、研修/表彰/感謝文化の仕組みを整える。
・派遣スタッフとの関係を“補充”ではなく“チームの一員”として再設計する。
賃金上昇は避けられない現実ですが、待遇+働く意義を両立させる戦略が、今後の採用ブランドを左右します。
⑤ 保育情報サイト「PriPriOnline」リニューアル|現場支援の新プラットフォーム
■記事の要約
株式会社世界文化ホールディングスが運営する「PriPriOnline」がリニューアル。保育士が日常業務で使える製作アイデア・指導計画・行事運営のヒントを網羅し、使いやすさと検索性を大幅に改善しました。現場の声を反映した設計で、季節行事や年齢別保育計画、保護者対応の資料などをダウンロード可能。保育者が創造的に働くための情報基盤として注目されています。
■人事担当者にとっての学び
・「学び続けられる環境」が、離職防止と定着促進のカギ。
・保育士が日々の業務を通じて自己成長できる仕組みを設けることで、採用後の満足度向上につながる。
・情報共有やナレッジ活用は、チームの一体感を高める重要な人事施策でもある。
■自分の事業所で検討できること
・PriPriOnlineなど外部サイトを活用した職員の学びの場づくりを行う。
・OJTだけでなく、オンライン研修や記事共有ミーティングで知識を循環させる。
・採用広報で「学び合う文化」「情報を共有する職場」を打ち出し、働きがいを訴求する。
このリニューアルは、保育の現場が“孤立した現場”から“学び合う職場”へ進化するきっかけになる可能性があります。デジタル活用を通じて、人材の育成とエンゲージメントを高めるチャンスといえます。
今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年10月20日~10月26日の注目ニュース
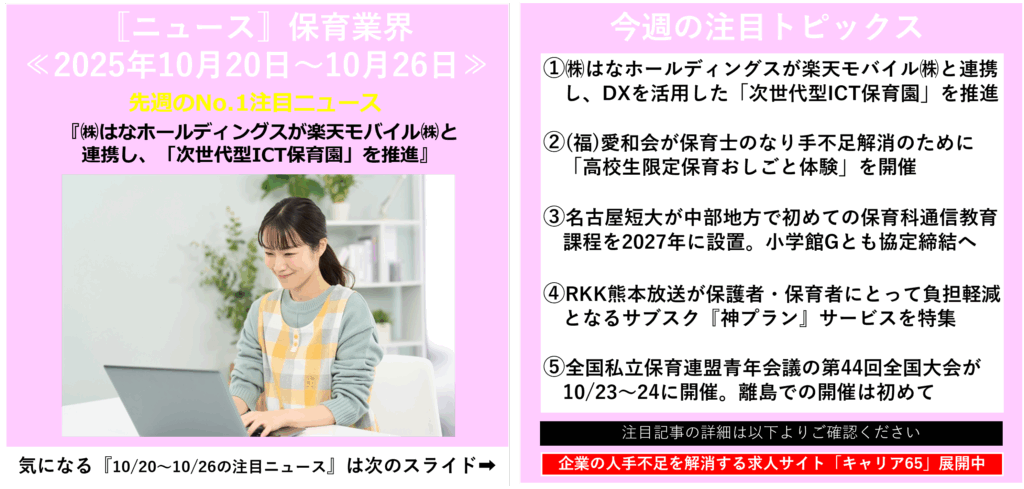
今週は、テクノロジー導入・労働環境改革・人材育成・地域連携と、保育業界の“未来志向”を象徴するニュースが相次ぎました。
人事・採用担当者の皆さまにとっても、今後の戦略づくりに役立つ実例ばかりです。
① はなホールディングス×楽天モバイルが推進する「次世代型ICT保育園」
保育事業を展開するはなホールディングスが、楽天モバイルと提携し、AI・IoT技術を活用した「次世代型ICT保育園」構想を発表。
AIカメラによる安全管理、IoT連携による健康・活動データの自動記録、タブレットを使った保育士業務の効率化などを進めることで、職員負担の軽減と保育の質向上を両立する狙いです。
・人事の学び:ICT化が離職防止のカギ。
業務をデジタル化し「書類作業」や「安全チェック」を自動化することで、保育士が“子どもと向き合う時間”を確保できます。
採用活動でも「ITで働きやすさを高める園」としてアピールすれば、若手層・再就職希望者への訴求力が増すでしょう。
② 高校生に“リアルな現場”を体験させ、次世代へバトン
奈良県天理市の社会福祉法人 愛和会(宮古保育園)が、高校生を対象に保育おしごと体験会を実施。
勤怠管理のデジタル化、不要業務の削減、待遇10%改善などを進めた結果、離職率は10%→5%に減少。
職員が主体的に提案できる「すごい会議」やレクリエーションを通じて、心理的安全性の高い職場文化を築いています。
・人事の学び:経営層の覚悟が改革を動かす。
労働環境改善と人材育成を同時に進める姿勢が、採用ブランディングに直結。
また、体験会のような“現場発信型採用広報”は、若手の関心を育む効果が高いでしょう。
③ 名古屋短大×小学館G、通信制「保育科」開設へ
名古屋短期大学が2027年度、中部初となる保育科通信教育課程を開設予定。
小学館アカデミーグループと提携し、全国の園職員が通信で保育士資格+幼稚園教諭免許を取得可能に。
学費は3年間で約65万円と低価格に設定されています。
・人事の学び:採用と育成を一体化する時代へ。
「未資格でも働きながら学べる」制度は採用間口を広げ、定着率向上にも寄与します。
自園で通信制短大との提携を進めれば、“資格取得支援がある職場”として差別化できます。
④ “荷物ゼロ登園”が実現!保育サブスクの広がり
熊本県合志市の豊岡ゆうすい保育園では、月額6,600円でおむつ・着替え・タオルを園が用意する“荷物ゼロ登園”を導入。
保護者の負担を減らすだけでなく、保育士の業務効率化にもつながり、子どもと向き合う時間が増えました。
さらに、熊本市の「ニチイキッズほたくぼ保育園」ではおむつ無料提供を実施。
全国100以上の自治体で「おむつサブスク」制度が導入され、宮崎県高原町では自治体助成で保護者負担が月800円に。
・人事の学び:業務DX=採用力アップ。
“便利な園”は“選ばれる園”でもあります。
人事としては、サブスク導入を「働きやすさ改革」として求人PRに活用する視点が重要です。
⑤ 全国私立保育連盟青年会議、初の離島開催
鹿児島県奄美大島で開催された全私保連青年会議全国大会(第44回)には、全国から約360名が参加。
「つむぐ」をテーマに、伊豆大島・五島・屋久島の園長が登壇し、地域ぐるみの保育の魅力と課題を共有しました。
登園時の「虫はOK」エピソードに象徴されるように、自然と共生する離島保育の温かさが語られる一方、少子化・人手不足の現実も浮き彫りに。
・人事の学び:採用は“地域とともに育てる”視点で。
地域資源を活かし、地元高校や短大と連携して若手を育成・雇用する“地産地育モデル”の重要性が示されました。
「つむぐ」というテーマは、まさに人と地域、保育と社会をつなぐ人事戦略を象徴しています。
まとめ|“人材戦略”は保育の未来戦略
今週の5本に共通するキーワードは、
「デジタル」「育成」「共創」「地域」「ゆとり」。
採用難の中で求められているのは、“人を増やす”より“人が続く仕組みをつくる”こと。
AIやサブスクといった最新トレンドから、地域ぐるみの保育まで、あらゆる取り組みが“保育者が笑顔で働ける環境づくり”につながっています。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年10月13日~10月19日の注目ニュース
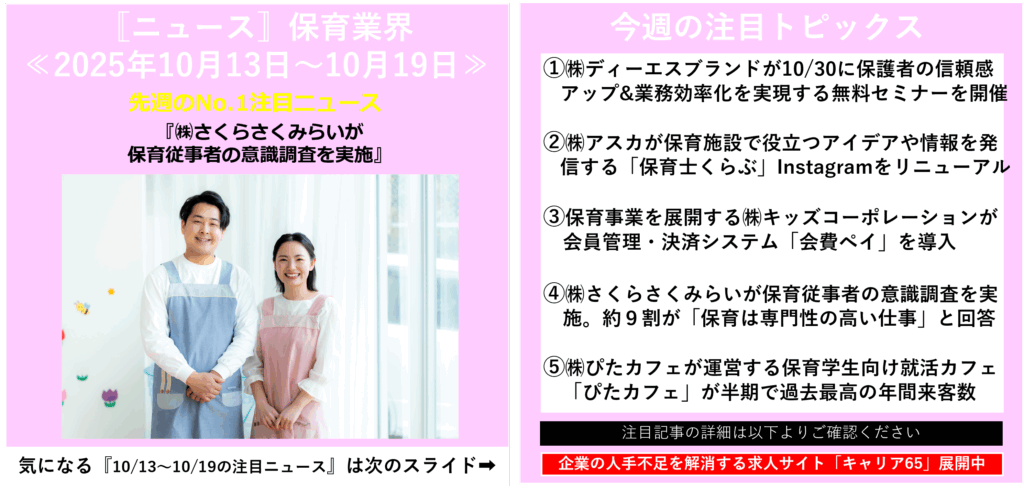
はじめに|採用・定着のヒントが満載!今週注目の保育業界ニュース
保育業界では、採用難・離職率の高さといった課題が続く一方で、ICT導入や働き方改革、広報手法の多様化など、変革の動きも広がっています。今週(2025年10月第3週)は、保育現場を支える「人」と「仕組み」に関する注目ニュースが多数登場しました。
本記事では、現場の負担軽減・採用ブランディング・専門性向上・学生リクルートの4つの観点から、人事担当者が押さえておきたい最新トピックをピックアップします。
① 保護者の信頼感アップ×業務効率化セミナー開催(株式会社ディーエスブランド)
株式会社ディーエスブランド、日本ソフト開発、リコーの3社共催による「保護者の信頼感アップ&業務効率化を実現する無料セミナー」が10月30日にオンラインで開催されます。テーマは“選ばれる園になるためのICT活用”。登降園管理やお知らせ配信、写真共有など、保育業務のデジタル化を通じて、保護者の満足度と職員の働きやすさを両立する方法が紹介されます。
保育業界では近年、事務作業の多さが離職の一因とされており、ICTによる効率化が重要課題です。本セミナーは、保育の質を保ちながら職員の時間を生み出す実践的なヒントを提供。さらに、ホームページやSNSを活用した園の魅力発信についても解説されます。
人事担当者にとってのポイントは、「ICT=採用・定着の武器」として活用する視点を持つこと。
業務効率化は単なるコスト削減ではなく、“働きやすさ”という採用ブランディング要素にもなります。
求人票や採用説明会で「ICTを活用し、保育士が子どもと向き合える時間を確保しています」と伝えるだけでも、求職者の印象は大きく変わるでしょう。
② 「保育士くらぶ」公式Instagramがリニューアル(株式会社アスカ)
株式会社アスカが運営する保育士・幼稚園教諭向け求人メディア「保育士くらぶ」は、公式Instagramを2025年10月に全面リニューアル。
デザイン刷新に加え、「季節の制作アイデア」「行事準備の工夫」「現場あるある」など、現場の先生が明日から使える情報を発信するコンテンツへと進化しました。
SNSを通じた発信は、いまや採用ブランディングの重要な要素です。保育士志望の学生や転職希望者は、求人票よりもまずSNSで園の雰囲気を確認する傾向があります。
また、現職員にとっても「役立つ情報を得られる場」があることで、モチベーションや業界への愛着を維持しやすくなります。
人事担当者の視点では、公式アカウントを単なる広報ツールではなく、「採用×定着」双方を支える発信拠点として活用するのがポイント。
園の魅力を伝える“働く人のリアル”を発信し、SNS上でも「この園で働きたい」と思わせる接点づくりを進めましょう。
③ 会費ペイ導入で業務負担を7〜8割削減(キッズコーポレーション×ペイメントフォー)
株式会社キッズコーポレーション(東京都港区)は、株式会社ペイメントフォーが提供する会員管理・決済システム「会費ペイ」を導入。全国の保育施設で請求・入金確認などの業務を自動化し、現場の負担を大幅に削減しました。
従来の現金集金や口座確認といった作業が不要になり、経理担当者による照合作業は7〜8割削減。保護者からも「手続きがスムーズ」「支払い管理がしやすい」と高い評価を得ています。
結果として、職員が子どもと向き合う時間を確保でき、保育の質の向上にもつながっています。
人事の観点では、業務効率化は“働きやすさの可視化”そのもの。
求職者に「ICTを積極導入している園」と印象づけることができ、採用力の強化にも直結します。
また、こうした改善事例を社内外に発信することで、職員の誇りやエンゲージメントも高まります。
④ 「保育の専門性」を再考する意識調査(株式会社さくらさくみらい)
株式会社さくらさくみらいが実施した「保育の専門性に関する意識調査」によると、約9割の保育従事者が『保育は専門性の高い仕事』と認識している一方で、社会からその専門性が十分に理解されていないと感じる人が7割を超える結果となりました。
このギャップは、保育士のモチベーションや定着に大きく関わる課題です。
専門職としての誇りが社会的に正しく評価されない環境では、「報われない」「評価されない」と感じる人が増え、離職リスクが高まります。
人事として注目すべきは、「学び・キャリア支援」の整備。
専門性を磨ける研修・資格支援・キャリアパスの可視化を進めることで、職員の“成長実感”を育むことができます。
また、保護者や地域に対しても保育士の専門性を発信し、「保育=専門職」という認識を社会に広げることが、採用ブランディングの一環となるでしょう。
⑤ 「ぴたカフェ」が年間来客数を半年で突破(株式会社ぴたカフェ)
株式会社ぴたカフェが運営する保育学生向け就活支援スペース「ぴたカフェ」は、2025年4〜9月の来客数が1,935名を突破し、過去最高の年間記録を半年で更新したと発表しました。
「ぴたカフェ」は、園長や採用担当者と学生がカジュアルに話せる“就活カフェ型イベント”を展開。
求人サイトでは伝わりにくい“園の雰囲気”や“人柄”を直接感じられることが好評で、学生と園のミスマッチ防止にもつながっています。
採用トレンドの変化として注目すべきは、学生が「条件」よりも「人・雰囲気」を重視している点。
人事担当者は、“説明会”よりも“交流の場づくり”へと発想を切り替える必要があります。
リアルイベント・SNS・動画など、多面的な接点を設けることで、「選ばれる園」への第一歩となります。
まとめ|“選ばれる園づくり”のカギは「人」と「仕組み」
今週のニュースから見えてくるキーワードは、
「ICT化」「発信力」「専門性」「リアルなつながり」の4つです。
採用難の時代こそ、人事担当者が果たすべき役割は“採用”だけではなく、
・働きやすい環境(仕組み)をつくる
・職員が誇れる職場を発信する
・社会に専門性を伝え、業界全体の価値を上げる
という“園全体のブランディング”に広がっています。
採用の現場を変えるのは、制度ではなく人の姿勢。
現場・人事・経営が一体となって、「選ばれる園」への進化を続けていくことが、これからの時代の最大の競争力になるでしょう。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年10月6日~10月12日の注目ニュース
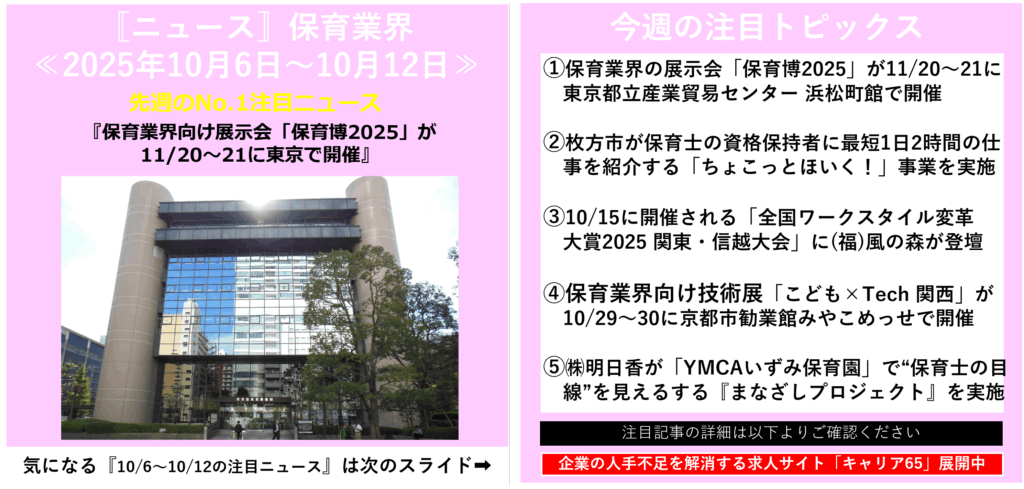
① 園の課題解決に国内最大級の保育・教育フェア「保育博2025」開催
全国から約200社が集結し、保育・教育分野の課題解決をテーマに開催される「保育博2025」。
展示ゾーンは「学習教材」「ICT」「発達支援」「人材」など多岐にわたり、業界の最新ソリューションが一堂に揃います。
特に注目したいのは、発達支援や人材採用に関する展示・セミナーが増えている点。
保育現場では「経験者採用」だけでなく、研修・育成・ブランディングを組み合わせた採用設計が求められています。
セミナーでは、著名な教育実践者やコンサルタントが登壇し、職員の定着や職場づくりのヒントが得られます。
人事担当者にとってのポイントは、「採用イベント」ではなく「課題解決の場」として保育博を活用すること。
採用ブース出展・企業連携・他園とのネットワークづくりなど、現場と経営をつなぐ“学びと発信”の場として有効です。
② 短時間保育士ウェルカム 最短1日2時間から働ける新制度(大阪府枚方市)
枚方市が試行を開始した「短時間保育士」紹介制度は、1日2時間から勤務可能という画期的な仕組みです。
出産・育児・介護などで現場を離れた有資格者が再び保育の仕事に戻れるよう、市がマッチングを支援。
潜在保育士の掘り起こしと、人材不足解消を狙います。
人事担当者にとっての学びは、「柔軟な働き方が採用力を高める」こと。
“フルタイム限定”ではなく、“短時間でも歓迎”という姿勢を打ち出すことで、応募層が一気に広がります。
求人票には「ブランクOK」「2時間勤務も可」といったメッセージを加え、安心して応募できる雰囲気を作りましょう。
また、自治体との連携は採用活動の新しい選択肢。
人材紹介や復職支援セミナーなど、地域の支援制度を積極的に活用することで、採用の質とスピードを両立できます。
③ 「人が辞めない働き方」を学ぶチャンス『全国ワークスタイル変革大賞』関東・信越大会
2025年10月15日(水)、横浜で開催される「全国ワークスタイル変革大賞 関東・信越大会」は、
“離職しない職場”づくりをテーマにした実践型フォーラムです。
社会福祉法人・NPO・民間企業など、業界横断で7組が登壇し、保育業界からは「社会福祉法人風の森」が参加。
保育士の働き方改革に挑むリアルな事例が紹介されます。
注目すべきは、「理論」ではなく「現場からの変革」を重視している点。
保育現場でも、小さな業務改善・仕組み化・意識改革が職員定着のカギになります。
大会で紹介される他業種の事例も、園のマネジメントや評価制度の改善に応用可能です。
人事部としては、「働き方=福利厚生」ではなく「業務設計そのもの」を変える視点を持つことが重要です。
生産性と離職防止の両立を実現する実践ヒントを吸収しましょう。
④ 教育×テクノロジーの最前線「第2回 こども×Tech 関西」開催(京都)
2025年10月29〜30日、京都市勧業館みやこめっせで「こども×Tech 関西」が開催されます。
「学校」「保育」「子育て」を支援する最新技術が集結し、AI教材、登降園管理、健康モニタリングなどのICTソリューションが多数登場。
園務効率化、保育の質向上、人材育成の分野で活用できる具体的な事例が紹介されます。
人事担当者にとっての注目ポイントは、“人を増やす前に、仕事を変える”発想。
ICT導入は採用対策そのものでもあり、
「残業削減」「事務の自動化」「負担の可視化」は、結果的に定着率を高めます。
また、採用広報にも「ICT導入園であること」を打ち出すと、若手・潜在層にとって魅力的な職場イメージになります。
展示会は、採用戦略とDX推進を同時に学べるリアルな場です。
⑤ “保育士の目線”を見える化 YMCAいずみ保育園「まなざしプロジェクト」
兵庫県神戸市の「YMCAいずみ保育園」が始めた『まなざしプロジェクト』は、
カメラを活用して保育士の“まなざし”を可視化し、保育の質とチーム連携を高める画期的な試みです。
職員同士で映像を振り返り、「どんな声かけをしているか」「子どもとの距離感はどうか」を共有することで、
保育スキルの標準化と心理的安全性の向上を実現。
「評価」ではなく「共有」を目的にした取り組みが、新人育成や離職防止の好循環を生んでいます。
この事例は、「テクノロジー×人間理解」という次世代の人材育成モデル。
映像分析や振り返りミーティングなど、自園でも取り入れやすい要素が多く、
“見える化でチームを育てる”発想が保育人事の新たな潮流になりそうです。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年9月29日~10月5日の注目ニュース
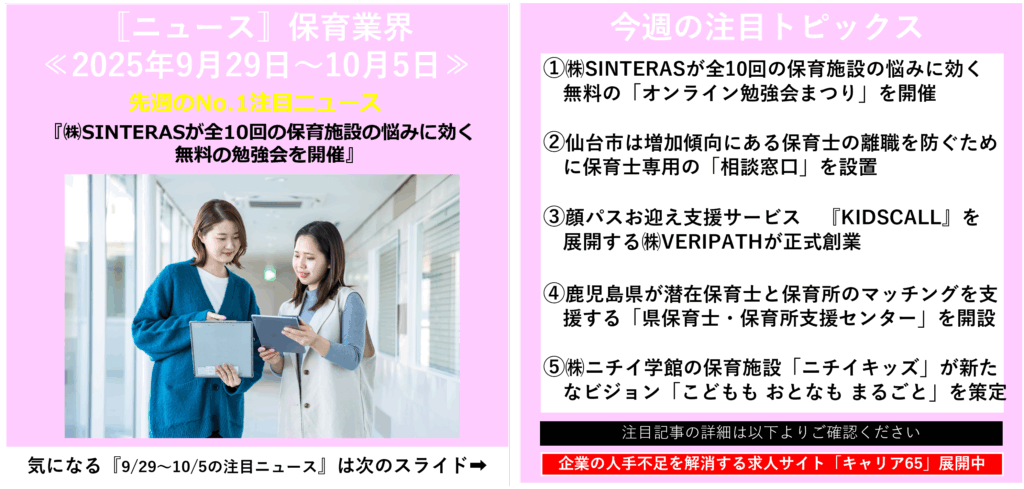
① 無料オンライン勉強会まつり開催|保育業界のDX・採用力強化セミナー
株式会社SINTERASは、保育園・幼稚園・認定こども園向けの「オンライン勉強会まつり」を開催中です。
全10回・完全無料のオンライン講座で、SNS活用・AI導入・採用広報・業務効率化など、現場が抱える課題に即した内容を提供しています。
特に「LINE発信」「ショート動画」「Googleビジネスプロフィール(MEO対策)」といった実践テーマが注目されています。スマホ1台で参加でき、現場スタッフも気軽に学べる点が魅力です。
人事の学び は、「発信力=採用力」であるという点。求人広告任せではなく、園の魅力を日常的に発信することが応募数増加につながります。
まずはSNS投稿を週1本から始め、Googleプロフィールを最新情報に保つことから始めましょう。
② 仙台市が「匿名相談窓口」を設置|保育士離職防止に新たな仕組み
仙台市は9月29日、保育士の離職防止を目的に、匿名でも相談できる電話窓口を開設しました。
市内約380施設を対象とした調査で、2023年度の離職率は15.1%。再び上昇傾向にあることを受けての対応です。
専門の保育士や臨床心理士が対応し、職場の悩みや人間関係、ストレスなどを匿名で相談可能。予約制で平日10時〜19時に対応します。
人事の学び は、「第三者相談体制の効果」。内部では話しづらい悩みを外部専門家が受け止める仕組みが、離職防止に直結します。
自園でもGoogleフォームによる匿名意見箱や外部カウンセラーとの提携など、低コストで導入可能な仕組みづくりを進めましょう。
③ 顔パスでお迎え!VERIPATHが「KIDSCALL」提供開始
株式会社VERIPATHは10月1日、保育施設向け**顔認証お迎え支援サービス「KIDSCALL(キッズコール)」**を正式リリースしました。
顔認証技術により、代理お迎え時の本人確認を自動化。お迎え業務の効率化と安全性向上を両立する仕組みです。
導入により、
・不審者対応/防犯強化
・登降園履歴の自動管理
・保育士の負担軽減
が実現します。
人事の学び は、ICT導入が「働きやすさ=採用力」につながるという点。
顔認証のような業務効率化は、単なる便利ツールではなく、離職防止と採用ブランディングの両面で効果を発揮します。
④ 鹿児島県に保育士・保育所支援センター開設|潜在保育士1200人を掘り起こし
鹿児島県は10月1日、「県保育士・保育所支援センター」を開設しました。
資格を持ちながら離職中の「潜在保育士」と保育施設をマッチングする専門窓口で、県内では約470人が不足している一方、潜在保育士は約1,200人に上るとされています。
支援員が希望条件を丁寧にヒアリングし、個別にマッチング。求職・求人ともに無料で利用可能です。
人事の学び は、「潜在人材の掘り起こしが即効性のある採用策」であること。
“ブランクOK”“短時間勤務可”など柔軟な条件提示をすることで、復職希望者を受け入れやすくなります。復職支援研修やOJTを用意すれば、早期戦力化も可能です。
⑤ ニチイキッズが新ビジョンを発表|“こどもも おとなも まるごと”で広がる保育の未来
全国約350拠点を展開する「ニチイキッズ」は、2025年10月1日に新ビジョン「こどもも おとなも まるごと」を策定しました。
この理念は、子どもだけでなく保護者・地域・職員など“保育に関わるすべての人”を支えるという包括的な姿勢を示しています。
こども家庭庁調査では「満足している」保護者が9割を超える一方、「負担を感じている」層も6割にのぼり、この課題に応える内容です。
人事の学び は、理念を“経営メッセージ”で終わらせず、
・保護者支援
・職員ケア
・地域との連携
へと実装していく点にあります。
理念を採用ブランディングに結びつけることが、園の信頼度と応募意欲を高める鍵になります。
★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★
□2025年9月22日~9月28日の注目ニュース
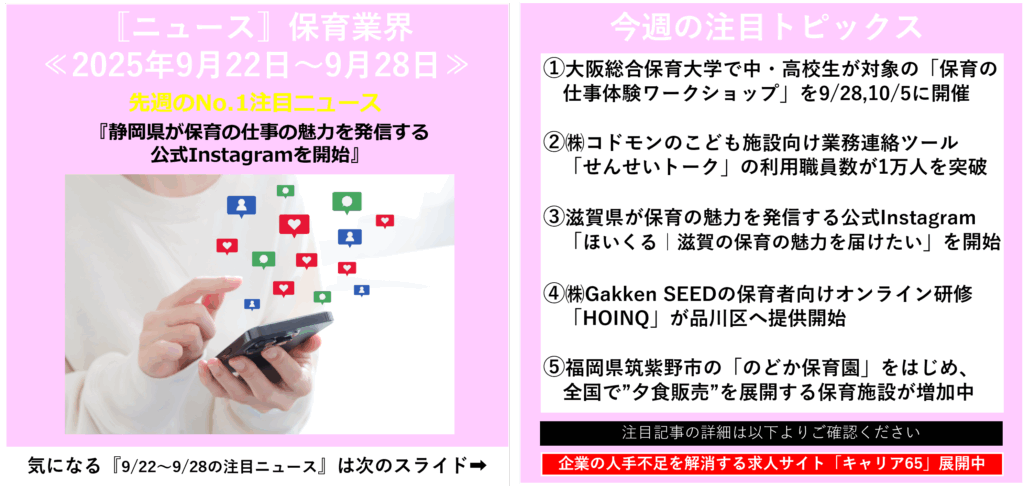
① 大阪総合保育大学が中高生を対象に「保育体験ワークショップ」を開催。
■ 記事の要約
大阪市東住吉区の大阪総合保育大学が、地元の中学生・高校生を対象とした「保育体験ワークショップ」を実施します。9月28日と10月5日に各1時間、無料で開催。内容は、流行のダンスアレンジで保育表現を体感する「流行りのダンス編」、紙コップを使った遊び方を考える「紙コップ編」など。講師には「ハッピーダンスおにいさん」三原勇気さんが登壇し、若い世代に保育の魅力を体験させる企画です。
■ 人事担当者にとっての学び
このような体験型イベントは、将来の応募者との早期接点をつくる「タレントプール」構築の手段となります。中高生の段階から保育という仕事を身近に感じさせることで、「保育士になってみたい」という志望形成を促せる可能性があります。また、地域との連携強化によって、地元出身者の採用や定着につながることも期待されます。さらに、体験イベントで感じた生徒の反応(興味を持った内容、質問、好評だったプログラム)を採用広報の素材に活かすこともできます。「どういう切り口で保育を伝えると響くか」の実地データとして蓄える価値があります。
■ 自分の事業所で検討できること
・近隣の中高生向け体験会を主催する
→自施設で園見学や保育体験を実施し、施設スタッフと触れ合う場をつくる。たとえば、子どもと一緒に簡単な遊びをする時間、保育の裏側見学、職員との座談会などを織り交ぜる。
・体験会で使えるプログラム素材を用意する
→ダンス、手遊び、工作といった“体験要素”を取り入れて、中高生世代が楽しめる内容を企画。保育の楽しさや魅力が伝わるよう演出する。
・体験会参加者の情報をフォローアップ
→参加してくれた中高生に対して連絡先(メールやSNS)を聞き、将来の進学・就職情報を案内したり、施設見学の案内を送付したりする。これにより、将来の候補者リスト(タレントプール)ができる。
・地域の学校/教育機関と連携を図る
→地元の学校・進路指導部と協力し、進路説明会や授業連携を通じて保育職を紹介する機会を作る。自治体とコラボすることも検討できる。
② せんせいトーク、利用職員数1万人を突破
■ 記事の要約
株式会社コドモンが提供する職員間連絡アプリ「せんせいトーク」が、正式リリースからわずか2か月で全国700施設以上に導入され、利用職員数1万人を突破しました。従来の口頭・電話・紙メモや個人アプリ利用の課題(伝達ミス・情報漏洩リスクなど)を解消し、緊急連絡やシフト調整、ヒヤリハット報告まで一元化。パート含む全員への一斉連絡も可能で、既読確認や研修動画機能も搭載。導入施設では業務削減や職場雰囲気改善の効果が報告されています。
■ 人事担当者にとっての学び
保育現場の「連絡業務効率化」は職員の離職防止にも直結します。情報伝達の不備がストレスや人間関係悪化を招く中、業務専用ツールの導入は心理的負担軽減につながります。また、パート職員を含めた公平な情報共有は、チーム一体感を生み、採用後の定着率を高めるヒントになります。
■ 自分の事業所で検討できること
・既存のLINEやメールを業務連絡から切り離す
→ 私用アプリ混在を防ぐ
・職員全員がアクセスできる専用連絡ツールを導入
→ パート・短時間勤務者も含めた公平な情報共有
・研修動画やマニュアルの一元化
→ 新人教育の効率化と品質維持
・導入後は定量効果を測定
→ 業務削減時間や職員満足度を数値化し、人事戦略の改善に活用
③ 滋賀県、保育の魅力を発信するInstagram開設
■ 記事の要約
滋賀県は保育士不足の解消に向けて、若者や学生に保育の魅力を伝えるため公式Instagramを開設しました。コンテンツは保育士インタビューや支援制度紹介、インフルエンサーによる現場体験など。月10本程度のショート動画投稿を予定し、養成校や駅でのポスター掲示も行います。
■ 人事担当者にとっての学び
SNSを活用した採用広報は、保育業界のような慢性的な人材不足分野で有効な手段です。ターゲット層に親しみやすい媒体を使うことで、従来の求人媒体に頼らない「攻めの採用活動」が可能になります。
■ 自分の事業所で検討できること
保育施設や法人単位でも、InstagramやTikTokを活用し、日常の保育風景や職員の声を発信できます。求人広告費を大きくかけずに、自然な形で応募者に働く魅力を伝えることができ、応募の質・量の向上につながるでしょう。
④ 学研オンライン研修「HOINQ」、品川区に導入
■ 記事の要約
学研グループのGakken SEEDは、保育園・幼稚園・こども園向けオンライン研修サービス「HOINQ(ほいんく)」を2025年9月1日から品川区の公立保育所で提供を開始しました。現在、全国で170施設に展開中です。
このサービスは次のような特徴を持ちます。
・15分のスキマ時間で受講可能
・一方向講義だけでなく、職員同士の“学び合い”を重視
・実務現場で起きやすい課題を題材とした実践型内容
導入園からは、「主語が“私”から“私たち”に変わった」「遠慮しがちだった意見が出しやすくなった」といった、組織文化や職員間の対話に変化が出てきたという声も聞かれています。
■人事担当者にとっての学び
・研修時間確保の難しさへの対応
→保育業界は多忙さゆえに研修時間を確保しづらいという構造的課題があります。15分で受講できるよう設計されたサービスは、受講ハードルを下げ、継続性を担保する手法として参考になります。
・双方向学び/意見交換の場づくり
→単なる講義型研修ではなく、職員同士の気づき合いや意見交換を促す仕掛けが、組織文化や心理的安全性を高める要素になります。
・現場課題を素材にする研修設計
→日常の困りごとや実務で起こり得る事例を研修テーマに取り入れることで、学び−実践の接続が強まり、研修内容の実効性が上がる可能性があります。
・定性的変化を捉える視点
→「主語が変わった」「意見が出やすくなった」など、研修後の職場の空気変化を観察することも、人事施策の成果指標にできるというヒントになります。
■ 自分の事業所で検討できること
・外部研修サービスとの連携検討
→自施設でゼロから作るのが困難な場合は、HOINQのような既存サービスを試験導入してみるか、その設計思想を参考に導入を検討。
・短時間研修コンテンツの導入検討
→自施設でも「5〜15分程度」で学べる動画・eラーニング教材を用意し、勤務の合間や休憩時間で少しずつ研修できる仕組みを整える。
・内製研修素材を現場事例から作る
→日常で起こりやすいトラブルや対応の困りごとをテーマにしたワークを用意し、職員同士で意見を出し合う“学び合い”形式の短時間研修を実施。
・研修後のフォローアップ機会を設ける
→研修を受けた後、ディスカッション会やアンケート、振り返り会を設けて、気づきの共有と行動変化につなげる。
・効果/観察記録を行う
→研修導入前後で職員の発言傾向、職場の空気、離職率などに変化がないかを観察・記録し、研修制度を改善していく。
⑤ 保育園で“夕食販売”の取り組みが拡大
■ 記事の要約
福岡県筑紫野市「のどか保育園」では、共働き家庭の負担を減らすため、週1回夕食用の惣菜販売「こどもごはん」を開始。管理栄養士が給食とバランスを考えて献立を作成し、1パック150~400円程度で販売。鶏の竜田揚げや煮物など、家庭の夕食にすぐ使える内容です。保護者からは「仕事終わりに助かる」と好評で、他地域でも無人販売の導入が始まっています。
■ 人事担当者にとっての学び
家庭負担を軽減するこうした支援策は、保育園を「働く親の強力なパートナー」として位置づける効果があります。職員側にとっても「保護者から感謝される」環境は働きがいにつながり、採用や定着のアピールポイントになります。また、時代背景に応じたサービス提供が、園のブランド力向上に直結することが示されています。
■ 自分の事業所で検討できること
・夕食サポートの検討
→調理スタッフや外部業者と連携し、惣菜やレトルト食品を保護者向けに販売。
・保護者ニーズの把握
→アンケートを実施して「どんなサービスがあれば助かるか」を聞き、採用広報やサービス改善に反映。
・福利厚生的なPR活用
→こうした取り組みを採用説明会や求人票でアピールし、求職者に「家庭と両立できる園」と印象付ける。
・小規模な実験導入
→まずは月1回など試験的に実施し、保護者の反応を見ながら拡大を検討。

★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★


